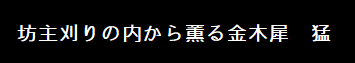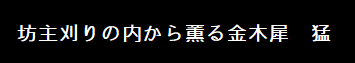| 10月も半ば、世界が "from bad to worse" という感じで変化しているとしか思えない2020年でしたね。2021年になってもそれが変わるのかどうか・・・一つの境目は11月の米大統領選挙でしょうね。ここでトランプが勝つようでは、アメリカ自体がメルトダウンしてしまう。何とかアメリカ人に頑張ってもらいたいですよね。そのトランプ夫妻がコロナに感染したことについてスガ首相がお見舞いのツイッターを送ったのだそうですね・・・と、この件については『むささびの鳴き声』で語らせてもらいます。 |
目次
1)スライドショー:マグナムの秋
2)むささび「重大」ニュース
3)ある新聞人間の生涯
4)労働党首は保守主義者?
5)英和辞書
6)鳴き声
|
1) スライドショー:マグナムの秋
|

|
世界を代表する国際的な写真家のグループにマグナム・フォト(Magnum Photos)という組織があります。ご存知の方も多いと思います。設立は第二次大戦直後の1947年で、事務所をニューヨーク、パリ、ロンドンに構え(過去には東京にも事務所があった)、現在約50名の写真家・フォトジャーナリスト(報道写真家)が在籍している。ロバート・キャパ、アンリ・カルティエ=ブレッソン、ジョージ・ロジャー、デヴィッド・シーモアらは特に有名で、日本人としては久保田博二(1939年生まれ)という写真家が会員になっている。ここに集めたのは「秋」をテーマにしたマグナムの写真家たちの作品です。 |
|
back to top |
2)むささび「重大」ニュース
|
 |
「ニュース」にもいろいろありますよね。一見すると何でもないけれど、実際には世の中に重大な影響を与える可能性があるのも「ニュース」だけれど、一見すると何でもないし、将来も世の中に重大な影響をもたらす可能性もゼロ・・・でも何となくおもろいというのも「ニュース」よね。というわけで、おそらく後者の部類に入るであろうローカルな話題を紹介します。 |
|
|
ボウリングというゲームは、10本立っているピンめがけてボウルを2回投げて何本倒せるかを競うものですよね。一発で10本とも倒してしまうのを「ストライク」と言い、2回投げて全部倒すと「スペア」と呼ぶ。ボウリングにはもう一つ「ノータップ」という記録もあるんだそうですね。それは1投目で9本のピンを倒したら、「ストライク」とみなすというやり方です。
米ペンシルベニア州にマッキーズ・ロックス(McKees Rocks)という町がある。人口は約6000人。その町にケネディ・レーンズというボウリング場があるのですが、そこでこのほどレーン始まって以来という画期的な記録が生まれた・・・とKDKA-TVというローカルテレビ局が伝えております。ある女性が"no tap 300"という記録を達成したのですが、これは10フレーム(野球でいうイニングのようなもの)すべてにおいて一投目で10本中9本のピンを倒すという記録なのだそうです。
この大記録を達成したのはサラ・ライオンズ(Sara Lyons)という女性なのですが、すごいのは彼女の年齢で、11月30日が来ると97才になるとのことであります。ここをクリックすると彼女のプレーぶりを見ることができる。彼女がボウリングを始めたのは27才のときというから、70年間プレーし続けているってことですが、"no
tap 300"を達成したのはこれが初めてだそうです。
- ここまでボウリングを続けてこれた理由についてサラは「一心不乱に家族の面倒を見てきたことで健康な身体と集中心を保てたこと」(healthy and alert)とコメントしている。泣かせる…。
|
言葉に気を付けよう
 |
北イングランドのリンカンシャーにある野生動物センター(Lincolnshire Wildlife Centre)で飼育されている約200羽のオウムのうち5羽だけが、バラバラに隔離飼育されることになったという「事件」です。彼らはアフリカン・グレイ・パロットと呼ばれる種類のオウムなのですが、隔離の理由は、5羽が集まって汚い言葉で罵り合うという行為を繰り返したからなのだそうです。「汚い言葉で罵り合う」ことを英語では"swear"とか"foul-mouth"と言いますよね。例えば「出ていけ!」というのは、普通なら
"Get out!" と言うのに "F---off!" と言ってみたりする。"Damn-it!"とか"Jesus
Christ!"などもこれにあたる。日本語でいうと「くそ野郎」とか「ドアホ」などがそれにあたるのかもしれない。
で、問題の5羽(ビリー、エリック、タイソン、ジェイド、エルジーという名前がついている)ですが、今年の8月に別の動物園から一緒に連れてこられたものなのですが、このセンターに加入した途端に5羽がかたまってお互いにののしり始めたのだそうです。オウムの
"swearing" は珍しいことではないけれど、普通は小屋の中でぶつぶつやるもの。なのにこの5匹は客のいる前で、しかも5羽固まって
"swearing" の大合唱をやり始めるというので、センターの関係者も首をかしげている。ただ「おもろいオウムがおるやんけ」というので、却って話題を呼んでいるのだから、無理に隔離することもないという意見はもちろんあったけれど、固まってやられるのでは子供(人間の)の教育に良くないというので、バラバラにされることになった。
- 確かに5匹が一斉に "F---off!" とやるのは、「壮観」だけど、人によっては顔をしかめるかもしれないな。
|
R・ニクソンが食べ残したサンドイッチ
 |
アメリカの大統領選挙がどうなるのか、さっぱり分からなくなってきたけれど、ちょうど60年前(1960年)の大統領選に関連して信じられないような話がある。共和党の候補者だったリチャード・ニクソンが、選挙運動のためにイリノイ州のサリバン(Sullivan)という町を訪れたのですが、町の有志がニクソン訪問を記念する野外昼食会を開いた。もちろんニクソンも参加してチキン・サンドイッチを食したのですが、半分食べ終わったところで出席者たちと話をするために席を離れた。それを見ていたのがボーイ・スカウトをやっていたスティーブ・ジェニーという少年で、誰も見てないことを確かめてから、ニクソンが食べ残した半分のサンドイッチを紙に包んで家へ持って帰り冷蔵庫にしまい込んだ。
スティーブとしては、子供心に「有名人の食べ残し=希少価値」というつもりで、他人にもそれを言いふらして歩いていたところ、それが有名になってしまい、ついには「ニクソンの食べ残し」をテレビが取り上げるまでになってしまった。そうなるとスティーブも有名人としてトークショーにゲストとして招かれたりするようになり、別の有名人の食べ残しをもらったりするようになってしまった。
そして今年(2020年)9月22日、ニクソンの食べ残しは家宝としてスティーブの家の冷蔵庫で60年目を迎えることになったというわけ。サンドイッチは紙に包まれており、'Save, don't throw away'という言葉がしっかり描かれているのだそうです。
- ちなみに食べ残しの本人(リチャード・ニクソン)は26年前(1994年4月)にこの世を去っています。
|
| ▼最後の「ニクソンの食べ残し」ですが、よくもまあ60年も保管しておいたものですねぇ。1960年の大統領選といえば、民主党のJFケネディと共和党のリチャード・ニクソンの間の争いで、初めてテレビを使った討論会が行われた選挙だった。ケネディは上院議員、ニクソンはアイゼンハワー政権の副大統領だったのですが、これが得票数の点で大接戦で、ケネディが全体の49.7%、ニクソンは49.6%だった。ちなみにニクソンがサンドイッチを食べ残したイリノイ州はケネディ陣営が勝っているのですが、得票率はケネディが49.98%でニクソンは49.80%、票差は1万票以下だった。これほどの接戦選挙も珍しいであろうから、例の「食べ残し」が家宝扱いされるのも無理ないか。 |
|
| back to top |
3)ある新聞人間の生涯
|

|
前号(459号)の「むささびの鳴き声」で、ハロルド・エバンズ(Sir Harold Evans)というジャーナリストが92才で亡くなったことを紹介しました。むささび自身はこの人のことを知らなかったのですが、英国メディアはいずれも「巨星墜つ」という雰囲気で伝えていました。9月27日付のThe
Observerが社説で彼の死について語っています。一人のジャーナリストの死を、その人間が所属したわけではない新聞の社説が論ずるというのも珍しいのでは?書き出しが次のようになっている。
|
 |
16才で新聞記者に
ハロルド・エバンズは、1928年イングランド生まれで両親はウェールズ人。ジャーナリストとしてのキャリアは16才のときにイングランドのランカシャーにある小さな町の新聞社に務めたことから始まっている。その後、大学新聞の編集者などを務めたりした後にManchester Evening News で副編集長、北イングランドのNorthern Echoという地方紙の編集長となり、1968年、38才のときにロンドンへ移り住み、1970年代にSunday Timesの編集長として活躍した。
The Observerは
- 新聞界という部族社会において全員の意見が一致する(Unanimity)ことは極めて稀であるが、ハロルド・エバンズが世代を超えて最も人を鼓舞する編集長であったということには誰の異論もないだろう。 Unanimity is a rare commodity in the tribal world of newspapers, but there has, rightly, been no dissent from the view that Evans was the most inspiring editor of his generation, and perhaps of any.
と言っている。 |
 |
| ▼新聞の世界を「部族社会」(tribal world)と呼んでいるのですが、その意味するところは「誰もが自分こそが一番偉いと思い込んでいる社会」ということです。ただ、エバンズの偉大さだけは誰もが認めざるを得ないというわけですが、彼が特にジャーナリストとしての凄さを発揮したのは、いわゆる「調査報道」(investigative journalism)の分野だった。調査報道とは「報道機関が、汚職や企業犯罪などを独自に取材・調査し、報道する」というやり方の報道のことです。その反対が(そのような言葉が存在するのかどうか知りませんが)「発表報道」で、政府や企業が資料を配ったりして発表する資料を頼りに報道するやり方です。むささび自身がかつては資料を配る側にいた人間なので、「発表報道」そのものを否定するつもりはありませんが、「調査報道」の方がお金も時間もエネルギーもかかることは間違いない。 |
|
「体制」に嫌われて
エバンズが放った調査報道の多くは彼がSunday Timesの編集長だったとき(1967年~1981年:39~53才)に行われたものだった。例えば英国の情報部員だったキム・フィルビーという人物が実はソ連のスパイであったことをすっぱ抜いたのは、Sunday
Timesの彼が編集長になりたての頃だったし、1972年に北アイルランドのデリーで起こった、北アイルランド市民が英国軍に銃撃・射殺された「血の日曜日」(Bloody
Sunday)事件の真相を報道したのも彼の指揮下にあったSunday Timesだった。どれもが政府を始めとする「体制」が隠したがるようなものばかりだった。彼が言った有名な言葉に
- When all authority is against you, well, then you must be right! あらゆる権威に反対された場合は、間違いなくアンタの方が正しい。
というのがある。 |
 |
サリドマイド事件
何といっても彼の名前がほぼ永久に記憶されるだろうと言われるのが、1960年前後に起こった「サリドマイド事件」という薬害事件だった。サリドマイドという医薬品の副作用により、日本も含め全世界で約1万人の胎児が奇形児として生まれるなどの被害を受けたもので、妊娠初期の母親が服用すると胎児の発達を阻害する副作用があったというもの。この事件を8年間にわたって徹底追及したのが、エバンズをリーダーとするSunday
Timesの取材陣だった。結果として1万人にものぼる奇形児のために補償金を勝ち取ることに成功した。 |
 |
マードックとの遭遇
エバンズがSunday Timesを辞めて、同じグループのThe Timesの編集長になったのは1981年のことで、The Times社を買収したオーストラリアの新聞王・ルパート・マードックの命令によるものだった。そして1982年、結局エバンズがThe
Timesを辞職することになる。マードックとの折り合いも悪かったけれど、タイムズの同僚ジャーナリストから敬遠されたこともある。彼らによると、エバンズの「調査報道」がスキャンダル中心主義であり、タイムズの編集水準を引き下げるものだ、と。そして1984年、エバンズはアメリカ国籍を得てニューヨークへ移住することになる。その20年後の2004年に「ジャーナリズムへの貢献」が認められてSirの称号を与えられた。 |
 |
▼(むささびの想像も含めて言うならば)上の写真は、ハロルド・エバンズという新聞人間を見事に表現しています。1981年に写されたものなのですが、真ん中でThe
Times紙を広げているのが、この新聞社を買収したばかりのルパート・マードック、右側にいるのがそれまでの14年間、The Timesの編集長だったウィリアム・リーズモグ、左側に立っているのがSunday
Timesの編集長からThe Timesの編集長へと異動を命令されたハロルド・エバンズ。エバンズの表情はどう見てもリラックスしているとは思えない。1981年といえばマーガレット・サッチャーの政権がスタートして2年目、いわゆる「新自由主義の英国」が産声をあげたばかりの時代です。1785年創刊のThe
Timesといえば、英国の知的エリートを象徴する存在だったので、「オーストラリアの成り上がり者」であるルパート・マードックに買収された時には時代の変化を象徴する出来事だった(むささびジャーナル219号参照)。
▼ここをクリックするとエバンズの略歴が出ているのですが、彼は16才のときに「記者」となってから少なくとも3つの地方紙で働いてから39才でSunday Timesの編集長(editor)に、53才でThe
Timesの編集長になっている。日本の新聞記者の場合、大学を出て、そのままどこかの新聞社に入り、定年までそこで仕事をするというケースが多いのでは?例えば筑紫哲也さんというジャーナリスト(2008年没)の場合、(ウィキペディア情報ですが)朝日新聞に入ったのが24才のときだった。それ以前に新聞記者としての経験がなかったとすると、ハロルド・エバンズより8年遅く記者になっていることになる。筑紫さんが朝日ジャーナルという雑誌の編集長になったのが49才のとき(1984年)です。エバンズがSunday
Timesの編集長になったのが39才のときだから、ここでも筑紫さんとの間に10年というギャップがある。そもそも英国でいう "editor"
と日本でいう「編集長・編集局長」は違うんですかね。 |
|
back to top |
4)労働党党首は保守主義者?
|

|
考えてみるとずいぶん長い間むささびジャーナルは英国労働党について書いていません。労働党のことが触れられている記事で一番最近のものは、昨年(2019年)12月22日に発行した439号に載せた『英国の選挙を振り返る』という記事だった。12月12日に行われた選挙に関するもので、労働党について語るというよりも、同党の地盤であったはずの北イングランドにおいてボリス・ジョンソンの保守党が勝利を収めたことを語るものだった。 |

スターマーとコービン(右) |
保守党に完敗
実は(お恥ずかしいのですが)現在の労働党の党首のことさえ書いてこなかった。2019年の選挙で、ボリス・ジョンソンの保守党が47議席増やして単独過半数(365)を確保したのに対して、ジェレミー・コービンの労働党は議席数をほぼ60も減らしてしまい、責任をとってコービンが辞任、2020年4月にキア・スターマー(Keir
Starmer)という人が党首に就任していたのであります。スターマーは人権問題を担当する弁護士だったのですが、2015年に労働党の国会議員になった。労働党の党首にしては珍しく"Sir"の肩書で呼ばれている。9月26日付のThe
EconomistのサイトがSir Keirを紹介する記事を載せているのですが、それによると彼の姿勢はどちらかというと保守主義に近いと思われる。
- この労働党党首が強調するのは「家族」、「安全」、「愛国心」のような価値観だ。それによってかつての(労働党の)の支持者を呼び戻そうとしているのだろう。 The Labour leader stresses family, security and love of country in an appeal to former voters
スターマー党首が呼び戻そうとしている「かつての支持者」とは、2019年の選挙でボリスの保守党を支持してしまった北イングランドなどの労働者階級のことなのですが、別の言い方をするとスターマーの前任者であるジェレミー・コービンに嫌気がさしていた労働党支持者たちのことです。 |

ジョンソン首相とスターマー |
「社会主義者」を自称
労働党の初代党首(1906~1908)はキア・ハーディという人であり、キア・スターマーも自分の名前がハーディ党首にちなんでつけられたものであり、自分自身も「社会主義者」(socialist)と言っているらしいのですが、そのことを余り強調したくもないようなのです。労働党大会(9月22日)で党首として彼が語ったのは、「自分がSirと呼ばれるようになったことを両親が大いに誇りにしており、自分がそうなったのは英国の優れた教育制度のお陰だ」などということだった。前任者のコービンと異なり、キア・スターマーは王室はもちろん英国という国家を誇りに思うというような趣旨のことを強調している。どう考えても(コービンに比べれば)「保守党的」なのです。
The Economistによると、2019年の選挙で労働党が惨敗したのは、主に北イングランド、中部イングランド、ウェールズのようなエリアで暮らす「社会意識が保守的な労働者階級」(socially conservative working classes)が雪崩を打ってBREXITを掲げるボリスの保守党を支持したからです。キア・スターマーが奪回しなければならないのは彼らの支持です。
党大会におけるスターマー党首の演説は、教育・医療の向上、人種差別の撤廃、労働者の権利拡大etcのような従来の労働党路線を受け継ぐものではあったのですが、労働党が政権をとったアカツキには、英国を「家族が第一(family first)」という国にすると強調し、防衛や領土問題にも力を入れることなども強調していた。党大会でスターマーは集まった党員に対して“We love this country as you do.”と呼びかけていたのですが、The Economistに言わせると、ジェレミー・コービンと決定的に違うのは、スターマーの労働党は「愛国的」(patriotic)ということだ、と。
|

クレア・エインズリー |
公正・勤勉・家族第一
スターマー党首を政策面で支えるのがクレア・エインズリー(Claire Ainsley)という女性(年齢不詳)なのですが、貧困問題に取り組むNPOとして知られるJoseph
Rowntree Foundationの幹部だった。彼女が書いた本に“The New Working Class”(新しい労働階級)というのがあるのですが、副題が"How
to Win Hearts, Minds and Votes"となっている。The Economistによると、彼女が強調しているのは労働党の政策は「公正:fairness」、「勤勉:hard
work」、「家族:family」のような道徳(moral)を基盤にするべきだということです。「謳い文句」(soundbites)ではなくて「価値観」(values)ということ。
スターマー党首の演説もそれらを強調したもので聴衆の受けも良かった(とThe Economistは言っている)。前任者のコービンの路線はというと「反軍国主義:denouncing British militarism」、「アイルランド風共和主義:sympathising with Irish Republicanism」などを強調しており、英国の国益にはおよそ無関心という感じであった、と。 |

バイデンとスターマー
|
英国版バイデン?
コロナ禍との戦いに四苦八苦という感じのボリス・ジョンソンについてスターマー党首は「保守党という名前の割には、彼らはあまり”保守”しているとも思えない」(For
a party called the Conservative Party, they don’t seem to conserve very
much)と言っているのですが、それは主としてボリスが英国の官僚たちを十分に使い切っていないということを意味している。素人のような首相のお陰で失われてしまった、英国に対する国際的な信用を取り戻し、英国を「称賛と尊敬の的になるような国」(once
again admired and respected)にしようではないか…とスターマーは呼び掛けているのですが、そのようなスターマーをアメリカで大統領選を戦うジョー・バイデンに譬える向きもある。 |
| ▼スターマー党首は、労働党内でBREXIT問題を担当しており、国会議員による「国民投票を再度実施する運動」のリーダー的な存在だったのですが、いまいち強硬な反BREXITという感じではない。12月の選挙でBREXITを推した保守党が大勝利したという現実は受け入れなければ・・・という姿勢です。スターマー政権を思想的に支えるクレア・エインズリーが強調する「フェア・勤勉・家族第一」という発想で気になるのは、受け狙いの姿勢が強すぎて、結局保守有利な現在の英国の政治に埋没せざるを得ないのではないかということです。1997年に誕生したブレアの労働党が辿ることになってしまった「第三の道」という名前の保守党化の道を進んでしまうことになるのではないか?ということです。 |
|
back to top |
5) どうでも英和辞書
|
| A-Zの総合索引はこちら |

|
| out of the woods:危機を脱した状態 |
コロナに感染したトランプが退院したことを伝える10月6日付の日本経済新聞の記事は、トランプの主治医が「完全に困難を乗り越えてはいないかもしれないと説明した」と言っている。この部分、ショーン・コンリー(Sean Conley)という主治医が使った言葉は
- he may not entirely be out of the woods yet...
というものだった。「困難を乗り越え・・・」は "out of the woods" の和訳だったわけですが、英語では危機を脱出することを「森を出る」と表現するのですね。"may not entirely be" などと柔らかな表現を使っているけれど、主治医にしてみれば「退院などとんでもない」という状態だったのかもしれない。それをトランプときたら ""Now I'm better, and maybe I'm immune"(気分はよくなったよ。自分には免疫性が備わったということかも)などとほざいている。
トランプの姪であるメリー・トランプがラジオ(NPR)のインタビューで明らかにしたところによると、トランプ家では病気に罹るということ自体が「許しがたいほどの弱さの発露」(a display of unforgivable weakness)なのだそうですね。つまり病気になること自体が道徳的に許されない行為であるということですね。そんな人物が国のリーダーであること自体、アメリカが "out of the woods" になることは望めないのでは?
|
back to top |
6)むささびの鳴き声
|
▼10月7日のヤフーニュースに「菅首相のツイート、自民から苦言」という見出しの記事が出ていました。記事自体は共同通信発のもので、コロナに感染したトランプ夫妻に対して、菅首相が送ったお見舞いのツイッターメッセージの英文がうまくないというわけで、自民党の外交部会が文句を言っているという趣旨の記事だった。菅さんが送った英文メッセージは次のようなものだった。
- I was very worried about you when I read your tweet saying that you and Madam First Lady
tested positive for COVID-19. 貴大統領とメラニア夫人がコロナに感染したとのツイートを見て心配しました・・・
▼自民党の外交部会が文句をつけたのはアンダーラインの部分で、"was very worried" という過去形が使われていることで、出席議員の中から「(あのときは心配したけれど)今は心配していない、という意味に受け取られる」という声が上がったのだそうです。共同通信によると、「(この英語は)日本語を自動翻訳したような文章だ、との酷評も上がった」とのことであります。
▼この"was very worried"は、そんなにダメな文章ですか?「貴殿のツイッターを読んだときに(when I read
your tweet)心配の気持を持ちました」と言っているだけのこと。もちろん同じことを伝えるためにこれとは異なる表現はいくらでもある。”Your
tweet made me worried...", "I recently have seen a worrying message
in your tweet" etc。でも"I was very worried"(心配した)と言うと"I
am not worried any longer"(もう心配はしていない)と同じように解釈されると文句をつけるのは、全く無意味な「難癖」というものなのではありませんか?そのようなケースが全くないとは言わないけれど、菅さんのこの文章を読んでトランプや普通のアメリカ人がそのように解釈するとはとても思えない。
▼でも・・・むささびが文句を言いたいのは、こんなことにケチをつけている自民党外交部会のヒマ人たちに対してではないし、この件について「サポート態勢を組んで対応する」などと大げさにコメントしている「外務省の担当者」に対してでもない。こんなことを記事として発信する共同通信という報道機関の感覚です。他に伝えるべきことがあるんでないの?ってこと。お分かり?アンダスタン!? でも、むささびが共同通信よりも情けないと思っているのが、ツイッターなどという道楽を使ってあのトランプ夫婦のような人たちとお友だちになろうとするスガという人のアタマなのよね。しかも別の人間に「英文」まで作らせて。
▼それにしてもこの「寒さ」は何なのでしょうか! まるで冬です。お元気で! |
|
back to top |
←前の号 次の号→ |
 |