| 最近のむささび夫婦は、悲しいくらい旅行というものをしなくなりました。だから上の写真が日本国内の景色だなんて全く知りませんでした。「北海道幌泉郡えりも町字目黒地内」というところにある豊似湖(とよにこ)です。「湖の形状が馬の蹄に似ていることから馬蹄湖とも、ハート形をしていることからハートレイクとも呼ばれている」とのことです。馬の蹄?とても見えないけどなぁ! |
目次
1)スライドショー:「あの人」のいない世界へ
2)89才、ジャーナリストの闘争宣言
3)さよなら、フィスク:「五分五分報道」の限界
4)原爆投下:フィスクの視点
5)どうでも英和辞書
6)むささびの鳴き声
|
1)スライドショー:「あの人」のいない世界へ
|

|
このところテレビ、ラジオ、ネット(そしてたぶん新聞も)・・・どれを見ても聴いてもアメリカの選挙の話ばかりですね。むささび家のワンちゃんたちでさえいい加減ウンザリしているようです。この世に「あの人」(ドナルド・トランプ)さえいなければ、さぞや住みやすかっただろうに、という慚愧にも似た気分で作ったのがこのスライドショーであります。そう言えば、この写真のウミガメの顔、あの人に似ている。 |
|
back to top |
2)89才、ジャーナリストの闘争宣言
|
 |
アメリカの大統領選挙はどのように決着するのか分かりませんが、昔、米CBSニュースのキャスターだったダン・ラザー (Dan Rather)がFacebookに掲載した短い文章に惹かれました。ラザーは1931年生まれだから、むささびよりちょうど10才年上なのですね。Facebookに投稿したのが11月4日の夜中の11時半、書き出しは次のようになっている。
- 我々(アメリカ人)が目を覚ますと、国は深々と分断され、痛みに苦しみながらもアメリカ精神を模索していた。いくつかの州で薄氷を踏むようなギリギリの票差を記録したけれど、そのことはアメリカ史においては異常なことではない。しかし今の我々の間に横たわる裂け目は極めて危険かつ埋め難いものであり、かつて感じたことがなかったような不安を持たざるを得ない。 We awaken to a country in pain, deeply divided, and in search of its soul. That we have an election with razor-thin margins in several states is not a complete anomaly in our history. That the chasms between us feel so fraught and so alienating does feel uniquely precarious.
|
 |
ラザーは、過去4年間、トランプのやってきたことを見るとき、なぜかくも多くのアメリカ人が彼を支持するのかをいぶかっているのですが、その一方で「アメリカ史の中でこれほど多くのアメリカ人が現職の大統領を拒否したこともないだろう」と言っている。そして多くのアメリカ人が大いなる疲労感の中で「アメリカとは何だったのか?これからどこへ行こうとしているのか?」と自分自身に問いかけている、と。ラザーの短い寄稿文は次の文章で終わっている。
- 余りにも多くのモノが壊れてしまっている。傷は極めて深い。が、毎朝目を覚ますと、他人を助け、世の中を少しでも良くしようとする仕事に挑戦するアメリカ人もたくさん存在する。私自身はそのような人びとの精神に敬意を払う。そして生きている限りにおいて、自分が暮らしたいと想うようなアメリカの建設を目指して闘いを続けるつもりなのだ。There
is a lot that is broken, deeply broken. But there are millions upon millions
of our fellow citizens who wake up each morning, undaunted, ready to do
the hard work to help others and make this world a better place. Today,
I honor that spirit. As long as I have breath, I will continue to fight
for the America I want to live in.
|
 |
ラザーの寄稿には多くのコメントが寄せられている。例えば:
- I appreciate but can’t share your optimism. 有難いとは思うが、貴方の楽観主義にはついていけない。
- Very sad as Democracy dies in darkness. 民主主義が暗黒の中で死んでいくのを見るのは悲しい。
- It saddens me that so many Americans chose hate, corruption and bigotry. 憎しみと汚職と偏見を選択するアメリカ人が余りにも多いのが悲しい。
という具合です。読んでいても痛々しい。 |
| ▼むささびがダン・ラザーの記事に惹かれたのは、「生きている限りにおいて、自分が暮らしたいと思うようなアメリカの建設を目指して闘いを続ける」と言っている部分です。この選挙に関連してメディアに掲載されているエッセイの類は、アメリカの分断・分裂を書き立てるだけで、団結を呼びかけるようなニュアンスのものが余りにも少ない。日本のメディアだけではなくて、アメリカのメディアも英国やドイツのそれも、鬼の首でも取ったかのように分裂・分断の悲観論を書きまくっている。そのようなジャーナリストや学者さんたちには「あなた方もそこで生きているんですよ」と言いたくなる。ダン・ラザーの記事は困難であることは認めながらも、アメリカを良くするために闘うのだという色彩が強い。筆者の闘争宣言です。おそらく今のアメリカは(たぶん日本も)悲観論に浸っている場合ではない・・・とラザーは感じているのではないか。 |
|
一夜明けて・・・
むささびが以上の記事を書いたのは、日本時間で11月7日(土)の夕方だった。一夜明けて11月8日(日)の午前7時ごろにラザーのFacebookを見たら、彼自身のコメントとして
と書いてある。ちょっと可笑しいのは、読者からのコメントです。
- (2016年に)トランプが選ばれたときに、自分は泣いた。そして私は今、再び泣いている。何故ならバイデンが選ばれたからだ。我々は再び一つになったのだ。有難う、ペンシルベニア、有難う、アメリカ。 I cried when Trump was elected. I’m crying again because Biden has been elected. We will become whole once again. Thank you Pennsylvania. Thank you America.
- 選挙期間中、私たちの手を取りながら歩いてくれたダン、有難う。貴方がいなかったら、私はとても正気ではいられなかった。アメリカに神の祝福を! Thank
you Dan, for holding our hand and walking us through this election! Couldn't
have maintained my sanity without you. God bless The United States of America!
一日前とずいぶん違うなぁ! |
back to top |
3)さよなら、フィスク:「五分五分報道」の限界
|
 |
10月30日、The Independent紙のロバート・フィスク(Robert Fisk)というジャーナリストが亡くなりました。中東問題の専門記者で、9・11テロ事件のリーダーであったオサマ・ビン・ラディンとは数回、単独インタビューをしたことで知られている。ジャーナリストの死去といえば、9月下旬にハロルド・エバンズが亡くなっているけれど、ほぼ一か月後にフィスクが亡くなったというわけです。フィスクは1946年生まれだから今年で74才、むささびより5才も若かった。逝くのが余りにも早すぎた。フィスクの死去については、エバンズの時と同様に最終的に所属したThe Independent紙はもちろんのこと、Guardian, Times, BBCなど、英国の主だったメディアが全て伝えて彼の死を惜しんでいます。 |
 |
むささびも過去において何度か彼の書いた記事を紹介しましたが、彼の死を惜しんで、今号ではその中から2本の記事を紹介します。まずはむささびジャーナル263号に掲載された『「五分五分ジャーナリズム」では中東は伝えられない』という記事です。ロバート・フィスクの記事は戦争の現場からのものがほとんどで、さまざまな紛争を、それに巻き込まれた人々の視点から伝えており、いわゆる「従軍記者」とか「戦争ジャーナリスト」による「大本営発表」式の戦場最前線報告ではない。彼なりの「ものの見方」(views)が鮮明に出てくる。
ここに紹介するのは、彼が2010年に米カリフォルニア大学バークレー校で行った講演会の中身です。講演のタイトルは"The Terror
of Power and the Power of Terror"(権力のテロとテロが生む権力)というもので、アフガニスタンやイラクにおける「対テロ戦争」に関連してフィスクなりのジャーナリストとしての姿勢のようなものを語っています。非常に長い講演で、とても全部を紹介するわけにはいかない。私が紹介したいと思うのは、いわゆる"50/50
journalism"(フィフティ・フィフティ・ジャーナリズム)なるものについて彼が語った部分です。日本語に訳すと「五分五分ジャーナリズム」ということになるのでしょうが、物事を伝えるのに一面的な伝え方をするのではなく、異なった見解や背景を平等に紹介することで報道の中立性を保とうとする姿勢のことなのですが、フィスク自身は、この姿勢について疑問を抱いているようです。 |
 |
駆け出し記者時代にフィスクが教わったのは、(例えば)サッカーの試合について報道する場合、地元のチームのことだけではなく、相手方のことをも伝える・・・それがフェアな50/50 journalismというものだ、ということだった。あるいは、政府が新しい高速道路の建設計画を発表したというニュースがあるとする。それが如何に必要かつ素晴らしい道路であるかを説明する政府高官のコメントを伝えるのと同じようなスペースを使って、道路の建設に反対する人たちの意見をも報道することが大切である、と。道路賛成に50%、反対に50%のスペースや放送時間を与えることによって偏った報道になることを避けることができる。即ち50/50 journalismというわけです。
ロバート・フィスクは、カリフォルニア大学における講演で、ジャーナリストの中に50/50 journalismという「中立性についての誤った考え方」(false idea of neutrality)を中東に持ち込んで報道する人がいる、と言います。彼に言わせると中東で起こっているのはサッカーの試合でもなければ高速道路の建設でもない。まさに「血まみれの悲劇」(a bloody tragedy)なのだとして次のように語っています。
- もちろんジャーナリストは中立であるべきで偏向があってはならないし、客観的でもあるべきである。が、それは最も苦しんでいる人々の側に立ったうえでのことである。それが誰であろうとも、だ。 Yes, we should be neutral and unbiased, we should be objective, on the side of those who suffer, and whoever they may be…
|
 |
いまから40年前の1982年9月、ベイルート郊外にあったパレスチナ難民キャンプで2000人以上ものパレスチナ住民が虐殺されるという事件があったのですが、これを取材したフィスクが報道したのは、殺されたパレスチナ人と生存者のことのみであり、この虐殺行為を見ていながら何もしなかったイスラエル側の事情などについての報道はしなかったのだそうです。
フィスクの50/50 journalism批判に関連するのですが、ブレア首相が2007年に退陣する際に行った演説の中で、英国の新聞の中でも特にThe Independent紙を名指しで取り上げ、同紙が事実を伝える「新聞」(newspaper)ではなく、意見を伝える「意見ペーパー」(viewspaper)だと痛烈に批判したことがある。これに対して同紙の編集長が「首相がThe Independentを批判するのは、それがviewspaperであったからではなく、首相のイラク政策に反対したからなのではないか」と反論しました。ブレアによるviewspaper批判は、どう考えてもThe Independent紙のフィスク記者のイラク戦争報道に対する批判であったわけです。 |
 |
フィスクの「五分五分ジャーナリズム」批判の根幹は、物事を伝えるという仕事をしている自分の立っている位置を明確に意識していることにあると(むささびは)思います。そしてそれが「苦しんでいる人々の側」であると明言してしまっているということです。政府や反政府勢力の言うことを単に受身的に「伝える」のではないということです。
フィスクはまたシリア情勢に関する記事の中で
- The cost of war must be measured by human tragedy, not artefacts. 戦争のコストは文化遺産ではなく人間に起こった悲劇によって測られるべきだ。
と書いたことがある。内戦状態のシリアについて「文化遺産が破壊されている」と危惧する声が上がっているらしいのですが、フィスク記者は「人間の命に比べれば芸術品の破壊程度など何だというのか」と怒っている。 |
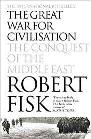 |
▼フィスクの代表作の一つにThe Great War for Civilizationという本があります。アルジェリア内戦、イラン革命から9・11テロに続くアフガニスタン、イラク戦争におよぶ半世紀の中東の歴史を語っているのですが、常に精神的のみならず肉体的にも内戦や紛争の銃弾が飛んでくるところに身を置いているのが伝わってきて圧倒されてしまいます。
▼その本の中でフィスクは、9・11テロの直後、アメリカのメディアが「誰が、何を、いつ、どこで、どのようにして起こしたか」(who, when,
what, where, how)については洪水のように報道したけれど、「なぜ」(why)については殆ど報道することがなかったと批判しています。テロリストがあのような狂気に走った理由・動機です。フィスクによると、あの当時のアメリカでは、whyを問題にすることはテロリストに味方するのと同じという風潮があったのだそうです。彼自身は9・11テロのwhyはパレスチナ問題にあると言っています。 |
back to top |
4)原爆投下:フィスクの視点
|
 |
ロバート・フィスクが書いた記事で、むささびが紹介したものをもう一つ紹介します。今からちょうど10年前(2010年)の8月7日付のThe Independent紙のサイトに掲載された
という見出しの記事を紹介します。この記事は、むささびジャーナル196号で掲載したものを再度掲載するものです。フィスクにしては珍しく、日本で取材したものであることが一つの理由ですが、テーマが、広島・長崎への原爆投下という極めて今日的なものであるということが一番大切な理由です。 |
 |
この記事は単なる事実報告ではなく、記者自身が広島の式典に取材した際に感じたことを文字にしているものです。タイトルでもお分かりのように、戦争に絡めて「国による謝罪」ということがテーマになっています。とてつもなく長い記事なので全部を紹介するのはムリですが、私が考えたエッセンスと思われる部分のみをピックアップして紹介したいと思います。まずは書き出しから・・・。
- 我々はようやく広島に対して謝罪した・・・かな?我々は自分たちの原爆というものが引き起こした苦しみを認識した。まあね。オバマ大統領は広島の殺戮現場において「反核資格」のようなものをひけらかそうとしていた。が、これは「ごめんなさい」という言葉を吐くことと混同してはならないものであったのだ。At last we’ve apologised for Hiroshima - well, sort of. We’ve recognised the suffering our atom bombs caused - well, kind of. President Obama was showing off his anti-nuclear credentials in the killing grounds of Hiroshima, but this was not to be confused with saying sorry.
つまり今年(2010年)の式典にはアメリカ大使が参加したけれど、だからと言って原爆投下についてアメリカが謝罪をしたわけではない、とフィスクは言います。またフィスクは英国代表が参加することについて駐日英国大使館が"This
is the right move at the right time"(適切な時期に行われる適切な行動である)と語ったことについてはBlairite
insincerity(ブレア風の不真面目)と決めつけている。ここは分かりにくい部分ですが、他のサイトを見ると、駐日英国大使館のコメントは次のようになっている。
- The attention is on the ceremony itself and on the victims, so we don't
want to overshadow the event. But given the way the international debate
is going, we think this is the right move at the right time. 注目されるべきなのは式典と犠牲者の方々なのであり、我々はこの行事に影を投げかけるようなことはしたくない。が、昨今の国際的な議論の方向性から考えて、英国代表が参加することは適切な時期に行われる適切な行動であると、我々は考えている。
|
 |
このコメントがどのような状況でなされたのか、私(むささび)には分からないけれど、ひょっとすると、メディアから「政府代表が参加すると、日本に謝罪をしたと解釈されるのではないか?」と聞かれたら、そのように答えろというロンドン(外務省)からの指示があったのかもしれない。それにしても、フィスクはなぜこのコメントが「ブレア風の不真面目」と考えるのか?それは「国際的な流れがそうなっているのだから、とりあえず歩調を合わせておいた方が自分たちにとって都合がいい」と言っているのと同じだ、とフィスクは感じているわけです。ブレアという人には常にそのようなご都合主義がつきまとっていたとフィスクは考えている。大使館も含めた英国人の正直な心を言うと
- After all, we are really not apologising for the 220,000 dead of Hiroshima and Nagasaki. Hell, didn't we win the Second World War? 我々は広島と長崎で死んだ22万の人々に謝罪する気などない。冗談ではない。我々は第二次大戦で勝ったんだぜ。
ということになるとフィスクは言っている。 |
 |
フィスク自身は、あの当時の日本はすでに降伏の可能性を口にしていたのであり、アメリカによる原爆投下は戦争犯罪(war crime)だと考えているのですが、アメリカ政府の関係者が英国の歴史家、AJP Taylorに語った言葉として次のようなものを挙げています。
- 簡単に言うと、原爆は使われる必要があったのだ。これを開発するためにとてつもない額のお金がつぎ込まれたのだ。失敗でもしようものなら言い訳のしようがなかったはずだ。国民が何を言うか分かったものではなかったのだ。だから原爆が完成して投下されたときには皆ほっとしたものだ。"The bomb simply had to be used - so much money had been expended on it. Had it failed, how would we have explained the huge expenditure? Think of the public outcry there would have been ... The relief to everyone concerned when the bomb was finished and dropped was enormous."
|

マウントバッテン卿 |
原爆投下を正当化する理屈として、あれを使わずに連合軍が日本の本土侵攻を行った場合、その方がはるかに犠牲者が多かっただろうというのがあるけれど、フィスクは「それはいまや全くのウソ(completely
untrue)であることが明らかだ」としながら、軍人であったマウントバッテン卿の言葉を紹介しています。
- もし原爆が日本人を殺し、我々側の犠牲を少なくするものであるのなら、私は当然、不必要に我々側の人間を殺すことを望むことはないだろう。私の責任はなるべく多くの日本人を殺すことにあるのだ。戦争は狂気ではあるが、日本人の命を救って我々側により多くの犠牲者を出すとしたら、これ以上に狂ったことはないだろう。 If the bomb kills Japanese and saves casualties on our side I am naturally not going to favour the killing of our people unnecessarily ... I am responsible for trying to kill as many Japanese as I can. War is crazy ... But it would be even more crazy if we were to have more casualties on our side to save the Japanese.
軍人としては当たり前のようなコメントですが、フィスクは、
- マウントバッテン卿の言葉は、残酷かつサディスティックで知られる日本の兵隊たちが殺したのが敵側の兵士たちであるのに対して、彼の部下たちが殺したのは殆どが日本の市民であったということに触れることを慎重に避けている。 This, of course, carefully avoids the fact that Japanese soldiers - brutal and sadistic though they were - were largely murdering soldiers, while Mountbatten's men were slaughtering mostly Japanese civilians.
と言っています。これ以上紹介し始めるとあまりにも長くなるのでこの辺で止めておきますが、フィスクによると、今年(2010年)の広島の式典にアメリカの政府代表が出席したのは
- ますます自惚れの度合を強める大統領によるイメージアップ作戦の一環であって、原爆の犠牲者が被っている肉体的な苦痛への真摯な憂慮の気持ちから出たものではないし、人道主義者としての悲しみの表現でもない。正しい方向への第一歩だと言う人もいるだろう。そのように信じたいものではあるが、(アメリカ代表の参加は)余りにも遅すぎたと言えるのだ。 And yesterday's theatre was played to boost the image of an increasingly self-regarding president, not out of any real concern for suffering - by which I mean physical pain - or humanitarian sorrow. A step in the right direction, you may say. Sure. But if you want to to believe in it, alas, it all came far too late.
ということなのだそうであります。フィスクの言う「ますます自惚れの度合を強める大統領」(increasingly self-regarding president)というのは、アメリカのバラク・オバマ大統領のことです。 |
| ▼9月に亡くなったハロルド・エバンズもそうだったけれど、ロバート・フィスクも記者としての仕事を北イングランドの地方紙、Newcastle Chronicleで始め、Sunday
ExpressとThe Timesを経て1989年からThe Independentの記者をやっている。フィスクもエバンズもいろいろな新聞社で仕事をしているのですね。The
Timesを辞めたのはオーナーのルパート・マードックとの対立というのもエバンズと同じです。ここをクリックすると、フィスクがThe Independentに寄稿した記事が出ています。 |
|
back to top |
5) どうでも英和辞書
|
| A-Zの総合索引はこちら |

|
TINA:これっきゃない
|
あのマーガレット・サッチャーが首相になりたての頃、産業の民営化、労働組合の縮小、規制緩和などの経済政策を実施したのですが、それについて野党の労働党はもちろんのこと、保守党内からも「やりすぎだ」という声があがったのですが、それに対してサッチャーが口にしたのが、労働党のおかげで弱体化した英国経済を立て直すには「これしかないのよ」という言葉だった。それが
だったのですが、彼女に批判的なメディアはもちろん、保守党の議員の中にも頑固すぎる彼女のやり方を称してTINAと表現する者が結構いたのだそうです。
最近になって、ジョンソン首相がイングランドにおけるコロナ対策として4週間のロックダウンを実施すると発表したのですが、保守系のThe Spectator誌によると、首相の気持としてはあのサッチャーのTINAと同じだろうと言っている。つまりコロナの拡大防止のためには「苦しいのは分かっているけれど、これっきゃない」ということです。ロックダウンは12月2日まで続くのだそうですが、冬が始まる頃のイングランドの陰鬱な気候を想うと、これは確かにきついかもしれない。
ところで "alternative" という言葉ををケンブリッジの辞書で引くと "something different from something else" というややこしい説明が出ており、具体的な使い方として "alternative to coffee" というのが出ていました。「コーヒー以外の飲み物」という意味ですよね。紅茶とか日本茶とかココア等々です。これが "to" を削除して "alternative coffee" となると「コーヒーめいた飲み物」というわけで、日本語では「代用品」ということになるのでしょうね。
つまり「現在の苦境を脱するにはロックダウンっきゃない」というのは "There is no alternative to lockdown to get out the current mess." ということに・・・。
|
back to top |
6)むささびの鳴き声
|
▼ラジオを聴いていたら、朝日新聞の記者という人がアメリカの大統領選挙について話をしていました。若い記者(40才代?)のようだったけれど、2016年の選挙を取材した経験があるとのことで、トランプについて「少なくとも自分で言ったことを実行している点は称賛に値する」という趣旨の発言をしていました。政治家を評価する基準は「実行力」ではなくて、実行しようとしている事柄の中身なのではないのか?その朝日新聞の記者は「自分は必ずしもトランプを全面的に支持するわけではないけれど」と言っていたのですが、これもまた意味のない言葉だと思いません?「全面的に支持するわけではない」のであれば、少なくとも一部分は支持するということですよね。ではそれは何なのか?そこを語らないコメントなんて・・・。
▼(話題は変わって)最近、ミセス・むささびが興味深い文章の存在を教えてくれました。相対性理論で知られる理論物理学者である、あのアインシュタイン(Albert Einstein 1879 - 1955)の言葉で、英語で次のような書き出しになっている。
- A human being is a part of the whole called by us universe...人間は、我々が「宇宙」と呼んでいる全体の一部として存在している。
▼これは文章の一部で、ここをクリックすると、文章のすべてが出ています。ごく短い「名言」(quote)のようなもので、この文章は今から70年前、彼が71才のとき(1950年)にある人に宛てて書いた手紙の中にあるのだそうです。「人間は宇宙の一部だ」と言われても、茫漠としていて「そうですか」としか言いようがないように思える一方で、何故か(むささびには)今の時代に読まれ・語られるべき言葉のように思えてならないわけです。
▼アインシュタインによると、人間は自分の思想、自分の感覚など(「自分自身」と呼ぶもの)を他のものから切り離して考える傾向があるけれど、実は人間は独りで存在しているのではない。身近な順でいうと、人間は「自分→家族→隣近所→地域→国→世界→宇宙・・・」という大きな枠組みの一部として存在している。なのに人間は自分を「他」から切り離して考えようとする傾向がある。アインシュタインによると、それは自意識がもたらす一種の錯覚のようなものであり、人間はその錯覚の中に閉じ込められている存在である、と。
▼それによって人間は「自分自身の欲望」とか「自分に最も近い数人の人間に対する愛情」という「牢獄」のような世界に閉じ込められた囚人のようになってしまう。アインシュタインは「人間は自分自身をそのような牢獄から解放しなければならない」(Our task must be to free ourselves from this prison)と言っている。どうやって「解放」するのか?答えは次のとおりである、と・・・。
- 自分自身に備わっている「思いやりの輪」を広げることによって、あらゆる生きものや自然界の美しさを抱きとめることである。Widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.
▼何だか分からないか、これでは。むささびの想像によると、トランプやシンゾーが叫んでいるのは、ここでいう人間が人間を閉じ込めようとする「牢獄の建設」なのではないかっつうこと。自分と自分の家族の利益だけ考えよう、気候変動?知ったことか、それよりへんなヤツらを入れないための壁づくりの方が肝心だ、Make America Great Againというわけ。それに文句をつける奴らはみんな気に入らないインテリ野郎だ!
▼あっという間に冬が来てしまったようですが、最近の埼玉県の山奥の空のきれいなこと、一度お見せしたいよね。Good-bye! |
|
back to top |
←前の号 次の号→ |
 |

