| 2021年最初の「むささび」です。非常事態宣言が出るの出ないのと、世の中、正月どころではないかもしれないけれど、何が起ころうとも時は過ぎていくのですよね。できれば今年も、むささびの道楽にお付き合い願えませんか? |
目次
1)スライドショー:正月早々、クリスマス・ソング!?
2)Global Britainとヨーロッパ
3)「国際社会」の定義が気になる
4)「逃げ遅れ」で得たもの
5)どうでも英和辞書
6)むささびの鳴き声
|
1)スライドショー:正月早々、クリスマス・ソング!?
|
 |
今回のスライドショーは、使われているスチル写真もさることながら、バックで使われている音楽にご注目いただきたいのです。ご存じの方も多いと思うけれど、Gilbert O'Sullivan(ギルバート・オサリバン)が歌う "Christmas Song" という歌です。お正月だというのにクリスマス・ソングを聴かせようというのだから、すごいじゃありませんか。
まずは歌詞から: |
I'm not dreaming of a white Christmas
ぼくは 「ホワイト・クリスマス」を夢見ない
I'm not dreaming of a white Christmas
ぼくは 「ホワイト・クリスマス」を夢見たりしない
All I'm dreaming of the whole day long
ぼくが一日を通して夢見るのは
Is a peaceful world
平和な世界のことだけ
Merry Christmas, Happy New Year
メリー・クリスマス、そして新年おめでとう…
To those of you who live in fear
と、恐怖の中で暮らしているあなた方に言いたい
And let us hope that very soon
そして、もうすぐ
The peace you seek will then resume
皆の求める平和が再びやってくることを祈ろう
|
|
2分40秒ほどの歌なのですが、基本的にこの8行の繰り返しで、"I'm not dreaming of a white Christmas"
というフレーズがこの歌のメッセージです。「私はホワイト・クリスマスを夢見ない」という意味ですよね。これを2回繰り返したあとに "All
I'm dreaming of the whole day long is a peaceful world"(私が一日中夢見るのは平和な世界の到来だ)というフレーズが続く。
「ホワイト・クリスマス」はビング・クロスビーのクリスマスの定番ソングのタイトルであり、この歌はあの歌に対抗する意味で作られたのかもしれない。あの定番ソングに代表される「平和で静かなクリスマス」の恩恵に浴さない人間への連帯のメッセージともとれる。
ギルバート・オサリバンは1946年生まれだから今年で75才になる。生まれはアイルランドですが、育ったのはイングランドです。彼がアイルランド系英国人であることが、歌詞で歌われる「平和の希求」精神に関係する(とむささびは想像している)。
この曲が発表されたのは今から45年前の1976年です。アイルランドへの帰属を求めるIRA(アイルランド共和国軍)のテロリズムが吹き荒れていた時代です。そのころに英国で暮らすアイルランド人であるオサリバンが世に出したのがこの曲だった。ほぼ半世紀後の今、EU離脱の過程において、国境をめぐる「アイルランド問題」は、いまだに存在していることがはっきりしたといえる。 |
| ▼このスライドショーで使われている写真は、コロナ禍で四苦八苦と報道される英国で、ロックダウンを生き抜く英国人の表情を集めたものです。死の恐怖に直面しているという意味では、アイルランド紛争で苦しんでいたころの英国と共通しています。 |
|
back to top |
2)Global Britainとヨーロッパ
|

|
英国とEUの自由貿易協定(FTA)が合意されて、いわゆる「合意なき離脱」(Brexit with no deal)の可能性がなくなったことは日本でも大いに報道されましたよね。むささびの見落としかもしれないけれど、この件についての多くのメディア報道(日本も英国も)の重点は「これで一応混乱は避けられそうだけれど、合意にはいろいろと問題や反対論がある」ことを語ることに置かれていたように思います。ここでは12月28日付けのThe Economistの社説を紹介します。この雑誌は英国のEU離脱には反対という立場をとっているのですが、社説のイントロの部分で次のように書いている。
- 海を隔ててこちらに背を向ける大陸、自分たちにとっては疎遠な場所となったヨーロッパ大陸を見つめる英国が直面するのは、答えるには勇気が必要な質問である。即ち英国はこれから世界でどのような役割を担うべきなのだろう?ということだ。 Looking
across the seas with an estranged continent at its back, a lonesome Britain
thus faces a bracing question: what role should it now play in the world?
大国のような顔をするな
昨年(2020年)9月に行われた世論調査で「英国は世界の大国であるかのようなふりをするのは止めるべきだ」(Britain should stop
pretending it is an important power in the world.)という考え方への賛否を問うたところ38%が「賛成」と答えて「反対」の28%を上回った。その数字を信用するとして、英国が目指すべき一つの方向は「大きなデンマーク」(a
big Denmark)のような国になるということかもしれない、とThe Economistは言う。即ちいわゆる「超大国」でも「大国」でもないけれど、国内的にはしっかりまとまっている国ということです。
|
 |
ただその一方でThe Economistは「英国人は、自分たちが世界に大きな影響力を有した国の国民であることを軽々しく考えるべきではない」とも言っている。国際貿易・気候変動・民主主義擁護などの問題について英国が有している影響力のおかげで英国人が利益を得ている部分も大いにあるということです。
保守党とGlobal Britain
英国の将来像について保守党政権が掲げるスローガンは“Global Britain”です。ヨーロッパという枠組みを超えて「世界の中の英国」になろうということです。この発想は2016年の国民投票の時点で離脱賛成派によって打ち上げられていたものです。なのに4年後の今も最終的な政策文献さえまとまっていないという状態です。要するに“Global
Britain”は立派には違いないけれど、政治スローガンの域を出ていない、とThe Economistは指摘するわけです。 |

|
ただ、Global Britainという考え方は、現実の英国を描写しているともいえる。英国が参加者としてかかわっている国際組織を挙げるならば、主なものだけでもNATO、G7、G20、英連邦(the Commonwealth)etcがある。さらに英国は国連の常任理事国の一つでもある。どの機関をとっても、世界に与える影響という点では非常に大きなものばかりです。しかも英国は核兵器を保有し、防衛予算はNATO加盟国の中ではアメリカに次いで大きい。いわゆる「ソフトパワー」にも事欠かない。途上国援助のために多額の予算を使っているし、ワクチンを始めとする科学技術面での国際貢献も無視できない。今年(2021年)英国は、G7会議と気候変動に関するCOP26会議の議長国をも務める国でもある。
コンセンサスを重んじる(大きすぎて身動きが取れない)EU加盟国であるよりも、それから独立することでより大きな柔軟性をもって行動できる。ベラルーシ支援もできるし、日本やトルコとの貿易協定も柔軟性あってこその成果だった。さらにワクチン同盟と呼ばれる組織のために資金調達をすることができた・・・Global Britainの可能性は非常に高いと言える。
|
 |
ただしGlobal Britainとしての英国を実現するためには、克服しなければならない課題もある。特に国内問題。かつてマーガレット・サッチャーやトニー・ブレアの率いた英国が国際舞台で「実力以上の力」(punch above its weight)を発揮できたのも、彼らの国内的な基盤が強固であったからこそである、と。現在の英国は国際社会においては「コロナ対策では四苦八苦する国」であり、経済もとても順調とは言えない国と考えられている。
スコットランドとアイルランド
さらに国内の政治問題として、スコットランドの独立とアイルランドの統一(共和国と北アイルランドの合併)問題がある。後者についていうと、アイルランドと北アイルランドの間を走る国境は、英国がEUを離脱した後も「検問なし」を維持することで合意している。そうなると、北アイルランドは事実上はEU加盟国と同じ扱いを受けるようになるということです。となると北アイルランドが英国を離れるのは時間の問題ともいえるわけです。スコットランドが相変わらず独立を志向していることは周知のとおりです。このように解体の危機さえはらんでいる国は国際社会においてもまじめに受け取ってはもらえない、とThe Economistは指摘するわけです。
国内おける意見の分裂は対米・対中関係にも表れているけれど、対ヨーロッパについても深い溝が存在している。メイ首相はEUとの外交・防衛政策のあるべき姿を「野心的なパートナーシップ」(ambitious
partnership)と呼んだけれど、ボリス・ジョンソンが望んでいるのは、NATOや個々の欧州諸国との「その場その場」(working ad
hoc)の協力なのだそうです。
|
 |
The Economistの社説の結論は次のようになっています。
- 歴史が示しているとおり、英国はいずれはヨーロッパに引き戻されるだろう。共通の利害や資源(リソース)の確保などのことを考慮するとヨーロッパとのパートナーシップは欠かせない。BREXIT派の人間には奇妙に映るかもしれないが、英国が欧州に対する盲目状態を早く抜け出すことによってGlobal
Britainの展望はさらに大きく開けてくるともいえるのだ。History suggests that Britain will eventually
be pulled back towards Europe. Shared interests and the need to pool resources
argue for a partnership. Strange as it may seem to Brexiteers, the sooner
the ex-eu member gets over its blindness over Europe, the better the prospects
for Global Britain.
つまり保守党の掲げるGlobal Britainという理想は、ヨーロッパの一員として存在することによってのみ達成が可能になるということです。 |
▼2016年に国民投票が行われた際に、BREXIT推進派の重鎮たちが強調したのが「英国は英国人が統治する」という理屈だった。そのような人たちが担ぎ上げたのが「地球規模で活躍する英国:Global Britain」という発想だった。「反EU=引きこもり」ではないというわけです。しかし「独立国として世界を股にかけて活動する」という発想が、19世紀~20世紀前半に存在した「七つの海を支配した国」の発想と何がどう違うのか?
▼ざっと半世紀も前(1973年)に自分から頼み込んでEC加盟を実現したのは、「共存するヨーロッパ」が持っていた経済力だった。要するにおこぼれにあずかったわけです。そして50年経って主張したのが「ヨーロッパのいいなりにはならない」という姿勢だった。それでも文化・文明の点で英国がヨーロッパの一部であることは否定のしようがないし、そのことは世論調査が示す英国人のBREXITへの疑念の根強さでも明らかです。 |
|
|
back to top |
3)国際社会の定義が気になる
|
 |
| この記事は10年以上も前に掲載したことがあります。再掲載する理由は、BREXITやトランプのやり方を見ていて「国際社会」というものの意味をもう一度確認したいと思うからです。 |
|
つい言葉にこだわってしまうけれど「国際社会」というのが気になる。「国際社会が一致団結して・・・」とか「そのような暴挙は国際社会が許さない」とか言ったりする。この言葉は英語のinternational communityの日本語訳で、日本の政治家が国連で演説する時にも大体この言葉を使う。普通communityという英語は「共同体」と訳すはずなのに何故か「国際共同体」といわない。EUがまだEC(European Community)であった頃に、日本ではこれを「欧州共同体」と言っていたのに、である。「国際社会」という日本語をinternational societyと英訳したら入学・入社試験ではバツを貰うのだろうか?逆にinternational communityを「国際共同体」とやったら落とされてしまうのだろうか?
There is no such thing as...
その昔、英国にマーガレット・サッチャーという首相がいた。彼女は在任中にいろいろと話題になる言葉を残している。その一つに「There is no such thing as society(この世に社会なんてない)」というのがあった。老人介護の問題をめぐって女性雑誌とのインタビューの中で言った言葉で、「国民のことを考えない独裁者の言いそうなことだ』というわけで新聞にさんざ叩かれた。
|
 |
彼女は自伝の中で「メディアはいつも私の発言を歪曲して伝える」と文句を言っており、この発言についても「この言葉のあとに『この世にあるのは家庭であり、個々の人々である』と言ったのに、この部分は無視された」と怒っている。 老人介護について彼女はCommunity Careという政策を進めていた。お年寄りの面倒を見るのは政府ではなくコミュニティの責任だというわけで、この場合のコミュニティとは家族とかお隣さんのような具体的な人々のことを指していた。
彼女は「社会(society)」という言葉を「インテリの作りだした抽象的な概念」として嫌っていた。極めて熱心なキリスト教徒の父親のもとで育った彼女にとってコミュニティは、教会を中心にした隣近所のようなものであったのかもしれない。いずれにしても「この世に社会なんてない」というのは「自分たちのことは自分たちで面倒を見なさい。社会(政府)などに頼ってはいけない」という意味であったらしい。
ブレアの国際共同体論
やはり英国首相であったトニー・ブレアという人は、サッチャーさん以上に「コミュニティ」という言葉を口にした。彼の場合は「お隣さん」どころか世界全体を「コミュニティ」と考えていたふしがある。1999年にシカゴで演説したときに「国際共同体主義(doctrine of international community)」なるものを持ち出した。それによると「ある国の内部で大量虐殺などのような人権蹂躙が行われている場合、そこへ軍隊を送り込んででもこれを止めさせるのが国際共同体の責任だ。何故なら人権蹂躙の結果として(例えば)難民が流出して近隣諸国にも影響を与えるからだ」という。 現在の世界では国と国との相互依存の度合いがきわめて深いので、昔ながらの「内政不干渉」を決め込むことができなくなっているというのである。 |
 |
|
ブレアの理屈によると、英国や米国がイラクを攻撃したのも「サダムのような残忍な独裁者を倒してイラク国民を解放し、国際社会への脅威も取り除いた"正しい戦争」(just
war)"」ということになる。もちろん当時の日本の首相(小泉純一郎)もイラクに自衛隊を派遣することで、「正しい戦争」のために破壊されたあの国の復興を支援しようというのだから「国際社会の一員」としての役割を果たしたというわけである。
「社会」の定義
むささび自身の定義によると「社会」(society)はさまざまな考え方や価値観を持った様々な人間が集って押し合いへしあいしている状態のことをいい、「共同体」(community)は同じような価値観とか理想などを共有する人々や国が集った状態のことを言う。トニー・ブレアのいわゆるinternational communityの中に北朝鮮は入っていたのだろうか?パレスチナは?スーダンは?ミャンマーは?キューバは?いずれも現状のままでは入れてもらえないだろう。おそらく第二次世界大戦前の日本もダメだろう。イラクに兵隊を派遣しなかったフランスは?ドイツは?中国は?ロシアは?途中で引き揚げてしまったスペインは?人質解放と引き換えに軍隊を本国に呼び戻してしまったフィリピンは…?
このように見ていくと、この世界にはinternational societyはあるにしても、international communityは「あったらいいのに」というものではあっても、実際には存在しないということになる。今の世の中であえて「それらしきもの」を挙げるとすればニューヨークの国連しかない。その組織の事務総長という人が「米英軍のイラク攻撃は国連憲章違反だ」と言い切ったりしているのである。
|
 |
米軍がバグダッドに攻め込んでフセイン大統領の像を引きずり倒した時、米軍兵士が星条旗を掲げようとしたシーンを鮮明に覚えている。あのアメリカ兵やブッシュ大統領にとって、イラク戦争は9・11テロに対する「復讐」であって「国際社会」などというもののための戦いではなかったはずだ。
Societyは〇、Communityは△
しかしあの頃のブレア首相にとってイラク戦争は、「国際共同体主義」という思想に従って、サダム・フセインという独裁者から「国際社会」を守るための正義の戦いであったわけだ。彼の場合、ブッシュ大統領のように自国の大都市がアルカイダのテロに見舞われたわけではないから(アメリカのように)熱狂的な復讐心に燃えた国民が背後にいたわけではない。あったのはブレアなりの「国際共同体主義」という理想である。
このような政治家を「理念がある」と言って称賛し、返す刀で「日本の政治家には理念がない」と嘆いたりする人がいる。しかし「国際共同体」という存在もしないものを守ると称して、他国に爆弾を落とすことを「理念」と呼ぶのなら、そんなもの要らないし、international communityなどという言葉を安易に使ってもらいたくもない。
というわけで、私が試験官なら「国際社会」をinternational societyと英訳した人には○を、international communityという答には△(×ではない)を与えるだろう。international communityの日本語訳は「国際共同体」の方がふさわしい。「不自然」なのがいい。 |
| ▼前の記事に関連するけれど "Global Britain" というのと "International Britain" というのでは何がどう違うんですかね。前者は「地球規模の英国」というわけで、何やらガキ大将の英国という気がしないでもない。後者の "International" という言葉のポイントは、何かと何かの間という意味の "inter" という接頭語にあるのではありません?「国(nation)と国(nationの間」という概念です。となると、Globalは支配的、Internationalは共存的ということになる。 |
back to top |
4)「逃げ遅れ」で得たもの
|
 |
むささびジャーナルでは何回か紹介された北九州市の東八幡教会の奥田知志(ともし)牧師による新しい本が刊行されたのですね。タイトルは「『逃げ遅れた』伴走者」で、30年以上にわたってホームレスのような貧困者の救済活動に取り組んできた奥田牧師による自問自答(何が面白くてそのような活動に取り組んできたのか?)の書のようであります。信念・情熱・愛情・・・牧師によると、活動を始めた当初は、そうした意識もなかったわけではないけれど、やっているうちに消えてしまった。現実が厳しすぎたということです。自分が考えていた「信念」だの「愛情」だのという世界ではなかったということ。
|
 |
そのような精神状態の中で奥田牧師の心に浮かんだのは「出会った責任」という言葉だった。助けを求める人間と出会ってしまったからには「無かったことにはできない」、「出会った責任がある」と自分で自分を説得し、奮い立たせようとした。そんな中で奥田さんらが気づかされたのは「責任がある」ということと「責任をとる」ことの違いだった。ホームレスがホームレスであることに自分たちは「責任をとる」ことはできない。けれどそのような人びとと出会ってしまった自分の運命のようなものに対する責任はある、と感じる。
貧困者らの運命を自分の運命として「引き受ける勇気」はないけれど、かといってそこから「逃げる勇気」もなかった・・・。奥田さんが、この本を通じて目を向けている(とむささびが想像する)のは、逃げる勇気もない、気弱な自分です。引き受ける勇気はないかもしれないけれど、逃げ出す勇気もない。結果としてその場に残ることに・・・つまり貧困問題の現場に残されたのは「逃げ遅れた人間」であり、奥田牧師もその一人であるというわけです。 |
 |
そんなこんなの30年間、逃げ遅れの30年間で、奥田さんらは「思いがけない出会いを経験」することができた。仕方なしに通い続けた現場で体験した出会い・・・
- それは、大変だけど決して不幸ではなかった。逃げ遅れたことに感謝さえできた。
と奥田さんは言っており、そのことを語るのが「『逃げ遅れた』伴走者」という本のようであります。 |
| ▼実はむささび自身、まだこの本を読んでいません。ただこの著者の普段の言動から想像して、ボランティア活動のようなものは、理屈抜きで「とにかくやってみること」が全てであるということを言いたいのではないかと(むささびは)想像するわけです。そのことはボランティア活動だけではなくて、生きること自体にも当てはまるのでは? |
|
back to top |
5) どうでも英和辞書
|
| A-Zの総合索引はこちら |

|
Covidiots:コロナ犯
|
「コロナ犯」という日本語はむささびが勝手に付けたものです。欧米では「新型コロナウィルス」のことをCovid-19と呼ぶケースが多いですよね。Covidiotsは、この「新型コロナウィルス」に関連して犯した犯罪が理由で刑務所に入れられている人たちのことをいうのだそうです。バーミンガム・メールというイングランド中部の地方紙のサイト(12月27日)に出ていた記事によると、ある人物はバーミンガム市内を走るバスに乗った際に、運転手(女性)と口論になり「オレはCovid-19にかかってるんだぜ」と言いながら運転手めがけて唾を吐きかけるという行為に及んで逮捕された。
ただこの記事によると、この人物がバスの運転手にひどいことをやった時点で実際に新型コロナのウィルス保持者であったかどうかはよく分からない。が、その後釈放されたときにこのウィルスの保持者となっていたことは間違いがないらしい。というわけで、新聞は彼のこともCovidiotと呼んでいる。つまり彼の場合は刑務所内で感染したということもあり得るというわけです。
実はCovidiotという言葉は(むささびが知らなかっただけで)かなり出回っているもののようで、日本語のウィキペディアにも出ていました。それによると
- コビディオット(Covidiot)は、利己的に行動して日用品の買い占めをしたり、パーティーを行なったりしてコロナ禍で必要な意識が欠如してしまっている人を指す言葉である。
と定義づけられており、新型コロナウィルス(Covid)と「愚か者」(idiot)を繋げて出来た造語だそうです。この記事のアタマの部分に掲載されている顔写真は、いずれも英国のCovidiotsです。 |
back to top |
6)むささびの鳴き声
|
▼ネットを見ていたら高須クリニックの高須克弥という院長さんが、作家の村上春樹さんを批判するツイッターを発信したという記事が出ていました。村上さんが、あるネット・ニュースのインタビューで日本の政治家のコロナ対応について、次のように批判したのだそうです。
- 今の総理大臣は紙に書いてあることを読んでいるだけではないか
- (コロナの対応について)各国の政治家に比べ日本の政治家は最悪だった
▼高須院長さんは、この批判について次のように批判しているのだそうです。
- 村上春樹先生は日本人ですか?日本人が選んだ代表を最悪と言うのは日本人が最悪だと言っているのと同じだと思います。残念な発言です。
▼日本人が選んだ代表を「最悪」と言うのは「日本人が最悪」だと言っているのと同じ・・・なんですか?シンゾーや菅さんに限らず、首相のことを「最悪だ」と批判するのは村上さんだけではありまへんで。わ、分かりました、むささびともあろうものが、こんな人の言うことをマジメにとって文句をつけるのはやめた方がいい、と、そう仰るんですね。そのとおりです、だからこの辺でやめておきます。ここをクリックすると、この記事が出ています(まだ削除されていなければ、の話ですが)。
▼でもぉ…12月28日付の東京新聞のサイトに「大村知事リコール、署名の8割超が不正か」という記事が出ているんですよぉ。愛知県知事に対するリコールというのがあったのですが、提出された署名の8割超が「選挙人名簿に登録されていない人物や、同一人物の筆跡と疑われる署名」があったとのことで、このリコール運動の中心となったのがこの高須克弥院長である、と。何なんです、このタカスとかいう人⁉「タコス」の間違いじゃないよね?
▼むささび夫婦が埼玉県飯能市で暮らすようになって40年以上経つけれど、市役所のやることに腹を立てることがけっこうあります。市役所発行の広報誌に出ていたものに「観光・エコツーリズム推進課」の企画として『冬の天覧山で野生動物の不思議にせまる!』というのがありました。夕方から夜にかけて市民が集まって天覧山という自然公園のような場所で見ることのできる動物を観察しようという催しです。
▼観察の対象にはむささび(ホンモノ)も入っている。問題は参加費用です。定員15人で「大人6000円、小学生以下4000円」と書いてある。「小学生以下」には小学生も入るのかどいうか確かではないけれど、小学6年生までは該当するとしても、お父さんと子供一人で1万円ということになる。むささび(私のこと)の感覚からすると法外な値段です。どんなに素晴らしいことが体験できるのか知らないけれど、貧乏人締め出し企画としか思えない。それがエコツーリズムってものなの?ええ加減にさらせ!
▼というわけで、このところ埼玉県は好天気が続いています。皆さまのところは如何ですか?でも、寒いのは嫌です。お元気で! |
|
back to top |
←前の号 次の号→ |
 |
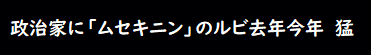 |

