目次
1)スライドショー:空中の気分?
2)The Economist社説①<「トランプ」に反対する>
3)The Economist社説➁<優れた大統領とは?>
4)再掲載:モノリンガルの悩み
5)どうでも英和辞書
6)むささびの鳴き声
7)むささび俳壇
|
1)スライドショー:空中の気分?
|
 |
例によって?BBCのお世話になります。今回のテーマは "in the air"。いろいろなモノや動物・人間がいろいろな理由で空中に飛ぶ…それをカメラに収めた。たったそれだけのことなのでありますが、何故か飽きがこないのですよ。
|
back to top |
2)The Economist社説①:「トランプ」に反対する
|
 |
10月31日付のThe Economistの社説が11月5日に迫ったアメリカの大統領選挙について
- A second Trump term comes with unacceptable risks
と言っています。「二期目のトランプでは余りにもリスクが大きすぎる」と。記事の書き出しは次のようになっている。
- NEXT WEEK tens of millions of Americans will vote for Donald Trump. Some will do so out of grievance, because they think Kamala Harris is a radical Marxist who will destroy their country. Some are fired up by national pride, because Mr Trump inspires in them the belief that, with him in the White House, America will stand tall. Yet some will coolly opt to vote Trump as a calculated risk. 次週に迫った大統領選挙では何千万というアメリカ人がドナルド・トランプに投票するだろう。中にはハリス候補に対する否定感覚からそのようにする人間もいる。ハリスは極端な共産主義者であり、アメリカを滅ぼすことになるであろう、と。別の人間はトランプが焚きつける愛国心に燃えて、彼がホワイトハウスにいる限りにおいてアメリカは堂々と胸を張っていられるであろうと考える。中にはもっと冷静な計算によってトランプを支持する向きもあるだろう。
このうちの最後のグループである「冷徹な計算による」トランプ支持者の中にはThe Economistの読者も多いはずであるけれど、彼らは個人的にはトランプのような人間とは付き合いたくもないし、自分の子どもにだけはトランプのような人間になって欲しくないと考える人も多いはずだ、と。ただそのトランプも大統領であった時には「悪いことより善いことをする:he did more good than bad」大統領ではあったはずだ、と。さらに彼らは世の中の「反トランプ論」には誇張も多いと考えている。実際のトランプ大統領はスタッフや官僚たちによって支えられており、トランプ本人の欲求などは抑えられてしまうはずである、と。 |
 |
The Economistは、トランプの考え方がスタッフや官僚たちによって支配されているという発想は「独りよがり(complacent」だと考えている。アメリカ自体はトランプ大統領下でも「そよ風の時代」が送れるかもしれないし、繫栄さえ謳歌できるかもしれない。が、よく考える読者ならば「トランプのアメリカ」が抱えるリスクを無視することはできないはずだ。さらにトランプがアメリカの大統領になるということは、彼自身が「自由世界」のリーダーになるということであり、そうすることで米国人は経済・法と秩序・国際平和などの面で大きなギャンブルを犯すことにもなる。彼をリーダーとすることによる国際社会の危機状況については誰もこれを予想することはできない。しかしThe
Economistの読者がそれを「小さな危機」にすぎないと考えるとすれば、それは自分を欺いてる(deluding themselves)というほかはない。
このような見方を「考えすぎ:alarmism」として無視する向きもあるであろうし、第一期のトランプ大統領時代はそのようなことはなかった。国内ではトランプ政府が行った減税と規制の自由化政策はどのような先進国よりも早かった。コロナ禍への対処にも充分な批評を費やした。国際舞台においては、トランプは中国との対決でも十分に強い姿勢を貫いた。またイスラエルとその隣国との関係についてトランプは「アブラハム合意:Abraham accords」という政策を通して友好関係の促進に寄与した。トランプはさらに同盟国における防衛費の増加を促進もした。
もし2016年のThe Economistの見る目が誤っていたとしたら、何故いま警告を発するのだろうか?Why heed our warning now? 答えは、あの頃よりも現在の方がリスクが大きいからということにある。政策的には、今のトランプの方があの頃のトランプよりも誤っているし、世界の危機ははるかに大きい。 |
 |
あの頃のトランプの政策から始めてみよう。2016年の頃の共和党はミット・ロムニー(Mitt Romney)のグループとトランプのグループとの対立がひどかった。そんな中でトランプはすべての輸入品に20%の関税をかけると同時にメキシコから輸入される車に対してのみ200%もしくは500%もの税金を課した。と同時に何百万人もの「違法移民」(その多くがアメリカ国内で職を有し、子どもさえいた)を追放することさえ行った。その一方でトランプは財政が赤字であるにもかかわらず減税を行ったりもした。とても財政管理に気を配っている大統領であるとは思えなかった。
トランプの財政政策は基本的にインフレを誘うものであり、連邦準備制度(Federal Reserve)の方針とは合わない。またトランプの貿易政策は外国との貿易戦争を起こしかねないものであり、最終的にアメリカとは合わない。インフレ、管理の利かない財政赤字、そして経済運営についての制度上の不備などを背景として、外国の金融機関が米財務省に対して無制限に金を貸すことをしなくなる。
アメリカ経済は世界の憧れの的となっているが、それは「創造的破壊:creative destruction」を伴うこともある自由で開放的な市場の存在を前提にしている。トランプ氏を見ていると、時として彼は19世紀に帰りたいと思っているのではないかとさえ思えてくる。即ち関税や税金を利用して自分の友人たちには有利な商売を許し、敵には罰を与えるような振る舞いということである。そのような行為は自国の貿易収支の向上に役に立つかもしれないが、アメリカが依って立っている基盤そのものを破壊しかねないものとなる。 |
 |
第二期トランプ政権の到来に関連して恐れなければならないことがもう一つある。それは「世界が変わった:the world has changed」ということである。2017~2021年の第一期においては大体において世界は平穏だった。それを変えたのはトランプ支持者たちで、彼らはトランプの予知不能性と強力かつ変わった行動を支持した。イランの重鎮であったガーセム・ソレイマーニーという人物が暗殺された際、アメリカの外交政策の専門家たちはその深刻な影響について大いに警告を発した。が、トランプはこれを深刻な出来事とは受け取らなかった。しかし2024年の今、米国に新しい大統領が生まれた際に、中東において同じような事件が起こると、アメリカの安全そのものが脅かされることになるだろう。同じことがウクライナに関連するロシアの脅威についても当てはまる。
第二期のトランプが悩まされるこれらの問題は第一期のトランプ政権時代には存在しなかったもので、彼にっとっては格好の試練となる。口達者なトランプはいずれはウクライナに平和をもたらすであろうが、イスラエルの戦闘的姿勢に対するトランプの鷹揚な態度がうまくいくという保障はない。トランプはまた「同盟国」とされてきた国々に対しても敵意を感じさせる態度をとっている。これらの国々は(トランプに言わせると)弱小国をさらに弱い存在にするものである、と。トランプは脅しによって生き残ることはあるかもしれないが、これらの国々はNATOにとっても脅威の存在となる。その一方でアジアでは中国が眼を光らせており、アジア諸国自体もこれまでのようにアメリカの核の傘を頼りにはしなくなるであろう、と。
内政面であれ外交面であれ、第一期トランプと第二期のそれとの間に横たわる大きな違いは、第二期トランプの方が「遠慮がない:less constrained」ということ。かつてトランプはメキシコにある麻薬関連の研究所目がけてミサイルを撃ちこもうとして関係者に止められたことがある。以来、共和党が音頭をとってトランプへの信頼度をチェックするようにしているし、党とは無関係の組織も次期政府における大統領への忠誠心をチェックするシステムを構築している。また最高裁による大統領のチェックは緩めている。 |
| ▼The Economistの編集姿勢からすると、特定の政治家をとり上げてけなしまくるということは珍しいと思うのですが、トランプおよび彼を支持するアメリカ世論には黙っているわけにはいかないと思ったのでしょうか? |
|
|
back to top
|
3)The Economist社説➁:優れた大統領とは?」
|

この記事はThe Economist誌の社説のつづきです |
優れた大統領は国を団結させる。トランプ氏の政治的な「才能」は、人間同士を敵視させることにある。4年前にミネソタ州でジョージ・フロイドという黒人青年がコンビニで偽の20ドル紙幣を使用したのではないかと疑ったことを受けて逮捕され、白人警察官によって殺害されたという事件があった。この事件後に大統領であるトランプが行ったのは、将来このような事件があった時は警官や軍隊は犯人の足を狙って銃撃すべきだというコメントだった。アメリカの繁栄は、政治的な立場は別にして、それぞれの人間が公明正大な扱いを受ける権利があることを基礎にしている、というわけで、トランプ大統領は司法省までも自分の敵にするところだった。
トランプとは対照的に民主党の大統領候補であるカマラ・ハリスが強調するのは安定性(stability)である。彼女は政治家としては目立った存在ではない。彼女が有権者に訴えたのは、自分が権力の座についたら何をしたいのかということだった。見かけ的にはハリスは優柔不断で自信がないような人物に見える。が、カマラは大統領候補になるべく民主党が有している左翼思想を捨て去って、中道を歩んできた。 |
 |
カマラにはごく当たり前の欠点はあるけれど、それが故に政治家になれないというような欠点ではない。トランプと比較すると「規則」とか「資産形成」というものに関する感覚が異なる。The
Economistに言わせると、カマラ・ハリスに「超一流の大統領:stellar president」であることを期待するのは無理かもしれないが「失敗する人物とも思えない:you
cannot imagine her bringing about a catastrophe」というわけです。
- The Economist社説の締めくくり
- 大統領は聖人君主である必要はない。我々(The Economist)は第二期のトランプ政権が悲劇的でないことを祈るのみである。トランプ氏はアメリカ及び世界に対して受け容れようのないリスクを受け容れることを要求している。もしThe Economistに一票を貰えるのであれば、我々はそれをハリス氏に投じるであろう。Presidents do not have to be saints and we hope that a second Trump presidency would avoid disaster. But Mr Trump poses an unacceptable risk to America and the world. If The Economist had a vote, we would cast it for Ms Harris.
|
|
|
back to top |
4)再掲載:モノリンガルの悩み
|
 |
英国の語学教育機関であるCILTが発表した子供の言語能力に関する報告書によると、バイリンガルの子供は将来の全国テストなどでも好成績を収めるケースが多いとのことであります。
この報告書によると、英国の小学生の8分の1にあたる約85万人の子供たちが、学校では英語を使っていても家庭では違う言語を使っている・・・つまり「外国人」の子弟というわけです。このようなバイリンガルの子供たちの方がモノリンガルの子供より、英語以外の外国語習得がうまいらしい。
日本と比べるとはるかに「国際化」が激しい英国の場合、子供たちも外国語にさらされるケースが多い。例えばロンドンのある小学校の場合、44種類の言語が子供たちによって使われているとのこと。44種類ですよ!ここでは月ごとに「今月の言語」(language of the month)を決めて、生徒たちがさまざまな言語に触れることができるような企画を行っている。 |
再掲載
英語しかできない悩み?

むささびジャーナル第100号
2006年12月24日 |
日本において英語を小学校から教えようという動きがある一方で、英国においては外国語教育がかなりなおざりにされているということについては、むささびジャーナル第97号「バイリンガルの子供は伸びる?」でも触れました。これに関連して、The Economistの12月16日号に国際言語としての英語の普及についての面白い記事が掲載されています。
同誌はまず英国人の外国語能力について触れ、外国語で会話ができる英国人はわずか30%(just 30%)であり、EUの中では下から2番目(ビリはハンガリー)なのだそうです。学校教育においても外国語はかなりなおざりにされており、公立学校の殆どが外国語の授業をギブアップ、私立の学校でもこれにならう学校が増えている。16才になると必ず受けなければいけない学力テストであるGCSEでも外国語をとる学生は半分にすぎない。
で、国際言語としての英語の普及についていうと、世界の総人口(約66億)のほぼ4分の1が、程度の差こそあれ英語を話す、とThe Economistは言っています。つまり第二言語として使う人も含めて大体16億人が英語を使うということです。このうち約4億が英語を母国語としている人です。中国で英語を習う人の数は1億8000万であり「日本では5才の児童の5分の1が英会話を習っている」(more than a fifth of Japanese five-year olds now attend classes in English conversation)とのことであります。 |
 |
と、このように皆が英語を使うようになるってことは、ネイティブスピーカーにとっては結構なことのように思えるかも知れないが、実はそうではないというのがThe Economistの指摘です。英語を第二言語として上手に使う人(バイリンガル)は、英語しか話せないモノリンガルに比べれば国際的な視野が広いということであるからです。
モノリンガルにとってさらに困るのは、英語を第二言語として使う人の間の会話が増えるに従って、従来の生粋の英語でない英語、いわば地球語(Globish)を使うケースが増えているということです。最近IBMの副社長を務めたJean-Paul Nerriereという人が本を出したらしいのですが、それによると、IBMの社内ではGlobishで十分通用してしまっているとのことです。Globishのボキャブラリは1500語で、アメリカ人や英国人なら使いそうなイディオム、略語、ユーモアなどは一切なし。ひたすら基本的に大切な事柄が通じるようにできている。味気ないという意味では、カフェイン抜きのコ-ヒーをもじってdecafenated Englishとも言うべく言語なのだそうであります。韓国人と日本人のスタッフなどは、これで「会話」するのが一番簡単らしい。 |
▼なるほど・・・そういえば一昨年(2004年)だったかオックスフォード大学の夏季講座なるものに参加したときに、先生が言ってましたね、今や英語はBritishでもAmericanでもなくWorld
Englishの時代なんだって。昔、世界言語のエスペラントというのが話題になったことがあったけれど、結局広がらなかったですね。
▼むささびも毎日の仕事の中で、非英語圏の人たちと英語で意思疎通を図ることが多いわけですが、これって結構単純でいいんですね。洒落た言い回しだの、微妙なニュアンスなんてどうでもいい。要するにビジネスが出来ればいいんですからね。Globishの世界では、本当に基本的な英語だけで何とかなる。英語の先生も敢えて「ネイティブ・スピーカー」である必要はないんです。この際、Globish
Schoolというのをやったら受けるかも?(2006年12月) |
|
back to top |
5)どうでも英和辞書 <A-Zの総合索引はこちら>
|
 |
duelling pitch:決戦場
11月3日付のBBCのサイトのトップ記事が
- Harris and Trump make duelling pitches in crucial North Carolina as election day looms
という見出しだった。"duelling pitch" というのは、例えば闘牛のような戦いが行われる会場のことを言うのですね。見出しの意味はもちろん
- 大統領選挙が近づくにつれて、ハリスとトランプの両者がノース・カロライナという重要な決戦場で戦っている
というような意味です。 |
| back to top |
6)むささびの鳴き声
|
 |
▼上の写真は、このほど英国保守党の党首に就任することになったKemi Badenoch(ケミ・ベーデノック)氏です。11月3日付のBBCのサイトに出ていたもので年齢は44才、両親はナイジェリア出身です。英国保守党が党首なるものを持ち始めたのは1922年、以来18人の党首を有しているけれど、女性党首は、あのマーガレット・サッチャー(1979-90)、ティリザ・メイ(2016-19)、リズ・トラス(2022)に次いで4人目です.
▼今回彼女が党首に就任するにあたっては、ロバート・ジェンリックという保守党議員との争いになったのですが、ベーデノック:53,806票、ジェンリック:41,388票という僅差での勝利だった。保守党の党首選びは、党員による投票で決めるのですが、現在の党員数は約13万2000人で、2年前に比べると2万人も減っている。要するに英国人の間における保守党人気が低迷しているということで、世論調査機関のYouGovが行ったアンケート調査によると、普通の有権者で「ベーデノック」や「ジェンリック」という名前を知っている人間さえ少なかったのだそうです。
▼日本における「総裁選」も大して変わらない? |
back to top |
7)むささび俳壇
|
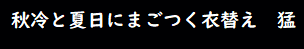 |
| 前澤猛句集へ |

←前の号 次の号→ |

