目次
1)スライドショー:自慢のショット
2)幸福と親切は両立するか?
3)再掲載①:「平和ぼけ世代」のプライド
4)再掲載➁:ノーと言える日本
5)どうでも英和辞書
6)むささびの鳴き声
|
1)スライドショー: 自慢のショット
|
 |
今回もBBCのサイトにお世話になりました。3月23日付のサイトに出ていたもので、"My Best Photo" というテーマに応募したいろいろな写真の一つ。撮影したのはVerna Evans
という人なのですが、名前からして女性であることは分かるけれど、プロの写真家なのか趣味人なのかは分からない。彼女によると、この家の垣根に向かってカメラを向けていたら、いきなりこの少年が熊のお面をかぶって出てきたのだそうです。それにしても、このシャッターチャンスの捉え方は見事ですね! |
back to top |
2)幸福と親切は両立するか?
|

|
アメリカの世論調査機関、Gallup のサイト(3月19日付)に
という題のエッセイが出ていました。「親切な世の中=幸せな世の中…か?」という意味ですよね。見出しの次に説明風の文章が載っている。
- Generosity could do more for people's wellbeing than earning a higher salary 人間の幸せのためには、高い給料よりも寛容さの方が大事かもしれない
Gallup は毎年、英国のオックスフォード幸福研究所(Oxford Wellbeing Research Centre)および国連の永続的発展ネットワーク(U.N.
Sustainable Development Solutions Network)と協力して「世界幸福度調査:World Happiness
Report」という報告書を作成しているのですが、このエッセイは2025年の報告書について書かれたもののようです。
Gallupの幸福度調査が明らかな傾向として示しているのは「慈悲の行為:acts of benevolence」と呼ばれるものがコロナの頃(pandemic-era)に比べると幸福度の原因としては落ちているということなのだそうです。ここでいう「慈悲の行為」にはボランティアや金銭の寄付などという行為が含まれる。
で、下記の表が示している今年の幸福度ランキングですが、トップ10を見ると、フィンランド、デンマーク、アイスランド、スウェーデンのような北欧諸国の健闘が目立ちますが、南米のコスタリカやメキシコ、中東のイスラエルらの存在も目を引きます。
一つ目立つのはアメリカの不在でアメリカは幸福度20位にも入っていないのだそうです。スイス、カナダのようないわゆる「欧米先進国」も圏外にはずれている。幸福度最下位はアフガニスタンとなっている。 |
幸福度トップ10とボトム10
 |
| ▼上記のグラフで使われている数字は「キャントリル尺度(Cantril Self-Anchoring Striving Scale)」と呼ばれるものを使っている。それぞれの国の人びとに「自分にとって最良の人生から最悪の人生の間を10段階に分けたとき、いま自分はどこに立っていると感じるか」という問いに答えてもらう。幸福度が高い人びとが多い国は数字も高くなる。トップのフィンランド人のスコアは7736、最下位のアフガニスタン人の場合は1364というわけです。 |
|
back to top |
3)再掲載①:「平和ぼけ世代」のプライド
|

|
| このエッセイは20年以上も前(2003年11月)に『外交フォーラム』という専門誌に掲載されたものです。書いたのはむささび(春海二郎)です。記事の中にオークの木のことが出てきますが、これは2002年に行われた日英グリーン同盟に関連しています。 |
 |
JR尾道駅を降りると直ぐ海になっていて、それを挟んで向島町がある。文字通り「向かいの島」なのだ。町外れの高台にある運動公園に一本のイングリッシュ・オークの木があり、オークが見下ろす町の中心部にある小さな広場には「時の翼」という銘のついた記念碑が立っている。オークも記念碑も2002年3月に「日英友好モニュメントを建てる会」というグループによって植えられ、建てられたものである。オークは「日英グリーン同盟」という植樹活動として英国大使館から寄贈されたもので、同じようなオークが全国204カ所に植わっているが、モニュメントは向島町にしかない。 |

尾道市街 |
向島町には第二次世界大戦中に英米人の戦争捕虜の収容所があり、英国人捕虜約100人のうち23人が、栄養失調や病気で死んだとされている。元捕虜とその遺族たちとの交流をするうちに、友好モニュメントを作ろうという話になり、その中心となったのが、向島町キリスト教会の南沢満男牧師と小林皓史さんだ。南沢牧師は「日英同盟を破棄したことは、日本にとって最大の過ち」だと言う。日本は、英国との軍事同盟のみならず「精神的同盟」をも破棄してドイツの観念論に傾斜し、それが皇民思想に繋がったと考えている。一方、小林さんはクリスチャンではないのだが、在英日本人で元戦争捕虜たちとの和解活動を続けている恵子ホームズさんのことを新聞で知り感激、モニュメントの活動に参加した。
小林さんは日本軍捕虜として生きた英国人が、自分たちの生活を描いたイラスト本の日本語版を自費出版した。本のタイトルは『忘れないように』となっているが、原題はLest
We Forget。日本語は主語を省くことが多いため、ここでも誰が何を「忘れないように」するのか曖昧だが、原文ではWeが作者も含めた英国人捕虜たちのことをさすのは明らかだ。しかし日本語だけ見ると、日本人を含めた人類一般に対するメッセージとも受け取れる。小林さんは、「この本を自虐史観と批判する人もいて、ほとんど売れていない」と残念がる。 |
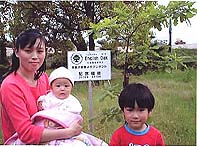
|
小林さんも南沢牧師も、私とほぼ同い年。つまり「自虐史観」と「平和ぼけ教育」にどっぷりと漬かって育った世代だ。売れない本を作ってしまった小林さんだが、「私が出会った訪日した戦争捕虜は、みな『日本に対する恨みの亡霊を成仏させることができた』という手紙をくれます。それが私の誇りでもあります」と語ってくれた。
なお、広島県因島市、三重県紀和町、新潟県上越市、山梨学院大学などにも、同じ趣旨(日英グリーン同盟)のオークが植えられている。きっとそれぞれの物語が育っているに違いない。 |
back to top |
4)再掲載➁:ノーと言える日本 |
|

|
むささびジャーナルが誕生して間もない2004年12月末(第48号)に『ノーと言える日本』というタイトルの記事が掲載されています。これはソニーの盛田昭夫会長と作家・石原慎太郎によって共同執筆された本で、日米貿易摩擦を背景にして「アメリカのいいなりになるばかり」の日本に疑問を呈したとされるものだった。出版されたのは1989年1月だった。
|
ノーと言える日本

むささびジャーナル48号
2004年12月26日 |
かつて「ノーと言える日本」とかいう本がありましたね。確か石原慎太郎とソニーの盛田さんが共同で書いたのですよね。アメリカによる「日本たたき」に業を煮やしてアメリカ追従はやめようという趣旨の本だった。私自身は読んだことありませんが、結構受けていたのではなかったかな。Japan That Can Say Noというタイトルで英文版も出ていたはずです。
で、12月15日付けのフィナンシャル・タイムズ(FT)にこの本のタイトルをもじって A Japan that can say No to Chinaというタイトルの社説が出ていました。小泉首相の靖国参拝に文句を言い続ける中国に対して日本の世論が反発しているという現状について語っています。日本の新聞でも報道されましたが、最近の世論調査では日本人の44%が小泉さんの靖国参拝を支持(反対は38%)、中国の不満に理解を示すのはたったの10%であったそうです。
FTの社説は「中国の態度が日本人を硬化させている」として「中国は自らを追い詰めてもいる」と、現在の日中政治関係が冷え込んでいる(経済関係は緊密の度を増している)背景の一つには中国のごり押し的な態度があり「(小泉の参拝を中止させようとする)中国が望んでいないような結果を招いている」(China's shrill protests about the Yasukuni visits have had the opposite of the intended effect)としている。
|
 |
しかしFTは日本が正しいと言っているのではなく、現状についての責任は日本にもある、とも強調しています。即ち日本が第二次世界大戦中に行った行為について近隣諸国に対して「ドイツのように正直に認めていない」(Japan
differs from Germany in failing honestly to admit the extent of the horrors
it inflicted on its neighbours more than 60 years ago)というわけです。 FTは日本がアジアで中国に対抗できる唯一の大国であるにもかかわらず、外交の力を発揮することが出来ないでいる。日本が経済力(と軍事力)に見合った影響力を発揮するためには(つまり中国に対してノーと言えるためには)「中国、韓国、アジアの近隣諸国、アメリカや英国の退役軍人たちが何故、靖国を巡って怒りを感ずるのかについて、日本が理解しなければならない」と結論しています。英文では次ようになっている。
- But until Mr Koizumi and other Japanese leaders can understand what it
is about Yasukuni that angers Chinese, Koreans and other Asians - not to
mention British and American veterans-there is little chance that Japan
will wield the diplomatic influence it craves to match its economic might
and re-emergent military strength.
靖国参拝というといつも中国や韓国の不満が報道されますが、アメリカ人や英国人はどのように考えているのでしょうか?FTの社説に見る限り、少なくとも兵士であった人達は快く思ってはいない。おそらく他の人たちは興味もないということでしょうね。しかし小泉さんを"He is a good man"と言っていたブッシュさんやブレアさんはどう思っているのか・・・気になります。小泉さんもこのあたりは気にした方がいいと思います。 |
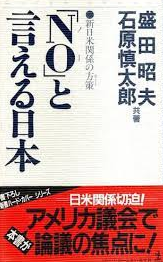 |
|
| back to top |
5)どうでも英和辞書
|

scrabbling: かき回す |
"Scrabble" といえばアルファベットの駒を並べて単語を作り、得点を競うボードゲームのことですよね。英国の辞書の説明によると、動詞としての"Scrabble"
には二つの意味があるらしい。
- to use your fingers to quickly find something that you cannot see: 指を使って何かを見つけ出そうとする。
例えば "He was scrabbling in the sand searching for the ring." は「砂の中に埋まっている指輪を見つけ出そうとする」ということ。
- to try to get something quickly that is not easily available: 入手が困難なものを素早く手に入れようとする。
例文として "The government is scrabbling around for ways to raise revenue without putting up taxes" というのがあった。「政府が増税抜きで収入をあげようとする」ということ。へ~、あのゲームとはちょっと違うなぁ!
もう一つ、BBCによると
- Trump has blown up the world order - and left Europe's leaders scrabbling
だそうです。 |
 |
back to top |
6)むささびの鳴き声
|
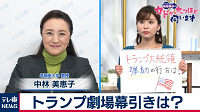
|
▼3月30日付の週刊エコノミストのサイトに早稲田大学の中林美恵子教授とのインタビューが掲載されています。『良識的な共和党員からの悲鳴・諦観「トランプのやりたい放題にさせろ」』というタイトルで、現代アメリカのトランプ政権について語っています。
- 毎日世界がびっくりするような政策を打ち出して、今までのルールや秩序を変えようとしている。それをまた有権者が支持する。
▼というわけですが、教授によると、先の選挙で民主党のカマラ・ハリスがトランプに敗れたのは「バイデン前政権の推進した政策がかなりリベラル寄り」で
- 何よりも大きかったのは経済、インフレが人々の生活を直撃したことだ。特に本当にギリギリの生活を余儀なくされている低所得者層に大きなダメージとなった。
▼あの選挙を数字的に振り返って見ると、選挙人の総数はトランプが312人でハリスが226人…確かにトランプの圧勝かもしれないけれど、国民的な意識を示す数字を見ると、トランプが7701万5439票(49.9%)でハリスは7463万9673票(48.4%)というわけで、民主党がそれほど嫌われていたとは(むささびには)思えない。ただ…これらの数字も州ごとの勝敗をみると、確かに共和党の圧勝に見える。でもあの頃のアメリカの有権者がそれほど民主党政権を忌み嫌っていたのか?となると…ちょっと疑問ではある。
▼中林教授の発言の中で、むささびが最も興味を魅かれたのは「予測不能なトランプ政権と日本はどう付き合えばいいか?」という質問に対する答えの部分でした。
- 今の状況をウエークアップコール(警鐘)と受け止めるべきだ。戦後、東西冷戦を経て常に日本は、米国を頼れる位置にいた。日本にとって米国という大事なカードを失うかもしれないというウエークアップコールだ。中国やロシア、北朝鮮と対峙(たいじ)する時、いつも米国が頼りだったが、トランプ政権にはそれが期待できないリスクが高まっている。
▼というわけで、教授が挙げたのはウクライナの現状です。ゼレンスキー vs トランプの口論の結果として、首脳会談は決裂、トランプは「ロシアに有利な条件での停戦や、これまでの支援の見返りにウクライナにある鉱物資源の権益を譲渡するように求めたり」している…というわけで中林教授は
- 日本としては、ウクライナの状況をよく観察し、独自に有効なカードをそろえることが急務だ。
▼と忠告しているわけです。ちなみに中林教授は1960年の生まれです。いわゆる「60年安保」の年です。この年に政治づいた日本の若者は多いと思います。むささびもその一人です。下に掲載した写真は1960年に国会周辺の日米安保条約に反対するデモに参加して死亡した女学生です。 |
 |
|

←前の号 次の号→ |

