1)H.G. Wellsと日本
|
 |
H.G. Wellsという英国の作家はTime MachineのようなSF小説で知られているようですが、私が読んだのは彼の書いたA Short
History of the Worldです。日本語訳が出ているのかどうか分からないのですが、人類の誕生から20世紀ごろまでを解説した世界史の本です。最近、理由があってこの本をもう一度読む機会があったのですが、学者の書いたものと違い、楽しみながら読めるエンターテイメント性が豊富で、歴史というものが案外面白いものなのだということを分からせてくれる本であるように思いました。英語もかなり平易で、本の書き出しは次の文章で始まっています。
The story of our world is a story that is still very imperfectly known.
我々が住むこの世界の物語は未だに極めて不完全にしか分かっていない。 |
H.G. Wellsは1866年生まれで第二次大戦直後の1946年に亡くなっています。小説家であり、評論家であり、ジャーナリストであり、歴史家でもあり・・・という著述の分野のスーパーマンのような存在です。A Short History of the Worldの中で私が最も興味を持ったのは19世紀終わりから20世紀の始まりの時代を解説したEuropean Aggression in Asia, and the Rise of Japan(ヨーロッパのアジア侵略と日本の台頭)という部分だった。1868年の明治維新から約30年たったころのアジアはドイツ、英国、ロシアというヨーロッパの帝国が中国各地を手中に収める帝国主義争いのような状態であったのですが、「そこへ新たなパワーがこの大国の覇権争い参加することになる。それが日本である」(now a new Power appeared in the struggle of the Great Powers, Japan)というわけです。
Wellsは欧米によって無理やり開国させられ、大いなる屈辱感を味わっていた日本が明治維新以後いかに変身したかについて次のように書いています。
In 1866 she was a medieval people, a fantastic caricature of the extremest romantic feudalism; in 1899 hers was a completely Westernized people, on a level with the most advanced European Powers. She completely dispelled the persuasion that Asia was in some irrevocable way hopelessly behind Europe. She made all European progress seem sluggish by comparison.
1866年の日本は中世の人々で、極端にロマンチックな封建主義の戯画のような存在であった。それが33年後の1899年には完全に西洋化していた。それも最も進んだヨーロッパの大国のレベルにまで西洋化していたのである。日本はアジアがヨーロッパからは全く遅れをとっているというイメージを完全に払拭した。日本に比べればヨーロッパにおける進歩でさえもダラダラしたものにうつるくらいであったのだ。 |
帝国主義国によるアジアでの覇権争いへの日本の参加の象徴ともいえるのが日清戦争(1894~95年)ですが、Wellsによると、それまでの日本ときたら人類に対する貢献めいたものはほとんどなにもなし、「取るだけで与えることはほとんどしない」(she has received much, but she has given little)という国だった。日清戦争から間もなくして英国と日本は同盟関係に入り(日英同盟・1902年)、日本は日露戦争(1904年)でロシアを破る。
▼私がとても面白いと思うのは、A Short History of the Worldという本が出たのが1922年であるということです。H.G.
Wellsは56才だったわけですが、日英同盟締結から20年後のことです。言うまでもなくH.G. Wellsはいわゆるジャパノロジスト(日本びいき)でも何でもありません。つまりここに書かれている記述が、そのころの普通の英国人が持つ日本についてのイメージであったのかもしれないということです。
▼ところでインターネットというのは驚異的なものですね。H.G. Wellsのこの本がそのままネットに出ているのですから。ここをクリックすると出ています。
|
|
back to top
|
2)部族社会、ニッポン
 |
The Economistには普通のニュースではなく雑誌としての考え方のようなものを書くコラムのページがいくつかあります。アジアのセクションにもそれがあって、ときたま日本が話題になることがある。最近号(12月3日)もその一つでTribal Japanというタイトルのエッセイが掲載されています。Tribalというのは部族的という意味だからこのエッセイは日本の社会にある部族社会的な要素について語っているものであります。
いろいろと例が挙がっています。オリンパスの問題で、前社長のMichael Woodford氏が社内で損失隠しの問題を取り上げて菊川社長に挑戦する中で、森久という取締役に向かって「森さん、あんたは誰のために仕事をしているのですか?(Mr Mori, who do you work for?)」と聞いたことがある。Woodfordとしては当然「会社のためだよ」という返事が返ってくるものと思っていたのですが、森さんの答えは "I work for Mr Kikukawa. I’m loyal to Mr Kikukawa"というものだった。「菊川さんのために働いているのだ。自分は菊川氏に忠実なのだよ」というわけですね。Woodfordはこの答えを聞いたときが「最もぞっとした瞬間の一つだった(one of the most chilling moments)」と言っている。部族社会的日本の一面であるとThe Economistのコラムは言っています。
オリンパスの例が個人的な忠誠心という意味で部族的であるとするならば、外部の意見を疑ってかかる(a general suspicion in Japan of outsiders’ points of view)というのも日本的な部族社会の特徴であり、その例が東電なのだそうです。2009年に行われた東電と経産省の間の会議メモによると、東電の原発にまつわる危険性について外部の科学者による指摘があったにもかかわらずこれが無視(dismiss)されたことがあるそうですね。東電の取締役20人のうち18人が東電内部からの人だそうで、東電や経産省から独立した原子力の専門家、外国人、女性などが加わっていたら事態は異なっていたかもしれない、というわけです。
政治の世界の部族性は、政策よりも派閥のボスに忠実であろうとする政治家によって保たれているとのことなのですが、The Economistによると、メディアの世界も部族社会だそうであります。例えば政治メディアの場合、ベテラン記者は党内の派閥争いの取材をやり、ちょっと難しい政策がらみの取材は若手の記者がやる。つまり政策よりも派閥という部族の動きの方を伝える方が重要だと思われているってことですよね。さらにオリンパス事件と経済メディアについては
Financial journalists quietly acknowledge that one reason they buried Mr Woodford’s claims on the inside pages early in the Olympus scandal is that the story was broken by an obscure monthly magazine. Worse, Mr Woodford first spoke to the Financial Times, not the Nikkei Shimbun.
オリンパス事件の初期の頃にWoodfordの言っていることが一面以外のページで埋もれてしまうような扱いを受けたのはそのニュースそのものが「名もない月刊誌」(obscure monthly magazine)の特ダネ報道を発端にしていたからだということは経済記者たちが暗黙のうちに認めている。しかも、あろうことか、Woodford氏が最初に話をしたのがFinancial Timesであって日本経済新聞ではなかったということだ。 |
と言っています。
そのような日本社会の部族的性格も政治の世界では少しずつ弱くなってきているかもしれない、とThe
Economistは言っており、その例としてTPP参加を推進しようとしている野田さんの姿勢と大阪の選挙で勝ってしまった橋下さんの例を挙げています。しかし
But in the tradition-bound, loyalty-bound business world, there is as yet little such clamour for change, from employees or shareholders, however much Mr Woodford has rattled their cages.
伝統に縛られ、忠誠心に縛られているビジネスの世界では変革を求める声は従業員からも株主からもほとんど聞こえてこない。Woodford氏がどんなにカゴを揺すってみても、である。 |
とのことであります。
▼オリンパス・スキャンダルについては、The Economistが書いているようなことはこれまでにも日本のメディアで報道されていると思います。この記事のイントロは次のようになっています。
Japan’s cherished loyalty system is part of the problem
日本が大事にしている忠義の慣習こそが問題の一部なのだ。 |
▼忠義とか忠誠心というのは悪いものではないけれど、自分の価値基準のようなものを喪失した上での忠義では困る・・・と言う人がいるかもしれない。ただ忠義というのはそもそも「自分」を捨てることが前提になっているのですよね。会社ではなく自分の上役に忠義を尽くしていると言うオリンパスの幹部のアタマでは、上役に尽くすことが会社に尽くすことになるという図式が成立していたのでしょうか?何やらやくざの世界という気がしないでもない。I’m loyal to Mr Kikukawaという日本人同僚の言葉を聞いて「最もぞっとした瞬間だった」というWoodfordの気持ち、分かりますね、私には。
▼いまから30年ほど前の1980年代、日本では「経済は一流、政治は三流」と言われていましたよね。大体においてこの種の言葉はメディアを通じて市民権を得ます。東電、オリンパス、大王製紙などにまつわる諸々を見ていると、経済が一流というのはジョークでしかないと思います。しかし「政治は三流」というのは本当でしょうか?ひょっとするとThe Economistのいわゆるベテラン政治記者たちが自分たちの存在を世の中に見せつけたくて「政治家はアホ」というラベルを貼りまくった結果、政治家がアホのように見えるようになってしまったってことなのでは?政治家というのは、選挙で選ばれた人たちです。その政治家をアホ呼ばわりするということは選んだ人たちをアホ呼ばわりしているのと同じです。
▼日本の政治ジャーナリズムについて、ベテラン記者は派閥取材を、若手は政策取材をするとThe Economistのコラムは言っている。かつてコロンビア大学のジェラルド・カーティス教授が言っていたことを思い出します。日本の政治記者が「ウチのおやじ」と言っていたのを聞いて、誰のことかと思ったら、その記者が取材対象にしている政治家のことだったというわけで、日本では政治家と記者が親しすぎると批判していた。日本記者クラブでの会見だったのですが、教授の発言はここをクリックすると読むことができます。 |
|
| back to top |
|
3)イラン人は英国を超大国だと思っている
|
 |
日本でも報道されているとおり、11月29日にイランのテヘランにある英国大使館が襲撃されたことへの報復措置として、英国政府が30日にロンドンにあるイラン大使館の閉鎖とイラン外交官の国外退去を命令しました。英国政府はテヘランにある英国大使館も閉鎖、英国の外交官を国外退去させています。つまり双方の大使館が閉鎖されるという異常事態に陥っているのですが、ヘイグ英国外相によると、イランと英国の関係は「最悪ではあるが、完全な国交断絶というわけではない」(relations between the UK and Iran were now at their lowest level, but the UK was not severing relations with Tehran entirely)とのことであります。
BBCの国際ジャーナリスト、John Simpsonは今回のイランと英国の間のトラブルについてBBCのサイトで
Hard though it is for the British to understand, in Iran they are seen as a superpower which has intervened decisively in their affairs time and again over the past two centuries.
英国人には理解しがたいかもしれないが、イランでは英国が過去200年にわたってイランの国内問題に何だかんだと干渉してくる大国(スーパーパワー)であると思われているのだ。 |
とコメントしています。
例えば1906年から1911年にかけてイラン国内で民主的な憲法を作ろうという動きがあったときに、これを軍事力で潰しにかかったロシアを英国が援助したということがある。また1925年にReza
Pahlaviがイランの国王になるように仕向けておきながら41年には彼がナチに同情的だという理由で追放、彼の息子を王位につけた。これも英国のやったこと。このような経験があって、1979年にイスラム革命が起こってパーレビ国王が追放されたときには国王側と革命勢力の双方から英国が敵の背後にいると疑われることになった。
英国人にしてみれば、このような出来事は霧の彼方の歴史(ancient history)にすぎないのですが・・・
But Iranians have not forgotten, and they are much less aware of the changes in the outside world. Many Iranians still credit Britain with pulling the strings behind the scenes, and believe that the British tell the Americans what to do.
しかしイラン人は忘れていない。イラン国民は外部で起こっていることがそれほど分かっていない。多くのイラン人が現在でも背後で操っているのは英国であり、英国こそがアメリカを指図している国であると信じているのだ。 |
とSimpsonは言っている。
Simpsonによると、テヘランの英国大使館襲撃も含めて今回の出来事は全てイラン国内の政治闘争であり、極右勢力が背後で動いているけれど、彼らは最近もっぱらアリ・ハメイニ最高指導者を自分たちの指導者と見なしている。英国との国交断絶の「真の敗者」はアフマディネジャド大統領なのだそうです。大統領は言うことは過激でも実際には西側との接触を維持することを望んでいるというわけです。
つまりアフマディネジャドvs極右勢力(ハメイニ師を巻き込んでいるかもしれない)の争いであるわけですが、大統領は大衆が望んでいるものを嗅ぎつける本能的な感覚を有しており、いずれは何らかの形で自分の政敵に報復行動を起こすであろう(We can expect him to find some way to hit back at his political enemies)というのがSimpsonの見方であります。
| ▼20世紀初頭の1906年から1911年におけるイラン国内の民主化運動をロシアが潰し、それを後押ししたのが英国であったとのことですが、1902年に日英同盟が締結され、1904年~1905年には日露戦争があった。英国は日本と一緒になってロシアと戦ったわけではないけれど、ロシアを破った日本の海軍が使った装備はほとんどが英国からの輸入品であったそうですね。 |
|
back to top
|
4)製造業のジャイアンツがいない
|
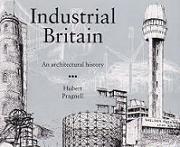 |
最近の英国メディアが頻繁に伝えるようになった話題の一つに製造業の復活ということがあります。復活したという意味ではなく、英国経済のバランスのために製造業を振興する必要があるということです。最近の例が11月26日付のThe Economistに出ていたReviving manufacturingという記事です。製造業の復活が大切であることは確かではあるけれど「英国の製造産業に大企業が足りないということが、製造業振興の足かせになっている」(A lack of big companies hampers efforts to boost manufacturing)と言っています。
いまから30年前、1980年代の初期、英国では約600万人の人々が製造業で働いており、英国にはBritish Leyland、GEC、ICIと言った世界に冠たる「メーカー」が存在していたものです。それらの多くが潰れるか、外国企業に買収されるかしてしまい英国経済の牽引役は金融業を中心とするサービス産業に移ってしまった。製造業による雇用者数は600万が250万へと激減、GDPに占める製造業の割合も、かつての25%が11%にまで落ち込んでしまったわけです。
ただ英国生まれの製造企業は少なくなったかもしれないけれど、モノづくりという活動そのものが衰えたわけではない。その例としてThe Economistが挙げているのが自動車産業で、「ニッサン、ホンダ、トヨタが英国に開いた自動車工場によって英国の自動車生産は年間150万台で、このうち5分の4はヨーロッパ大陸向けに輸出され、英国の自動車産業は生産効率の点でヨーロッパの先導的な国となっている。
そうは言っても「巨大企業」(giants)と呼ばれるような製造業が少ないことは工業国としての英国というイメージが弱いというハンディはある。現在の英国で世界的に有名な製造企業は航空機エンジンのRolls-Royceと防衛機器のBAE
Systems(EUが日本に売り込んでいるユーロファイター戦闘機の開発の中心となっている)くらいのもので「英国生まれ・英国育ち」のジャイアンツがいない。
製造業の場合、ジャイアンツが存在するとそれに付随する関連企業が育つわけですが、The Economistはドイツを例に挙げて、BMW、Siemens、Daimler、Volkswagenのような大企業に部品を提供する中小企業(Mittelstand companies)が数多く存在しており、ドイツでは従業員250人以上という企業の数が英国の2倍、アメリカでも製造産業が雇用創出の点で英国よりも重要な役割を担っているとしています。
かつてはそれなりにジャイアンツが存在した英国の製造産業ですが、サッチャーの保守党政権が推進した外国からの投資誘致によって英国企業が買収されたり、外国企業が工場進出したりする中で消えてしまった。JaguarやLand
Roverと言えばかつては英国を代表する自動車メーカーだったけれど現在はインド企業のTataの傘下に入っている。これが大いに業績好調で、英国内に新しい工場を作ることを発表するまでに至っている。
Jaguar Land Roverの場合、部品を供給する企業が2000社に上っており、売上も年間40億ポンドにのぼっているのですが、自前のジャイアンツがいない英国の生命線は外国の製造企業に対する開放的な投資誘致政策です。そのような英国がはらはらしながら見守っているのがユーロ圏の危機的状況です。外国企業が英国に工場を作るのも、ヨーロッパ大陸という大きな市場に輸出できるというメリットがあるからです。
Yet with the euro under unbearable strain, the European Union in danger of succumbing to protectionism and Britain increasingly sidelined, the country looks less like a springboard to a vibrant market and more like an island.
ユーロが危機的な状況に置かれ、EUが保護主義に陥る危険性をはらみ、英国がますます脇に押しやられるようなことになると、この国は活気に満ちた市場への跳躍台というよりも単なる島に見えてきてしまう。 |
とThe Economistは言っています。
▼The Economistという雑誌は自由貿易・開放経済こそが人類を幸福にすると考えているので、サッチャーさんが英国を開放して外国企業を受け入れる政策を推進したことを大いに支持しています。その過程において地元・英国の産業が潰れたとしても、英国に工場を作った外国企業は「英国企業」なのであり、彼らが英国人を雇用するのであれば同じことではないかというわけですね。というわけで1980年代にたくさんの日本の製造企業が英国に工場を作って雇用を生み出したのですが、今ではそれらの日本企業の多くが賃金が安くて、EUへの輸出も容易な東欧諸国に移ってしまったと言われています。つまり自由貿易・開放経済を進めるということは、そのような浮き沈みをも引き受けるということでもあるのですよね。
|
|
back to top
|
5)英国の製造業:弱さの原因
|
 |
The Economistの記事とは別に総合誌The Prospectの9月21日付サイトに掲載されていたCan Britain make it?という見出しの記事も、いまの英国経済を立て直すためには製造業の復活が必要だと訴えています。かなり長い記事で、ここをクリックすると読むことができますが、筆者(Warick大学のRichard Lambert教授)のメッセージは次の文章に代表されています。
Manufacturing can play a big part in reviving the economy but it has been handicapped by short-termism from investors -- and ministers
製造業は(英国の)経済復興に大きな役割を果たし得るが、投資家と政治家の短期的なものの見方によってハンディキャップを負わされている。 |
いわゆる市場経済主義をベースにするサッチャー、メージャーの保守党政権の経済政策をほぼそのまま引き継いだブレアの労働党政権が生まれたのが1997年。それから2008年のリーマン・ショックまでの約10年間、英国経済は大いに盛り上がっており、人々の生活も目に見えて向上していた。その英国経済を支えていたのが、政府による公共投資、旺盛な消費、そして金融業界の長続きするはずのない拡大(unsustainable expansion)だった。お陰で国も借金が増えて緊縮政策をとらざるを得なくなっているのですが、これからの金融業界は縮みこそすれ拡大が望めず、英国は製造業の復興によってバランスのとれた経済に戻らなければならない(とRichard Lambertは言っている)。
ただLambert教授によると、製造業が復活するためには乗り越えなければならない課題が二つある。一つは英国の経済を支配してきたかのように見える短期的な利益追求主義であり、もう一つは産業政策の不在ということです。
短期的な利益追求主義についてですが、一つの例としてセメント、コンクリート、タイル、屋根材、石膏ボードなどの建設資材メーカーでBlue CircleとRedlandという大手2社は英国に本社を置いて世界中に製品を輸出していた。それがいずれもフランス、スイス、メキシコなどの会社に買収されてしまった。なぜそうなるのか?理由はこの業界が大きな資本を必要とすることにある。セメント製造のキルンを作るのには巨額の経費がかかるのだそうですが、英国の経営者には早く利益をあげることが求められており、長期的な視野に立った投資が行われない。短い期間にもうけが出ればそれで良しとしてしまって、その後のことは考えない。つまり建材生産のような業種は英国には合わないということになる。
それに対して外国の買収企業は投資を増やして生産性を上げビジネスを成功させようとする。英国の製造業における投資はGDP比で16.8%ですが、フランスは21.9%、中国に至っては41.1%もある。また英国の製造業における研究開発の資金の25%が外国からのものであり、この比率はドイツの5倍以上になるのだそうです。
英国の製造業にとってのもう一つの問題として、Lambert教授は政府レベルでの産業政策というものが存在しないことを挙げています。これにはサッチャー以後の30年間、「政府による産業の現場への介入は経済にとってダメージを生む(any intervention by government in the workings of the economy is likely to be damaging)]という考え方が支配的であったことが背景として挙げられる。
サッチャー流の自由経済にはそれなりの利点はあった。自由で開放的な経済体制のお陰で外国企業による直接投資が大幅に増え、英国企業が倒産しても外国企業が雇用を生むことで表面的には問題が
ないように見えた。が、そのやり方には問題もあった。市場に任せればすべてオーケーというわけで、市場そのものがうまく稼働しないという事態もあることが無視されてきた(Market failures have been ignored)。
また英国の製造業の強みについて、政府レベルでマジメに考えることがなかったということです。産業関連のお役所はしょっちゅう再編されたりして、一貫性のある産業政策が作られることがなかった。Lambert教授は政策面での産業無視の例として、産業にとって最も大切な分野であるエネルギーが経済ではなく環境関係のお役所の仕事になっていることを挙げています。
Lambert教授は、製造業が英国経済全体に占める割合は減ったが、それは社会が豊かになるとどこでも起こることであるとしています。また英国の製造業がGDPに占める製造業の割合はざっと11%で、ドイツや日本ほどではないがアメリカやフランスと同じ程度であり、製造業が盛んな国のトップ10の一つにはなっている、と指摘しています。しかも英国には自動車、航空宇宙、薬品、生命科学などの分野で世界をリードするような企業が数多く存在している。さらに英国では2020年までに原発建設や海上風力発電施設の建設など発電産業には1000億ポンドが費やされることになっており、これらが関連の製造産業の活性化に繋がる可能性もあると言っています。
To restore the balance and get back to stable growth, the country needs to shift away from the consumption of goods and services and towards activities that can help us create wealth and pay our way in the world. That of necessity means a greater emphasis on private-sector investment and trade, and since manufacturing accounts for more than three-fifths of British exports and a big chunk of private investment, its role becomes pivotal.
経済的なバランスを回復し安定した経済成長を取り戻すために英国が必要としているのは、モノやサービスの消費を離れて富を生み出す活動へ向かうことによって、この世界で自力で道を切り開くことであり、そのためには民間部門での投資と貿易に力を入れることである。英国の輸出のうち5分の3は製造産業によっており、この産業の役割がこれから極めて重要になる。 |
とLambert教授は言っています。
▼この記事の中でイチバン興味深いのは、英国において過去30年間、金科玉条のように言われてきた「政府による産業への介入は産業にとってダメージになる」という考え方(小さな政府至上主義)に対する反省のようなことが書かれているということです。1980年代の世界では全く正しかった政策が30年後に見直されているということで、時代が変わりつつあるということですよね。
▼私は未だ読んでいないのですが、BBCの経済記者であるEvan Davisという人が書いたMade in Britainという本が話題を呼んでいるそうです。英国の製造業のことを書いたものなのですが、Davisによると「消費が余りにも盛んすぎる国では製造産業が小さくなる傾向がある」(countries that consume too much tend to have a smaller manufacturing sector than they otherwise would)のだそうです。社会的な風潮としてお金を貯めるよりも使う方が奨励されるような国では、企業も将来のために貯蓄や投資をという考え方をしなくなる。サービス産業はそれでもいいかもしれないけれど、製造業のよう元手がかかる業界にとっては消費第一主義は合わないということです。 |
|
6)どうでも英和辞書
|
| A-Zの総合索引はこちら |
off the record:オフレコ
 本来はメディア用語なのに普通の会話にも使われるようになってしまったのがoff the recordですね。念のために説明させてもらうと、政治家や役人やビジネスマンのような人たちがマスメディアの記者と話をするとき自分の言うことは記事にしないで欲しいということを予め断ったうえで記者と話をすることがある。これがoff
the recordです。 本来はメディア用語なのに普通の会話にも使われるようになってしまったのがoff the recordですね。念のために説明させてもらうと、政治家や役人やビジネスマンのような人たちがマスメディアの記者と話をするとき自分の言うことは記事にしないで欲しいということを予め断ったうえで記者と話をすることがある。これがoff
the recordです。
防衛庁の何とかいうお役人が沖縄のことで暴言を吐いたというので更迭され、ひょっとすると大臣もクビになるかもしれないと言われています。この「暴言」は担当記者たちとの「オフレコ懇談会」で行われたのですよね。NHKのニュースによると、この懇談会はオフレコを前提に行われたけれど、「犯す前に・・・」という発言が余りにもひどいので、どこかのメディアが報道してしまったのだとか。この懇談会はそもそもどちらが持ちかけたのでしたっけ?メディア側ですか、防衛庁側ですか?いずれにしても、このお役人にはoff
the recordについては、アメリカの国防長官だったドナルド・ラムズフェルドの
| With the press there is no "off the record". |
という言葉を教えてあげるべきだった。オフレコの約束などメディアが守るはずがないと思った方がいいということです。
やっかいなのは、on the record(オンレコ)という了解で会話を始めたのに会話中に舌が滑って言わずもがなのことを言ってしまったような場合です。オバマ大統領が上院議員であったころに外交政策顧問を務め、2008年に大統領選挙チームにも名を連ねたSamantha
Powerがスコットランドの新聞、Scotsmanの記者とインタビューをする中で、オバマの対立候補であったヒラリー・クリントンについて
"[Hillary Clinton] is a monster, too - that is off the record"
ヒラリー・クリントンも怪物みたいだわ。いまのはオフレコだけど・・・。 |
と発言、これが報道されてしまい、結局オバマの選挙チームから離れざるを得なかったということがあります。Scotsmanの記者はこのコメントを掲載したことについて
Unless a deal has been struck in advance that the interview is off the record, I believe any journalist worth their ink should run the story.
あらかじめこのインタビューにはオフレコの約束があったわけではない。だとしたら新聞記者なら書くのが当たり前だ。 |
と言っているのですが、アメリカのメディア関係者の間ではスコットランド記者の評判はきわめて悪く、テレビのキャスターなどは「英国のジャーナリズムの水準はアメリカに比べるとかなり低い」とコメントしたりしていたのだそうです。
更迭された防衛庁のお役人の件ですが、「犯される前に・・・」という発言は、彼なりに「うまい冗談」のつもりだったのですよね。きっと普段からメディアの記者たちに「局長は冗談がお上手だから・・・まいっちゃうなぁ」とか言われてにやにやしているような間柄であったのかも?
off the recordを別の言葉でいうと「ここだけのハナシだけどさ」ということになる。これは必ずしも悪い慣習ではないですよね。例えば何かの組織の内部告発者が秘密を明かしたいけれど、今の時点では未だ記事として報道してもらいたくないと思っていて、それが理にかなった理由であるような場合、オフレコは許されますよね。でも政治家やお役人とメディアの間の「ここだけのハナシ」は「癒着」という感じがしていい気がしない。なぜなんですかね?
|
back to top
|
7)むささびの鳴き声
|
▼ちょっと古い話題で、大阪のダブル選挙ですが、府知事選挙の方は勝った松井さんが200万、次点の倉田さんが120万票だから確かに「圧勝」ですよね。でも市長選挙の方は勝った橋下さんが75万、負けた平松さんが52万だからおよそ6:4です。これで「圧勝」なのでしょうか?橋下さんに投票した75万人の感覚が東京新聞の社説が言うように「既成政党不信の帰結」なのだとすると、平松さんに入れた52万の人々の想いは何であったのでしょうか?
▼この選挙では大阪が大いに盛り上がっていたとのことですが、関東にいる私には直接分からない。でもおよその察しがつくのは、「維新」を訴えた橋下さんがテレビなどでほとんど英雄扱いされたのに対して、平松さんについては「維新の邪魔をするさえないおっさん」のようなイメージで扱われてしまったということです。古くさくて破壊するっきゃない大阪を守ろうとしている悪者ということです。そのような雰囲気の中で橋下さんに投票した75万人、それでも平松さんに入れた52万人のどちらが一票を大切にする意識が高かったのか?
▼前回のむささびジャーナルでフィンランドにおける右翼政党の躍進について書きました。なぜいま右翼なのか、この際フィンランド人に聞いてみたいと思っていたら、その機会が意外にはやくやってきた。11月30日に日本記者クラブでフィンランドの大臣が記者会見をやったので、そこに参加させてもらったわけであります。Jyri
Hakamies(ユリ・ハカミエス)経済産業大臣とAlexander Stubb(アレクサンデル・ストゥブ)欧州・貿易大臣の二人による会見でした。
▼「(右翼政党の躍進が意味するのは)フィンランド全体が右寄りになっているということか?」という私の質問にストゥブ大臣が「政治には変化が必要だ」として、あの「右翼」政党の台頭もフィンランドの政治に「新鮮な空気」(fresh air)を吹き込むことになっているので「むしろ歓迎だ」というようなことを言っていた。大臣はさらに「あなたは右翼政党という言葉を使ったけれど、厳密に言うとそれは違う。いまはもう右翼・左翼という時代ではなく、ローカルかグローバルかという選択の時代になっている。自分はフィンランドがグローバルで開かれた国であるべきだと考えている」と言っていた。
▼なるほど・・・。True Finnsという政党をFar Right(極右)と表現したのは英米のメディアであって、私はそれを無自覚に繰り返したに過ぎないわけです。フィンランド語ではどのように表現されているのか分からないのですが、この政党はフィンランドがグローバリゼーション(国際化)の波に乗っていることに反発しているのであって、排他的にフィンランドが世界一だと言っているのではないわけですよね。英国でもBritish National Party(BNP)という愛国主義政党があって、ちょっとしたブームであったのですが、結局昨年の選挙ではひとりも当選者を出さなかった。
▼フィンランドの大臣の「むしろ歓迎」発言がどの程度本当の気持ちなのか分からないけれど、英国内でBNPに対して示される政界全体の拒否反応のようなものはフィンランドにはないのかもしれない。True Finnsという政党は少なくとも5議席を有する政党ではあったわけですからね。BNPはTrue Finnsよりもナショナリズム(つまり右翼)色が強いと思います。
▼フィンランドのローカリズム政党ブームと大阪のハシズムブームに共通している(とむささびが感じる)のは「シロクロをはっきりさせないコンセンサス政治」に対する拒否反応であります。サッチャリズムも同じであったわけですが、むささびの独断によるとフィンランドのTrue Finnsリーダーとサッチャーにあってハシズムにないものがある。それは宗教色です。True Finnsリーダーがカソリックでサッチャーはメソジスト。両方ともその国におけるキリスト教としては少数派です。橋下さんには何かの宗教意識はあるのでしょうか?
▼なお日本記者クラブでの会見でハカミエス経済産業大臣が、フィンランドにおける原発建設について発言しました。彼によると現在フィンランドには4つの原発があり、5基目が建設中で、6~7基目の建設も決まっているとのことでした。大臣によると、フィンランドは現在のところ発電量の約3割を原発によっているけれど、将来はこれを6割にまで増やす計画だとのことだった。日本から見ると信じられないような楽観論です。
|
back to top
|
|