1)またやってしまったエディンバラ公
|
 |
エリザベス女王の旦那さんであるエディンバラ公が最近、ロンドン郊外のルートンという町の病院における心臓病治療センターの開所式に出席したのですが、その際に病院で仕事をするフィリピン人の看護婦と言葉を交わす中で
- The Philippines must be half empty - you're all here running the NHS.
フィリピンは半分空っぽになっているに違いない。皆さん、全部この国(英国)で病院の仕事をやってるんですから。
と言ったのだそうです。NHSはNational Health Serviceという国民保健制度が運営する病院のことですね。言われた看護婦は笑っていたのだそうですが、これを伝えるBBCのサイトはこれをエディンバラ公による失言の一つというニュアンスで報道しています。確かに聞きようによっては、出稼ぎ労働者が多いフィリピンをバカにしたような発言ではある。
エディンバラ公のgaffe(失言・暴言)についてはかつてむささびジャーナルでも紹介したことがありますよね。1986年に国賓として中国を訪問した際に、中国で勉強する英国人の留学生たちに向かって
- あんまり長い間この国いると目が吊り上るよ。
If you stay here much longer, you'll all be slitty-eyed.
と言ったと思ったら、西インド諸島の一つ、ケイマン諸島を訪問したとき、出迎えた島民たちに向かって
- 皆さん、ほとんど海賊の子孫なのではありませんか?
Aren't most of you descended from pirates?
と話しかけたりした。そうかと思うと、ナイジェリアのオバサンジョ(Obasanjo)大統領が自国の民族衣装を身にまとって現れると
- おやすみ(就寝)の準備がおできになったようですな。
You look like you're ready for bed.
と言ってみたり・・・。いくらなんでも大統領の正装をパジャマにたとえるというのはシャレにならない。
で、今回のフィリピンの看護婦さんとの会話ですが、バッキンガム宮殿のスポークスマンはメディアからの問い合わせに対して「個人的な会話についてのコメントはできない」(We
do not comment on private conversations)と述べたのだそうです。本当はいい加減ウンザリというところかもしれない。
▼この記事の上に載せた写真が、エディンバラ公(右)とフィリピン人の看護婦さんの談笑風景です。確かに看護婦さんは笑っていますが、関係者にじろじろ見られて、エディンバラ公に「フィリピンは空っぽ・・・」などと言われてたら、とりあえず笑うっきゃないですよね。また英国内の看護婦関係の団体によると、英国全体の看護婦数は65万人、うちフィリピンから来た看護婦さんは約1万6000人だそうであります。
▼エディンバラ公の場合、個人的な悪意のようなものはないのではないか?フィリピンという国とかフィリピン人をバカにしてやろうという意図はないのではないかってことです。一種のブラックユーモアとして、自分では面白いと思い込んでいるような部分があるのでは?ちなみにエディンバラ公は今年で91才、訪問を受けた病院によると殿下は自分のことを「世界で一番経験豊かな幕開け係」(the world's most experienced curtain puller)と呼んだうえで「今度からヘリコプターで迎えに来てほしい」と述べたのだそうです。クルマに乗るのが面倒らしいのであります。だったら来なきゃいいのに・・・。 |
|
| back to top |
2)ローマ法王辞任発表の現場
|
 |
むささびジャーナルは2週間に一度お送りしています。いつも感じるのですが、その2週間の間に実にいろいろな出来事が起こるので、前号をお送りした直後の出来事がはるか昔の出来事であるかのように思えてしまいます。今回の典型的な例はローマ法王ベネディクト16世が2月28日をもって辞任することを発表したというニュースですね。
ごく限られた範囲で日本のメディアのサイトを見ると、ローマ法王辞任発表のニュースはそれぞれ2月11日の次のような時間に掲載していました。
- 日本経済新聞:20時21分
毎日新聞:20時27分、
NHK:20時46分
共同通信:21時49分
産経と朝日は検索できず、読売はなぜかぐっと遅れて翌日(2月12日)の11時01分となっていました。私の見方が悪かった可能性もあるので、間違っていたら謝るしかないのですが、ちょっと興味深いと思うのは、2月11日付のHuffington Postのサイトによると、辞任発表の際にバチカンのプレスルームに居わせた記者の中に日本人がいたのだそうですね。
この記事を書いたGiacomo Talignaniという記者によると、この日(2月11日)はさしたる行事があるわけではなかったけれど、とりあえず何かネタはないかとプレスルームでぶらぶらしていた記者はフランス人が2人、メキシコ人、イタリア人、そして日本人がそれぞれ一人ずつだった。
その中で法王辞任表明のニュースを世界で最初に伝えたのはイタリアのANSA通信と契約していたGiovanna Chirriというイタリア人女性記者だった。なぜ彼女が最初だったのか?それは居合わせた記者の中で彼女だけがラテン語を理解したからだった。法王は辞任の発表をまずはラテン語で行ったのだそうですね。ANSA通信の特報としてPAPA LASCIA PONTIFICATO DAL 28/2(法王、2月28日に去る)という見出しが世界中に配信されたわけですが、この記者は「記事を発信したあと泣けて泣けて仕方なかった」(I gave the news, then I started crying)と語っています。それにしてもあの場に居合わせた日本の記者は誰だったのでしょうか?
あの発表以来、ローマ法王という存在についてはいろいろ情報が飛び交っておりますが、The Economistによると、存命中に退任するケースは極めてまれではあるけれど、在任期間が非常に短いというのも特徴で、266人のうち半数以上が2週間から5年で任期を終えている(死亡している)。なぜそれほど在任期間が短いのか?就任年齢そのものが高いからです。
1500年~2005年の約500年間におけるローマ法王の就任年齢(平均)は64才、ベネディクト16世は78才だった。でも7年半も法王の仕事を務めたのだから立派。1500年以来の法王を振り返ると、アーバン7世(Urban VII)という人の在任はわずか13日(1590年9月)でこれは最短記録。在任期間の最長記録はピウス9世(Pius IX)の32年(1846年6月16日 - 1878年2月7日)なのだそうです。
▼アメリカのPew Researchという社会問題研究機関のサイトによると、世界のキリスト教人口は約22億、うち51%の11億人がカソリックだそうです。辞任発表のニュースを最初に流した記者が「泣けて泣けて」と言っているけれど、カソリックの世界では超大特ダネであったわけですよね。
▼ローマ法王辞任発表のニュースが流れると、世界中でツイッター情報が飛び交ったのだそうですが、フィンランドのツイッターに(英語で)出ていた次の情報は笑えますね。
-
Latest information indicates that the reason for the Pope's resignation is a poor relationship with his supervisor. No one likes a boss who thinks he is omnipotent.
最新の情報によると、ローマ法王辞任の理由は上司との関係がうまくいかなくなったということらしい。まあ、自分は万能だと思っている上司なんて誰だって嫌いだから。
▼もちろん、この場合の「上司」(supervisor)というのは神のことですよね。フィンランドはルーテル派プロテスタントの国です。
|
|
| back to top |
3)英国大使が見た北朝鮮
|
 |
いまいち得体のしれない国である北朝鮮について、かつて(2006年~2008年)平壌駐在の英国大使を務め、現在は国連を中心に外交コンサルタントをやっているJohn
Everardという人が、自分の眼で見た北朝鮮観察記を"Only Beautiful, Please"というタイトルで出版したのをご存知ですか?私は知りませんでしたが、この本の出版記念も兼ねて昨年(2012年)6月にアメリカのブルッキングス研究所とスタンフォード大学が主催してJohn Everardを招いた講演会が開かれました。この人の眼で見た北朝鮮の人々の暮らしぶりについてハナシをするという趣旨で開かれたものですが、ここをクリックすると講演録が文字で読める。さらに講演会で使われたパワーポイントの写真がここをクリックすると見ることができます。
元大使のハナシもさることながら、講演録に入っている「質疑応答」の部分が非常に面白い(と思う)。これも非常に長いものなので、全部を紹介するわけにはいきません。私自身が最も興味深いと思った部分のみ紹介します。それは北朝鮮の人々の対中国観に触れた部分です。
大使によると、北朝鮮では中国人が非常に嫌われており、それにはいくつかの理由がある。一つには自国が中国に依存しているという現実が面白くないということがある。ただ北朝鮮人の中国嫌いはもっと基本的な部分で、人種的嫌悪感(basic racial antipathy)のようなものがあるのだそうで、
- 北朝鮮人は何から何まで中国人が嫌いなのだ。変な臭いがするし、礼儀知らずだし、中国人の食べるものはアメリカの食べものよりもひどいと思っている。
North Koreans do not like Chinese in any form or description. They think they smell funny. They think they’re rude and they think the food they eat is even worse than American food.
さらに北朝鮮人の反中感覚を激しくさせているのが、中国人ビジネスマンの振る舞いである、と大使は言います。数多くの中国人ビジネスマンがさまざまなビジネス目的で北朝鮮に入っているわけですが、特にひどいのは工場を開設して朝鮮人を雇う中国人の態度で、全くゴミ屑扱いするのだそうです。それでも朝鮮人としては出て行けとは言えない。なぜなら中国のお金が必要であり、職場を生んでくれるのも中国人だからです。
John Everardはケンブリッジ大学で中国語を学び、北京大学で経済学を学んでいます。それだけに中国には詳しくて「親しくしている中国人もたくさんいる」(there
are a lot of Chinese I really like)と言っているのですが、その彼によると、北朝鮮でビジネスをする中国人だけは「夕食は一緒に食べたくない」(you
would not want to go to dinner with)類の人たちだそうであります。
では政府レベルで中国はどの程度北朝鮮に対する影響力を有しているのか?John Everardによると、それほどの影響力がないというのが現実なのだそうです。中国の政府関係者が北朝鮮の政府幹部に対するアクセスは有しているのは事実であり、例えば英国大使の眼から見ても平壌駐在の中国大使が金正日総書記に面会する回数はかなりのものがあった。しかしアクセスがあるということと影響力があるということは全く別のことなのだそうです。
また大使によると北朝鮮のエリートたちは、アメリカからの軍事的な脅威は全く感じていない。南の韓国が攻めてくるなどとも考えていない。なぜなら韓国は単なるアメリカの操り人形にすぎず、アメリカが同意しない限り韓国が北朝鮮を攻めるということはない、と考えられている。
ただ何と言っても北朝鮮が望むのは平壌駐在のアメリカ大使館で、これが開設されたら北朝鮮には大変なインパクトになる(tremendous effect
on the country)。但し
- 北朝鮮が望むのは、まともな貢ぎ物の献上者としてのアメリカ人、人民の天国としての(北朝鮮の)優位性を認めるようなアメリカ人が平壌に存在するということである。
one of the great DPRK ambitions is to have Americans in Pyongyang as proper tribute-bearers recognizing the superiority of the People’s Paradise.
ということで、これは当分の間はムリだろうと言っています。
大使はさらに韓国による、いわゆる「太陽政策」(Sunshine Policy)が却って韓国側の「北」への支援を挫かせるものになった側面があるのではないか、と言っている。韓国人にしてみれば、あれほど援助をしたのに「何があったというのか?約束していたはずのソウルにおける首脳会談さえ開かれなかったではないか」というわけで、韓国サイドには苦い思い(quite
a bitter taste)だけが残ってしまった。
大使のハナシには日本と北朝鮮のことについて二つだけ出て来ます。一つはかつて少しは関係が良かった時代に日本から輸入された中古の自転車が今でも立派に活躍していること、もう一つは北朝鮮の人がよく口にすることで、第二次大戦において金日成主席が日本をほとんど片手で(almost singlehandedly)朝鮮半島から追い出したということ。ただ毎年、終戦の季節になるとロシア人が平壌のロシア人兵士の墓に花輪を捧げる儀式をするらしいのですが、その目的はロシアの助けがなかったら北朝鮮が日本に勝つことはなかったはずということを思い起こさせることにある(と大使は言っています)。
最後に、John Everardは北朝鮮が「危機の時代」(periodic crises)にあり、人々が方向感覚を失っている(people are disoriented)として次のように語っています。
- 北朝鮮は多くの意味で、17世紀~18世紀に啓蒙主義にさらされたヨーロッパと似ている。つまり伝統的な宗教がもたらす確かさが疑問に思われ、目の前の事実・現実によって自分たちの信じてきたものを見直さざるを得なくなっているということだ。これは多くの北朝鮮人にとって実に苦痛であると言えるが、同時にまた新しいもののやり方について語ることを受け容れる状態にあるとも言える。
In many ways, North Korea is like Europe at the beginning of the Enlightenment, that traditional religious certainties are being questioned and facts are coming to the fore that are making people reassess what they believe. And this is really quite distressing for a lot of North Koreans. It also means that right now that they will be particularly receptive to talking about new ways of doing things.
▼現代の北朝鮮は既成の権威のようなものへの信仰が揺らいできており、17世紀~18世紀のころのヨーロッパと似ている・・・という大使の観察はとても興味がありますね。最近(2月9日)のThe Economistが北朝鮮特集を掲載しているのですが、その中でも現代の北朝鮮には、かつてに比べると非常に多くの外部からの情報が入ってきており、そうした情報を自分たちの間でシェアすることに北朝鮮の人々が「以前ほどの恐怖感を持たなくなっている」(they are less fearful of sharing that information)と言っている。これ、本当のことかもしれないですね。その一方で、”北朝鮮核実験「反対」、中国各地でデモ”(朝日新聞)というニュースも気になりますね。核実験をめぐる中朝関係については中国情報を詳しく掲載している浅井基文さんのブログも参考になります。
▼英国が北朝鮮との国交を回復したのは2000年のこと。正式な大使館を置いたのは2002年ですが、Everardによると、平壌に大使館を置くについてはロンドンの外務省でもいろいろと意見があったのだそうなのですが、当時の雰囲気が韓国の「太陽政策」に見るように北朝鮮もかなり雪解けムードであったこともあって、開設派の意見が通ってしまったとのことです。初代の英国大使はDavid
Slinnという人、Everardは2代目で現在の大使は5代目でMichael Giffordという人です。
▼John Everardの観察によると、北朝鮮に食糧援助をしている組織としてWorld Food Programmeというのがあり、この組織や韓国から来た食糧援助の場合、大きな袋に組織名や韓国からの援助であるということが分かる大きな文字が入っている。しかし韓国などよりは沢山の食糧を送っているはずの中国の場合はそのような袋を使わないので、それが中国から来たものであることは普通の人には分からない。北朝鮮ではこの大きな袋というのが不足していて、食糧が配布された空き袋がいろいろな場所で使われる。ということはWorld
Food Programmeとか韓国の言葉が常に普通の人々の眼に触れるというわけです。
|
|
back to top
|
4)大きな政府が個人主義を守る(?)北欧のやり方
 |
The Economistの2月2日号が「北欧特集」を掲載しています。スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランドの4か国をまとめて「北欧」(Nordic)と呼んでいるのですが、人口の多い順に並べるとスウェーデン(900万)、デンマーク(560万)、フィンランド(540万)、ノルウェー(500万)となり、合計でざっと2500万人です。またこのうちノルウェーだけがEU加盟国ではない。さらにいうとユーロを使っているのはフィンランドのみです。
その国の生活水準のレベルを表す数字として使われる情報に国民一人当たりのGDP(GDP per capita)というのがありますよね。CIAのサイトには世界228カ国のGDP per capitaのランキングが掲載されています(2012年の数字)。
| 9位 |
ノルウェー |
$ 55,300 |
| 12位 |
アメリカ |
$ 49,800 |
| 22位 |
スウェーデン |
$ 41,700 |
| 26位 |
ドイツ |
$ 39,100 |
| 30位 |
デンマーク |
$ 37,700 |
| 33位 |
英国 |
$ 36,700 |
| 34位 |
フィンランド |
$ 36,500 |
| 36位 |
日本 |
$ 36,200 |
北欧からはギリシャ、スペイン、イタリア、アイルランド(もちろん英国や日本)などが経験している経済的な苦境めいたニュースは聞こえてこないし、アメリカのように銃規制だの人種差別だのと「社会的に病んでいる」(social ills) というハナシもほとんど耳にしない。また英国のように古い部分と新しい部分がせめぎ合っていつも対立状態というのでもなさそうだ。
さらに日本のように自然災害に見舞われて、それが政治・経済・社会のあらゆる面にひび割れを生んでいるということもない。それどころか、日本では北欧というと教育から福祉にいたるまで社会政策のお手本のように言われる。実際、政治の透明度、社会的平等、労働生産性、教育水準や社会福祉・・・どの分野の国際比較でも北欧はトップクラスに位置している。
なぜ北欧ではなにごともうまくいっている(ように見える)のか?なぜ北欧で出来ることが外国(日本も含む)ではできないのか?非の打ちどころがないような北欧システムは、北欧独特の自然環境や歴史(厳しい冬、少ない人口、単一民族性など)が生み出したものであり、他の国がマネしようとしても所詮無理かつ無駄なものなのか・・・などと考えながらThe Economistの特集を読んでいたら次のような文章に行き当たりました。
- 北欧諸国の政府は、地理的・歴史的な条件が組み合わさって二つの強力な「資源」を与えられている。一つは見知らぬ人々に対する信頼・信用の念であり、もう一つは個人の権利に対する信念である。
The combination of geography and history has provided Nordic governments with two powerful resources: trust in strangers and belief in individual rights.
地理的な条件とは過酷な冬ということであり、歴史的な条件とは厳しい自然環境のせいもあって人口が少なく、社会のトップと普通の人々の距離が近いということです。「雲の上の存在」というのがいない。またここでいう「見知らぬ人々」というのは、政府とか統治者のことを言っている(と思う)。つまり「個人の権利への信念」を有した人々が「政府とか統治者に対する信用」も持っているということ・・・?というわけで私が興味を持ってしまったのは、The Economistの特集記事に出ていた次の文章です。
- 北欧の人々はまたキリスト教のプロテスタント主義の教義をしっかり受け入れた。そこでは教会は「手助けをしてくれる仲間」という存在であり、個人とその神の間の直接的な関係が重視される。ルーテル派教会の主なる活動の一つは農民に読み書きを教えることであった。
They also embraced Protestantism - a religion that reduces the church to a helpmate and emphasises the direct relationship between the individual and his God. One of the Lutheran church’s main priorities was teaching peasants to read.
北欧においては(少なくとも昔は)教会が「キリスト教の教えを垂れる」というよりも、読み書きを教えてくれる学校のような極めて身近な存在であったということですが、なぜプロテスタント主義を信奉すると「政府・統治者を信頼・信用」し、「個人の権利への信念」が強まるのか?この部分をキリスト教とは無関係のむささび流に解釈すると、政府・統治者への信頼というのは、「神の下ではみんな平等の知り合い」という感覚であり、個人の権利への信念は、人間には一人一人に「神との関係」という世界があり、そこには他者が入り込むことはないという信念のようなものなのではないか・・・。
英国などに比較すると、北欧諸国では議会に対しても政府に対してもかなり信頼度が高い。例えばロンドンに本部を置くTransparency Internationalという国際組織が毎年発表する政府の腐敗度指数(Corruption Perception Index)の2012年版を見ると、世界176カ国の中のトップ10に北欧4カ国がすべて入っています(日本と英国は17位、アメリカは19位、中国は80位)。さらにEUが加盟国の国民を対象に定期的に行っている意識調査(Eurobarometer:2012)によると、それぞれの国の議会や政府に対する国民からの信頼度について次のような結果が出ています。
特に議会に対する北欧の人々の信頼感が他国に比べるとかなり高いものがある。つまり自分たちが選挙で選んだ政治家に対する信頼感が高いということですよね。また、「信用・信頼」について、10年以上前の1999年、World Values Survey(世界価値観調査)という機関が行ったヨーロッパ人を対象にした調査があります。質問は次のようなものだった。
- 一般的に言ってあなたは殆どの人が信用できると思いますか?それとも人間と付き合うときは気を付けるに越したことはないと思いますか?
Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you can’t be too careful in dealing with people?
それに対して「殆どの人が信用できる」と答えた人の国別のパーセンテージは次の通りです。
ここでも北欧諸国が群を抜いている。さらに面白いと思うのは、The Economistの記事が、北欧の人々の間では「信頼」とか「信用」の対象が血のつながった「家族」というよりも広く「社会」というものになっている傾向が強いと言っていることです。何かと言うと訴訟につながるアメリカ流の社会やイタリア風の「見返り中心の取引」(quid-pro-quo deals)社会でもない。
- 社会が信頼・信用で成り立っているということは、質の高い(信頼性の高い)人間が役人になるということであり、市民は規則に従って税金を払い行動する。そこでは政府が決めることは広く支持される傾向が強い。
Trust means that high-quality people join the civil service. Citizens pay their taxes and play by the rules. Government decisions are widely accepted.
もちろん北欧と言えどもいいことだけではない。The Economistによると、北欧では全労働力の6%が常に病欠、労働年齢人口の9%が障害者手当を受けている。つまり手厚い社会保障のおかげで働かずに生活している人が多いということです。が、なんといっても現代の北欧諸国にとって最大の問題は移民・難民の受け入れです。ある研究機関の数字によると、北欧のような福祉社会を維持していくためには、成人の8割が仕事に就いている(納税者である)必要がある。これにスウェーデンを当てはめると、ネイティブ・スウェーデン人(成人)の就業率が84%であるのに対して、ヨーロッパの外から来てスウェーデンで暮らしている人の場合は51%にまで下がってしまう。
税金で賄われている事業である刑務所の「利用者」についていうと、スウェーデンの場合、服役者全体の26%、刑期が5年以上の服役者の50%が外国人です。また失業者の46%がヨーロッパの外から来た移民・難民であり、非ヨーロッパ人の40%が政府のいわゆる「貧困者」なのだそうです(ネイティブ・スウェーデン人の貧困率は10%)。
というわけで、いま北欧の人々は心の葛藤に揺れている(The biggest battle is within the Nordic mind)のだそうです。すなわち
- 難民たちに門戸を開放することで「進歩的」な社会であるべきなのか、それとも門戸を閉じて難民たちを危険なところに放置した方がいいのか?前者をとると福祉国家としての拡大のし過ぎというリスクを負うことになる。Is
it more progressive to open the door to refugees and risk overextending
the welfare state, or to close the door and leave them to languish in danger
zones?
(難民・移民に多い)熱心なイスラム教徒たちには世俗主義(非宗教主義)的な価値観を強制する方が賢明なのか、それとも「多文化主義」の名の下に自由主義的な価値観を薄める方がいいのか?Is
it more enlightened to impose secular values on devout Muslims or to dilute
liberal values in the name of multiculturalism?
ということであります。そういえば2011年に大量射殺事件を起こしたノルウェーの青年が叫んでいたのは「反イスラム」であったし、イスラム教のモハメッドの風刺漫画が出版されて大騒ぎになったのはデンマークだったですよね。
とはいえ、北欧諸国は他のヨーロッパ諸国に比べれば経済的なトラブルがほとんどないというのも事実。国民が納める税金などは他国に比べると高い。大きな政府で税金が高い国は経済成長が低いというのが経済学者の常識であるはず。この点について、1996年から2006年までスウェーデンの首相であったヨーラン・ペーション(Goran Persson)が、スウェーデンの経済をマルハナバチ(羽が小さい割には体が肥っている)にたとえて「本当なら飛べないはずなのに、飛んでいるのだ」(supposedly it should not be able to fly but it does)と言ったことがあるのだそうですね。
The Economistの記事はこのあたりのことを、政府の「正直さと効率性のなせるわざ」(for the benefits of honesty and efficiency)であり、
- こんにちの北欧は時代に適応するべく戦いながら、かつてよりもさらに上手に飛ぼうとしている。
Today it is fighting fit and flying better than it has done for decades.
と言っています。
▼The Economistが国や地域の特集記事を掲載するときは、記事の対象になる国の長所を描くことが中心であるのが普通です。したがってこの特集企画も「いいことずくめの北欧」という感が否めないのですが、それでも北欧を英国的な視点から検討している点が私(北欧人でも英国人でもない)には興味深い。
▼例えば「社会と家族のどちらを信用しますか?」と聞かれて、あなたならどう答えます?The Economistの記者は、北欧では信用の対象として「家族よりも社会」という傾向があると伝えています。もちろん北欧にだって家族の絆がないわけではないのであろうけれど、福祉の担い手は血縁関係ではなくて社会であるという考え方が自然に受け入れられている、とThe
Economistの記者は感じたのではないかと想像します。
▼「社会」というと思い出すのが、マーガレット・サッチャーの「この世に社会というものはない(There is no such thing as society)」という言葉です。「社会が弱者の面倒を見る」という考え方(福祉国家)に対する批判の言葉ですが、実はこのあとに「個人個人の男や女、それから家族というものがある」(There are individual men and women and there are families)と付け加えたのにその部分は報道されず、サッチャーさんは福祉嫌いの冷たい首相ということになってしまったというわけです。サッチャーとしては弱いものを助けるのは近所同士(community)とか家族同士であるべきだと言いたかったらしい。サッチャーは北欧的ではないということです。 |
|
back to top
|
5)英国史上最大の反戦デモから10年
|
 |
(私以外には)どうでもいいことですが、むささびジャーナルの第1号が発行されたのはちょうど10年前、2003年の2月23日でした。その第1号の最初の記事がBBCの視聴者とブレア首相の対話集会に関するものだった。話題は英国のイラク戦争への参加についてだったのですが、この対話集会の約一か月後の3月20日にアメリカを中心とする「有志連合軍」(coalition
forces)によるイラク爆撃が始まったわけです。
2003年の2月中旬、ロンドンに100万人という大群衆が集まってイラク戦争に反対するデモが行われました。このデモは英国史上最大の規模と言われて今でも語り継がれており、「あの反戦デモから10年」という記事がいろいろと出ています。あの当時、イラク戦争については労働党の内部にもかなりの反対意見があったし、ICMという世論調査機関が行った調査では、イラク爆撃に「賛成:30%」、「反対:47%」、「分からない:23%」となっていた。それを押し切って参戦を決めたブレア首相は2003年3月1日付のGuardianとのインタビューでイラク戦争への参加決定について
- 歴史が私を判断するはずだ。
History will be my judge.
と語っています。つまり自分の正しさは将来明らかになるだろうということですね。また爆撃開始2日前の3月18日に行われた下院の採決では賛成412票・反対149票(うち労働党が139票)という圧倒的多数でブレアの参戦政策が支持されたのですよね。
あれから10年、2013年2月15日付のGuardianが
- 英国人は歴史をブレアが望むようには読んでいないようだ。
Britons are not reading it in the way Blair would have hoped.
と言っています。同紙がICMに依頼して行った最近の調査によると、55%が「イラク戦争は間違っていた」として、「正しかった」とする28%のほぼ2倍になっているということです。いまの英国人の意見を党派別にみると、2003年当時の反戦集会の正否について次のような結果になっています。
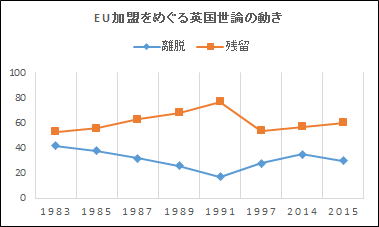
保守党支持者の間でさえもイラク戦争に反対の意見の方が多いのですが、イラク爆撃開始の直前の世論はかなり好戦的(belligerent)になっていたのも事実です。でなければ下院であれほどの支持は得られなかったはずです。
2003年3月18日の下院におけるブレアの演説は「極めてパワフル」と評価されているものであり、その結果として大規模な反戦デモにもかかわらず議会は圧倒的多数でブレアの方針を支持した。その演説はここをクリックすると読むことができますが、イラクのサダム・フセイン大統領がいかに暴力的で危険な存在であるかということをさまざまな事実を挙げながら訴えかけた。演説は次のような言葉で終わっています。
- いまやこの議会が、単にこの政権、単にこの首相だけではなく、まさにこの議会が先頭に立って、自分たちが正しいと分かっていることのために立ち上がることを示すときであり、我々が圧政者、独裁者、テロリストたちに立ち向かうときなのであります。彼らこそが我々の生活を脅かすのです。決断のときです。自分たちが正しいことを断行するという勇気を持っているということを示すときなのであります。
This is the time for this house, not just this government or indeed this prime minister, but for this house to give a lead, to show that we will stand up for what we know to be right, to show that we will confront the tyrannies and dictatorships and terrorists who put our way of life at risk, to show at the moment of decision that we have the courage to do the right thing.
が、その後ブレアが、イラクが大量破壊兵器を隠していると主張したにもかかわらずそれが見つからず、ブレア政権が危機感を煽り立てたのではないかという疑惑が出てきたりした。さらにフセイン政権打倒後もイラクが内戦状態に陥ってしまったこともあって、世論は急速にブレアから離れて行き、戦争開始から4年後の2007年の調査では55%対30%で反対意見が強くなっていった。
ただイラク爆撃によってブレアが提起したのは、ある国の内政問題に他国が軍事介入することの善し悪しという問題でもあった。イラクでサダム・フセインが独裁的な政治をやろうがどうしようが、それはイラク人の問題であって他国が介入するべきではないという見方に真っ向から反対したのがブレアだった。彼によると、フセインのような独裁者が支配することは単にイラク国民だけの問題ではなく、世界の安全にかかわる問題でもある。フセインを打倒することでイラク国民を独裁者から解放することになるだけではなく、世界全体も良くなる、だから軍事介入も辞すべきではない・・・というわけです。「進歩的介入主義」(liberal
interventionism)という考え方です。保守主義者ではなく、ブレアのような「進歩派」「革新派」と呼ばれる人たちによる「正しいことのためには他国への介入も辞さず」というタカ派的な発想です。
このあたりのことになると、実は英国人の意見は必ずしも軍事介入反対というわけではない。イラクではうまくいかなかったけれど、アフガニスタン、リビア、マリなどへの軍事介入についてGuardianが行った最近の調査でも次のような結果が出ている。
- 48%:軍事介入は殆ど問題解決に繋がらず、却って敵を作り出すだけで、英国にとってはいいことよりも悪いことの方が多い。Military interventions solve little, create enemies and generally do more
harm than good.
- 45%:英国は軍事力を通して世界を良くする力となることができる。Through its armed forces, Britain generally
acts as a force for good in the world.
「軍事介入は止めた方がいい」という意見のリードはわずかに3%にすぎないのです。党派別にみても、保守党支持者が介入に肯定的なのは分かるとしても、労働党や自民党の支持者でもほぼ半数が同じような意見なのです。ちょっと変わっているのは独立党(UKIP)支持者で、56%対32%ではっきり介入反対が多い。この党は従来の右派・左派という区別からすると明らかに右派なのですが、必ずしも大英帝国に対する郷愁があるわけではないということのようです。
| ▼具体的に調べたわけではないので、むささびの勝手な印象かもしれないのですが、ブレア首相について日本のメディアはかなり好意的に評価していると思います。違います?そしてその根拠となるのが、「リーダーシップを発揮した」とか「自分の信念を貫いた」ということのようです。違いますか?私は「リーダーシップ」であれ「信念」であれ、やはり中身を語ったうえで評価するべきであると考えています。ヒットラーも日本の軍国主義者も金正日も(もちろんジョージ・ブッシュも)みんな「信念の人」であったのですからね。 |
|
back to top
|
|
6)どうでも英和辞書
|
A-Zの総合索引はこちら
|
perverting the course of justice:司法妨害
 アメリカではObstructing justiceと言うのだそうですが、イングランド、カナダ、インド、アイルランドではこのように呼ぶ。要するに公正な裁判や司法捜査などが行われることを妨害するような行為のことで、例えば証拠捏造・隠滅、証人・陪審員脅迫、偽証などがこれにあたる。最近の英国メディアでこの言葉が盛んに使われたのは自民党(Lib-Dem)のクリス・ヒューン(Chris Huhne)という国会議員が辞職したケースです。この場合は、議員本人と彼の元妻の両方がperverting the course of justiceの罪に問われている。 アメリカではObstructing justiceと言うのだそうですが、イングランド、カナダ、インド、アイルランドではこのように呼ぶ。要するに公正な裁判や司法捜査などが行われることを妨害するような行為のことで、例えば証拠捏造・隠滅、証人・陪審員脅迫、偽証などがこれにあたる。最近の英国メディアでこの言葉が盛んに使われたのは自民党(Lib-Dem)のクリス・ヒューン(Chris Huhne)という国会議員が辞職したケースです。この場合は、議員本人と彼の元妻の両方がperverting the course of justiceの罪に問われている。
今からちょうど10年前の2003年3月12日、ヒューン氏の車が高速道路を走行中にスピード監視カメラにひっかかってしまった。スピード違反ですな。ただこの場合、車はヒューン氏のものであったのですが、運転していたのは彼の奥さんであったという申し立てがあり、これが受け入れられて奥さんの運転歴に3ポイントの違反がついた・・・と、これで終わっていればperverting
the course of justiceなどという面倒なハナシにはならなかった。
このスピード違反の7年後(2010年)、ヒューン氏は現政権のエネルギー・気候変動大臣という要職についたのですが、その直後に自分の広報担当である女性と不倫関係にあることがばれてしまった。ヒューン氏はそれでどうしたのかというと、26年間連れ添った自分の妻と離婚すると発表した。
その1年後の2011年5月、「あのスピード違反は実は奥さんではなく、ヒューン氏本人が運転していたものであり、ヒューン氏が奥さんに罪をなすりつけたものである」という報道がなされた。これは元の奥さんがメディアに情報を提供したことがきっかけだった。
そして昨年(2012年)の2月にヒューン氏と元の奥さんの両方が2003年のスピード違反について偽証をしたというわけでperverting the course of justiceの罪で起訴されてしまった。ヒューン氏は「記憶にない」、奥さんは「無理やり押し付けられた」ということで両方とも無罪を主張したのですが、ヒューン氏の方は大臣の職を辞してしまった(議員は辞職していない)。が、つい最近(2月初め)になってヒューン氏が罪を認めて議員をも辞職、元の奥さんの方はまだ無罪主張をして争っている。
このハナシを聞いていると、最初(2003年)からスピード違反を認めていれば良かったのに・・・と思うけれど、ヒューン氏の場合、それまでにも何度かスピード違反をやっており、ここで捕まると3年だか4年だかの免許停止になってしまうという状況だった。日本のように新幹線のような公共の乗り物を使って地元へ帰るというわけにはいかない(あまりにも電車の頻度が少なすぎる)ので、クルマによる移動が政治活動には不可欠。というわけで奥さんに「頼むよ、いいだろ?な?」となってしまったってことですね。
|
back to top
|
7)むささびの鳴き声
|
▼2月21日、3人の死刑囚の刑が執行されたということを谷垣法務大臣が発表していました。彼らがどのような人で、どのような罪を犯したのか等についてはNHKのサイトに出ているのでここでは繰り返しません。それよりも死刑という刑罰の善し悪しについて篠田博之というジャーナリストが自分のブログで語っているものを紹介したいと思います。
▼篠田さんは死刑になった3人のうち2人と取材を通して知り合いになっていたのだそうです。一人は小林薫、もう一人は金川真大という人だった。小林氏は2004年に奈良市で下校途中だった小学1年生の女の子を連れ去って殺害するという犯行だったのですが、「死刑になるために殺人を犯した」ということを本人が言っていた。死刑になりたいと念願していたのだから、なまじ減刑などになっては困る。裁判で検察が主張した「筋書き」は事実とは全く違っていたのに、「死刑になりたいので争わず受け入れるとして、法廷で真相を語ることを拒否していた」と篠田さんは書いています。
▼ただ、変わっているのは、この死刑囚は裁判では真相を語らなかったのに「真実は残したい」というわけで、篠田さんが編集長を務める『創』という雑誌に手記を書いたということです。つまり検事の言うことは間違っているけれど、それを言い出すと死刑になれないので、真実は別に書かせてもらいますということです。そして小林氏は念願かなって死刑になった。小林氏の「手記」と検察の「筋書き」、どちらが「真実」なのか、本当のところは分からないけれど、裁判を傍聴した篠田さんは
- いずれが真実なのか、本当はそれを争い裁くのが法廷なのだが、実際の裁判ではほとんどその解明はされないまま、被告の望み通りに死刑判決が出された。こんなことでよいのか、と私は裁判を傍聴しながら、大きな疑問を感じざるをえなかった。
と言っている。
▼死刑囚の言うことが本当だったとすると、彼は自分で自分の命を絶つことはせずに裁判所に「殺してください」と直訴して、それが通ってしまったということになる。篠田さんはブログで
- 死刑が凶悪犯罪の抑止どころか逆に犯罪の背中を押した事例だ。本人はただ死にたくてやったというだけだが、そういう人間を死刑にすることが「裁いた」ことになるのかどうか、真剣に考えるべき事件だと思う。
と言っています。
▼英国では1998年に死刑制度が廃止されているのですが、実は復活を望む声がかなり強い。2011年の世論調査では「幼児と警察官殺害については死刑」という意見が60%に上っている。そもそも1998年に廃止されたのも欧州人権協定との関連で「人権法」(Human
Rights Act)が制定されたからなのですが、その際の議会の採決でも約160人の議員がこれに反対している。それにしても篠田さんの言うように自殺願望者のお手伝いとしての死刑制度など考えてもいませんでした。
▼ところで、私、犯罪者のことを「XX容疑者」とか「YY死刑囚」、「ZZ被告」と書くことに抵抗を感じます。メディアでは普通に使われているけれど、警察お仕着せの呼称をそのまま使う神経が私などには理解の域を超えています。
▼最後にむささびジャーナルはちょうど10年前(2003年)の昨日(2月23日)始まっています。隔週日曜日にお邪魔しているわけですが、2月23日が日曜日となるのは来年(2014年)で、それ以後では2025年(むささび82才)、2098年(むささび157才)のようであります。それから日英同盟締結の1902年も2月23日が日曜日だった。日本(いや世界)の歴史にとって画期的な日となった1941年7月5日は土曜日でありました。何を隠そう、この日、むささびが生まれているのであります・・・という具合で、カレンダーネットというのは案外楽しめますね。
▼お付き合いいただき感謝します。まだまだ寒いです、お身体に気を付けて・・・。 |
back to top
←前の号 次の号→

message to musasabi
journal
|
|
|
![]()