| 埼玉県はまだ梅雨の真っ最中で、かなり蒸し暑い日が続いています。むささびにも畑というのがありまして、そこにカボチャを植えました。一ヶ月ほど前のことです。昨日、なんと花が咲いていたのでありますね。これはしめたものだってんで、説明書きを見たら「収穫は開花から50日後が普通」とありました。まだ一ヶ月半も待たなければダメだなんて、ウソでしょ?上の写真はカボチャには無関係、イワシの群れの中を泳ぐサメだそうです。 |
目次
1)「沖縄慰霊の日」の伝わり方
2)中国の反テロ対策:ラマダン代わりにビール祭り!?
3)「ガーディアン」 が目指しているもの
4)ガーディアン:「コメント民主主義」のあり方
5)認知症を「哲学」する
6)どうでも英和辞書
7)むささびの鳴き声
|
1)「沖縄慰霊の日」の伝わり方
|
 |
6月23日付のGuardianに
という記事が出ています。6月22日の「沖縄慰霊の日」の式典会場で安倍首相が「野次り倒された」(heckled)という意味ですよね。同じ日の英国メディアには似たような見出しが見られました。
という具合です。安倍さんが演説しているというのに彼に対して「戦争屋!」とか「帰れ!」という野次が聞こえたということですよね。むささびの見落としかもしれないけれど、Telegraphのサイトだけがこのニュースを伝えていなかった。「たいしたこっちゃない」と思ったんですかね。それからDaily
Mailの記事はロイター通信のものを使っており、自分たちの特派員からの報告ではない。
沖縄慰霊の日に関する報道のうち最も詳しかったのがGuardianのもので、太平洋戦争における沖縄の過酷な経験から韓国の従軍慰安婦問題にいたるまで解説されています。記事中で安倍さんの演説内容を報道したのは次の2カ所だった。
- People in Okinawa have long been asked to carry a big burden for our security. We will continue to do our best to reduce it.
沖縄の人々には、米軍基地の集中など、永きにわたり、安全保障上の大きな負担を担っていただいています。今後も引き続き、沖縄の基地負担軽減に全力を尽くしてまいります。
- We must take pride in the path of peace we have single-mindedly walked in the last 70 years and make ceaseless efforts to establish world peace.
この七十年間、戦争を憎み、ひたすらに平和の道を歩んできた私たちの道のりに誇りを持ち、これからも、国際平和の確立に向け、不断の努力を行っていかなくてはならないのだと思います。
Guardian以外の記事は、BBCも含めて安倍さんの言葉を引用することはなく、沖縄が現在置かれた立場とそれに対する沖縄県民の不安・不満に軽く触れ、もっぱら首相が野次り倒されたことに重点が置かれた報道であったと(むささびは)思います。ちなみにThe
Timesの東京特派員のRichard Lloyd-Parryは彼自身のツイッターで
- PM Abe openly heckled and derided by crowd. Never seen anything like it
in Japan.
- 安倍首相が群衆によって公然と野次られ、侮辱された。こんな光景を日本で見るのは初めてだ。
と言っている。この人は(むささびの記憶によると)少なくとも30年は東京で英国メディアの特派員をやっていると思います。
ところで安倍さんが野次られたことは日本のメディアではどのように報道されたのでありましょうか?昨日(6月27日)のTBS『報道特集』ではかなり詳しく報道していましたが、例えばNHKのサイトには「沖縄慰霊の日で戦没者追悼式」という記事は出ているけれど、野次については全く触れられていない。新聞ではさぞや大きく報道されているのだろうと思ったのですが、ネットで検索する限りほとんどなかった(でもこれはむささびの検索努力不足のせいですよね、ね?)。
一つだけ目に付いたのは、6月24日付の「琉球新報」のサイトに出ていた「『戦争屋 帰れ』安倍首相に罵声 沖縄全戦没者追悼式」という記事だった。それによると、この野次を飛ばしたのは那覇市に住む82才の男性で、沖縄戦で祖父を失ったけれどまだ遺骨も見つかっていないとのことで、安倍首相に野次を飛ばした理由について、
- 「辺野古の基地建設を止めることが、私が生きている間に沖縄差別をなくす最後の機会だと思っている」と説明した。
と琉球新報は伝えています。
▼むささびは、野次を飛ばした82才に「ありがとう、よくやってくれた!」とお礼を言いたいのですが、もうひとり絶賛に値すると思うのが、この記事を書いた記者ですね。野次を飛ばした男性は「警官に促され、退席させられた」のだそうですが、むささびの勝手な想像によると、琉球新報の記者は安倍さんのスピーチよりも野次を飛ばした人物の方が気になって、式典の会場から警官に付き添われて会場を出て行くこの82才を追いかけて行って上記のコメントをとった、と。こういう記事を書く記者とこれを活字にする新聞社に敬礼をしたいと思いません?
|
|
| back to top |
2)中国の反テロ対策:ラマダン代わりにビール祭り!?
|
 |
6月27日付のThe Economistに「中国におけるイスラム教徒」(Muslims in China)という記事が出ているのですが、その見出しが
- Wooing Islamists with a beer festival
イスラム教徒をビール祭りでなだめる
となっている。何のことかと思ったら、イスラム教徒が多く暮らす新疆ウイグル自治区のあるお役人(イスラム教徒ではない)がラマダン(断食月)の初めにビール祭りをやらせたというものだった。The Economistの記事は中国政府に対して「イスラム教徒にもっと思いやりを持て」(Try treating Muslims more sensitively)と言っているのですが、記事を読んでみると、「なるほど」と思ってしまいます。
中国西端の新疆はウイグル族の「自治区」ということになっていますよね。人口は約2000万で、ウィグル族が45%、漢族が41%を占めているけれど、このエリアで暮らすウィグル族のほとんどがイスラム教徒です。最近、このエリアにおける漢族を狙ったテロリズムが相次いでいるということは日本のメディアでも報道されています。過去2~3年間で「テロ事件」(と中国政府が言っている出来事)によって殺された人の数はざっと400人、直近では6月22日にカシュガルという町で18人が死亡している。
The Economistによると、この地区の経済は石油とガスの生産で潤っているのにウィグル族にはほとんど利益が還元されず人口では40%にすぎない漢族がこれを独占してしまっている。石油、ガス関連の企業の経営者もほとんどが漢族なのですが、雇われているのはほとんどが漢族でウィグル族には職がまわってこない。ウィグル族の人間は言葉(中国語)もまともに話せないし、技術も持っていないから、というのが雇用者側の言い分です。このエリアの社会的安定のためにはウィグル族の教育向上が欠かせないと中国の政府当局は言うけれど、漢族とウイグル族との間の対立が激しくて、社会的安定どころかますます事態が悪くなっている。それを示したのが6年前の2009年に首都のウルムチで起こった暴動で、約200人が死亡した。
The Economistの記事は、中国がもっとウィグル族の文化や宗教を尊重しない限り騒乱はなくならないと言っている。例えば中国政府が行っている「対テロ人民戦争」(“people’s war” against terrorism)の一環として実施されているのが、イスラム教女性によるヴェール着用の禁止であり、男性の場合は髭を伸ばすことが禁止されたりしており、これがイスラム教徒の怒りを買っている。
ヴェールの禁止などはフランスやベルギーでも行われているけれど、The Economistによると中国のやり方はあまりにも過酷(draconian)すぎるのだそうです。今年の3月には髭を伸ばしていたイスラム教徒の男性が「騒乱を喚起」(prvoking trouble)した罪で6年間の禁固刑を食い、彼の妻もヴェールで顔を覆っていた罪(!?)で2年間の刑務所入りとなったりしているのだそうです。さらにイスラム教徒にとっては欠かせない行事であるラマダンについては、教師、官僚、学生による参加を禁止したりしている。
中国側も何もしていないのではない、というわけで、例えば昨年には新疆の役人20万に対してウィグル族と暮らす計画というのを実施した。ウイグル族が抱える悩みや問題点を「理解」することが目的であったのですが、とてもウィグル族の言うことにまともに耳を傾けたとは思えない(They clearly failed to listen hard enough)とThe Economistは言っている。その例として挙げられているのが、記事の最初に出てきた「ビール祭り」です。6月の初め、イスラム教徒がラマダンの準備で忙しい時期であるにもかかわらず、ホータンという町では地方役人の思いつきでビール祭りが開催され、地元のニュースサイトには、このお祭りに参加した人びとがへべれけに酔っ払っているシーンが登場したりしており、海外にいるウィグル族の怒りを買っている。
中国では現在「反テロ法」(counter-terrorism law)が作られようとしているのだそうですね。草案によると、当局の許可を得ない宗教活動はすべて「過激」(extremism)と見なされることになる。普通の人びとを「過激分子」に育て上げないために必要なのは、一般大衆の中の欲求不満を少なくすることなのに、「厳しい取り締りは新疆のみならずそれ以外の中国さえも、これまで以上に危険な場所にしてしまうだろう」(Heavy-handedness will only make Xinjiang - and the rest of China - less safe)とThe Economistは言っている。
▼この記事のキーワードは "sensitive" ですね。中国人(漢民族)はもっとウィグル人に対して "sensitive"
でなければダメと言っている。この言葉にはどんな日本語が最も適切なのでありましょうか?"sensitive"の反対(insensitive)は「無神経」という日本語が当てはまると思うのですが、"sensitive"
は "understanding" というような意味もあるから「理解力がある」という感じですね。はっきり言うと、漢民族の皆さんにはそれがない、と?
|
| むささびジャーナルの関連記事 |
| ウィグル出身、ピザ職人の流浪 |
|
| back to top |
3) 「ガーディアン」 が目指しているもの
|
 |
むささびがたびたびお世話になる新聞、ガーディアン(Guardian)の編集長が代わりましたね。それまで20年間その地位にあったアラン・ラスブリッジャー(Alan Rusbridger)が5月いっぱいで退任、キャサリン・バイナー(Katharine Viner)が、ガーディアンの歴史上初の女性編集長に就任しました。ラスブリッジャーは1953年生まれ(61才)、編集長になったのは1995年(42才)だった。キャサリン・バイナーは1971年生まれだから44才の編集長ということになる。
5月29日付のガーディアンに、ラスブリッジャー編集長が‘Farewell, readers’という読者宛のお別れ記事を寄稿しており、彼自身の編集長論のようなものを語っているので紹介します。非常に長いお別れエッセイなので、一ヶ所だけ抜粋しますが、全文はここをクリックすると読むことができます。ラスブリッジャーのエッセイにはいる前にガーディアンという新聞そのものの歴史を手短に紹介します。 |
 |
ガーディアンの第一号は1821年5月5日、マンチェスターに本社を置く新聞(Manchester Guardian)としてジョン・テイラーという人物によって発行された。きっかけとなったのは2年前の1819年にマンチェスターで起こったThe Peterloo Massacre(ピータールーの虐殺)という事件だった。当時の英国は劣悪な経済状況で大衆は飢餓状態にさえあった。これに抗議する集会が「選挙法改正」という名目で開かれたのですが、これに政府が派遣した奇兵隊が突入して弾圧をはかり多数の死者を出した。マンチェスター・ガーディアンは、このような民衆の声を支援するという目的で発刊されたものだから、誕生当初からどちらかというとラディカルかつリベラルな雰囲気をもつ新聞だった。
ただマンチェスター・ガーディアンの名前を全国的・国際的にも不動のものとしたのは、1872年から57年間も編集長兼オーナーの座にあったCPスコットだった。CPスコットは1932年に死去、その後、息子のジョン・スコットがスコット・トラスト社(Scott Trust)という信託会社を設立、マンチェスター・ガーディアンの所有権をこの会社に移譲した。1964年に本社をマンチェスターからロンドンに移しています。
スコット・トラスト社のサイトに出ている説明によると、同社は株主や所有者がおらず、ガーディアンが稼ぐ利益は新聞設立のバックボーンとなったジャーナリズムの質を維持することに使われるとなっている。同社が掲げる「ジャーナリズム」とは「産業界や政治勢力による介入からの自由」(free from commercial or political interference)を意味するのですが、名編集長であったCPスコットが、創刊100周年にあたる1921年に書いた社説の中で掲げたジャーナリズムの理念の例を挙げると:
- 意見(を述べること)は自由である。しかし事実こそが聖なるものである。
Comment is free, but facts are sacred.
- 反対者の意見は仲間の意見と同じように傾聴される権利を有している。
The voice of opponents no less than that of friends has a right to be heard.
- 新聞というものは、物質的な存在であると同時に道徳的な存在でもあるのだ。
Newspapers have a moral as well as a material existence.
|
 |
ラスブリッジャー編集長は上に挙げたCPスコットの三つ目の言葉(新聞は物質的な存在であると同時に道徳的な存在でもある)について自分の考え方も含めてさらに詳しく語っています。それによると、新聞発行には、これを売って収益(profit)を上げようという目的と、世の中を良くする「力」(power)になろうという目的がある。前者は「物質的な存在」(material
existence)としての新聞であり、後者は「道徳的な存在」(moral existence)と言うことができる。CPスコットにとっては「力」が「収益」を上回ることは明々白々だった。そしてラスブリッジャーは次のように語ります(ちょっと長いけれどそのまま訳してみます)。
|
 |
新聞編集の世界では、新聞の「道徳性」が「収益の追求」という目的よりも大切であるという(CPスコットのような)考え方を現代の新聞編集にあてはめようとすると、私としては不安な(uneasy)気持ちになってしまうのだ。この際、その不安感について正直なところを白状させてもらいたい。
編集長の「絶大なパワー」
まず言えることは、編集長という存在は、男だろうが女だろうが、本人にその気さえあれば、極めて大きな影響力を行使できる存在だということである。編集長は人びとを成長させることもできるし、めちゃくちゃに破壊することもできるのだ。編集長は、どの人間が発言権を与えられ、どの人間が「無言」(voiceless)を強いられるのかを決める権限を与えられているのだ。その気になりさえすれば、自分の気に入らない奴らをいじめぬき、脅迫することだってできる。編集長は、新聞を通して自分の考え方を国や何百万もの人びとのに対して押し付ける(impose)こともできる。
英国でもこれまで見てきたとおり、編集長たちは、法を破ってまでして個人の生活に立ち入ったとしても誰も止めることはないという自信さえ持ってしまっているのだ。警察も、役人も自分たちを止めることはない・・・そう確信しているのだ。彼ら(編集長たち)は世の中で行われる議論というものに対して不釣り合いなほどに大きな影響力(disproportionate influence)を与えることができる。それは自分たちの意見を主張するということだけでなく、ある種の意見は無視する(報道しない)ということによっても可能なのである。第一面からニュース面、社説欄にいたるまで、一つの新聞の最初から最後までを一人の人間が支配することも可能である。評論家の選択についてさえも編集長が支配することができる。
「第四階級」は強いほうがいい
現代では、いわゆる主要メディア(mainstream media)の影響力が低下しているとされるけれど、それでも人びとは編集長のこの種の「力」には屈してしまうものである。私はどちらかというとおとなしい方ではあったけれど、その私でさえ編集長としての「力」を実体験したことはある。そして、ある意味において、私は編集長の「力」が強いということはいいことだと思っている。「第四の権力」(fourth estate)には強い伝統の力(institutions)が必要だと思っている。グローバル化し、遠く離れ、しばしば無責任である権力が支配する世界においては、それに対抗するような監視の力や影響力を有した反対勢力(countervailing source of scrutiny and influence)がこれまで以上に必要とされているのである。 |
 |
反対者の意見
しかし私はガーディアンが自分の意見を反映することを望んだことはただの一度もない。ガーディアンの同僚だってそれを望まなかったであろうし、許しもしなかったであろう。CPスコット編集長が明確に理解していたのは、編集者は「独占の誘惑」(temptations of a monopoly)に勝たなければならないということであり、「反対者の意見は仲間の意見と同じように傾聴される権利(right to be heard)を有している」ということである。
自分がいつもCPスコットの理想に沿ってきたのかは定かではないけれど、(リベラルを標榜する)ガーディアンという新聞が、執筆陣の中に必ずしもリベラルとは言えない書き手を抱えているということこそが大切なのだとは思ってきたものである。例えばSimon Jenkins, Max Hastings, Matthew d’Anconaのような人びとである。 |
|
むささびでは何度も触れてきたことですが、英国の全国紙の場合、大衆紙(populars)というのと高級紙(qualities)というのに大別され、ガーディアンは後者の部類に入ります。ラスブリッジャーによると現在のところどの新聞社も赤字だそうですが、いずれもインターネット・メディアとしての生き残りをかけていると言っている。その意味で興味深いのはガーディアンとThe Timesです。前者のネット版は原則としてどの記事も無料で読めるけれど、後者の場合はお金を払わないと一本も読むことができない。ネット版The Timesの有料購読者は28万1000人と言われているけれど、ネット版のGuardianの読者(unique browsers)数は700万人、うち3分の2が英国外の読者だそうです。 |
▼ネット新聞の日英比較をしてみました。英国のThe Timesと日本のM新聞を比べてみた。The Timesの場合、料金は一か月24ポンド(1週間で6ポンド)。むささびの金銭感覚によると24ポンドはざっと2400円という感じです。M新聞のデジタル版の料金は3200円です。記事内容の善し悪しは個人的な好みもあるので比較するのは止めておくけれど、The Timesの場合、有料購読者は過去200年にわたる同紙のバックナンバーを読むことができる。M新聞?たった5年分です。むささびの読み違いでしょうか?そうでないとすると、同じお金を払っても得るものがあまりにも違うと思いません?
▼ラスブリッジャー氏は読者へのメッセージの中で、編集長という立場の人間が職業柄持っている「絶大なパワー」について語っているのですが、むささびが興味をひかれたのは、編集長という立場にある人は「どの人間が発言権を与えられ、どの人間が無言(voiceless)を強いられるのかを決める権限を与えられている」と言っている点です。誰が何をどのような大きな声で叫んでも新聞がそれを掲載せず、放送がそれを伝えなかったら「無言」(voiceless)と同じことになる。沖縄慰霊の日の式典で安倍さんに「戦争屋、帰れ!」と叫んだ人も日本(本土)のメディアの編集者によって、国内的には「言わなかった」ことにされてしまったかもしれないですね。
|
|
| back to top |
4)ガーディアン:「コメント民主主義」のあり方
|
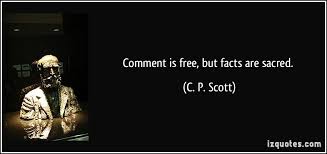 |
退任したアラン・ラスブリッジャーは1995年から2015年までの20年間をガーディアンの編集長として過ごしたわけですが、それは新聞が「紙」から「ネット」へ移行した20年でもある。「紙」でも「ネット」でも文字による情報伝達という意味では変わらないのですが、「決定的」ともいえる違いの一つにネット媒体においては、読者による「参加」が紙媒体とは比較にならないほどの規模で可能になったということがあります。
紙の新聞の場合でも「読者からの手紙」(letters to editor)という形で読者の意見を伝えることは可能であったけれど、せいぜい10本~15本程度だった。ネットの場合は1000件を超えるケースもあるし、ネット新聞の上に設けられたスペース上で読者同士が意見交換をするということも可能になった。ネット・メディアならではのそのような特性を生かして、ガーディアンが2006年に始めた「実験」(experiment)が "Comment Is Free" (現在はOpinion)というコーナーだった。ジャーナリストや評論家のような人が、自分の意見を述べるようなエッセイを投稿、それに対する読者がコメントを寄せる、それを読んだ別の読者がコメントに対するコメントを投稿・・・という具合いで、読者参加型のディスカッション・スペースが作り出される。"Comment Is Free" はかつての名編集長であったCPスコットが「反対者の意見を尊重する」という社是の根幹として掲げた言葉です。

"Comment is Free" コーナーの編集担当者たち |
このコーナーの責任者はジョージナ・ヘンリー(Georgina Henry)という女性編集者(故人)だったのですが、彼女の言葉によると、ATL (above the line) と呼ばれる書き手とBTL (below the line) と呼ばれる書き手が紙面作りに参加する。ATLは記者であれ、評論家、学者、政治家であれ、名前を名乗った上で記事を書く人びとのことです。BTLというのは無記名・匿名の投稿者です。
ジョージナ・ヘンリーは、Comment Is Freeの部長を務めるなかで学んだことが二つあると言っています。一つは「ATLとBTLは相互依存の関係にある」(mutually dependent)ということであり、お互いがお互いのベストを引き出すということ。そして・・・
- もう一つ学んだのは、新聞の世界で育ったジャーナリストたちが自分たちの権威とか支配権のようなものを手放すことを如何に嫌っていたかということだった。
I've also learned how difficult it is for journalists who grew up in a print world to cede authority and control.
とも言っている。新聞記者にしてみれば、自分たちこそが物事に通じているのであり、その権威をBTLなどに壊されてたまるかという気持ちがあったということですよね。
記者たちがどう思っていようと、編集長であったラスブリッジャーは "Comment Is Free" の登場によってガーディアンのコメンタリー機能が大幅に拡大・多様化した(immensely broadening and diversifying)こと、新聞の世界に「コメント調整役」(comment moderators)とでもいうべき新しいタイプのジャーナリストが生まれたとも言っている。
- ("Comment Is Free"の登場によって)我々は、表現の世界の新たなる民主主義のようなものを作り出したのである。その民主主義はときとして不愉快なこともあるが、大体において豊かで興味深い世界であり、たまには実に爽快な気分になれる世界でもある。
We had created a new democracy of expression, which was sometimes uncomfortable, but mostly rich and absorbing, and sometimes even exhilarating.
ここをクリックすると、Comment is Freeのコーナーへの参加(投稿)についての規則のようなものが細かく説明されていますが、要約すると次の3点が守られないようでは困るということのようです。
- If you act with maturity and consideration for other users, you should have no problems.
大人の態度であなた以外のユーザーのことも考えてもらえれば何の問題もないはず。
- Don't be unpleasant. Demonstrate and share the intelligence, wisdom and humour we know you possess.
人を不愉快にさせるような言葉は使わないこと。あなたにだって知性・知恵・ユーモア感覚があるはず。それを発揮してください。
- Take some responsibility for the quality of the conversations in which you're participating. Help make this an intelligent place for discussion and it will be.
このコーナーで繰り広げられる会話の質の維持に責任を持つこと。この場を知的なディスカッションが行われる空間にすることです。
6月19日付のこのコーナーにガーディアンのコラムニストが書いた
- Why don't Americans call mass shootings 'terrorism'? Racism
アメリカ人が大量射殺のことを「テロリズム」と呼ばない理由は何か?人種差別、それが理由だ。
という見出しのエッセイが掲載されています。これはサウス・カロライナのチャールストンの教会で起こった大量射殺事件について語っている記事で、「アメリカでは白人がテロリスト的な行動をとってもそれをテロとは決して呼ばない。それは人種差別主義者が殺人者とは限らないという考え方をしっかり守りたいからだ」というわけで、アメリカ社会には人種差別には甘いという特徴があるということを批判するような内容の記事です。
この記事が掲載されたのは6月19日ですが、6月20日現在で1106件のコメントが寄せられている。最初のコメントは
- They didnt call Nidal Hasan - the Fort Hood mass killer - a terrorist, and he was Arabic. Anyone else got any leftist shibboleths that need demolishing?
Fort Hoodの大量殺人の犯人(Nidal Hasan)だってテロリストとは呼ばれていません。彼はアラブ人ですよ。誰か、他にこの種の陳腐な左翼的理屈を披露したい人はいませんか?叩いてへこましておく必要がある。
ガーディアンのコラムニストの主張を「左翼による陳腐な理屈」と批判しているわけです。この批判について、別の人が「テロリストと呼ばれる人も場合によっては自由のための戦士と呼ばれることもある」(One
man's terrorist is another man's freedom fighter...)というコメントが寄せられている。このようなコメントに混じって
- This comment was removed by a moderator because it didn't abide by our
community standards.
- このコメントは調整担当者により削除されました。我々のコミュニティの基準に合致していないからです。
という文章が載っている。やや薄い文字で書かれているのですが、投稿者のペンネームを記したうえで、ガーディアンの基準に合わないので削除されたと言っている。なにも言わずに無視するのではなく、「違う意見もあったけれど、ひどい内容だったので削除した」と公表している。投稿そのものを「なかったことにする」のではない。
▼Comment is Freeの責任者だったジョージナ・ヘンリーが、その仕事で学んだことの一つに、新聞記者という人たちが「自分たちの権威とか支配権のようなものを手放すことを大いに嫌っていた」ということがあると言っています。つまり自分たちがさんざ苦労して築き上げた「識見」が、ど素人の投稿マニアなどにとやかく言われるのは不愉快だということですね。でもこれは新聞が「紙」から双方向性が特徴の「ネット」に変わってしまったことの結果です。
▼むささびの印象によると、日本の新聞社のサイトの最大の弱点の一つが投稿欄の貧しさですね。主宰者(新聞社)がおっかなびっくりなのです。ある新聞のサイトを見ていたら、6月3日付で北岡伸一さんとの「戦後70年談話」というテーマのインタビューが出ていたのですが、これに対する投稿はたった3本。ないのと同じですよね。それは投稿がとてつもなくやりにくくなっているからです。気楽にやれない。主宰者としては「読者の投稿など自由に許したら我々のサイトが滅茶苦茶にされてしまう」というところなのでしょう。
▼その点ガーディアンの「投稿コーナー」の責任者だったジョージナ・ヘンリーの言うATL(プロの書き手)とBTL(投稿者)の相互補完という考え方は極めて健全だと思いません?新聞記事とは、玄人である書き手が素人の読者に一方的に読ませるもの・・・と日本の新聞の編集者は考えているのですよね。それでは日本のニュースサイトに未来はない!ジョージナ・ヘンリーだって最初はビクビクものだったのであります。
|
|
| back to top |
5)認知症を「哲学」する
|
 |
Aeonという雑誌のサイトに "The disremembered" というタイトルのエッセイが出ています。"disremember" という単語は見たことがなかったのですが、辞書によると
"fail to remember" という意味だそうです。「記憶することができない」ということですね。このエッセイは認知症について語っているものなので
"The disremembered" の意味は「記憶することができない人びと」という意味なのであろうと思うのですが、ひょっとすると「忘れられている人びと」という意味なのかも知れない。
エッセイの筆者はチャールズ・リードビーター(Charles Leadbeater)という社会思想家で、この人は公共政策などについてのコンサルティングなどを主なる仕事にしている。このエッセイは、社会が認知症とどのように付き合うべきかについて語っています。
|
 |
予め言い訳めいたことを言うのも情けないのですが、この記事の内容を正確かつ読みやすく伝えることができるのか大いに不安を感じております。認知症そのものについての知識がほとんどないということもあって、これに対する問題意識のようなものがどの程度筆者と共有できるのか定かではないからです。ただその一方で紹介してみたいという欲求もある。一つには、むささび自身がこれに罹りつつあるという気がしないでもないということがあるけれど、エッセイの中に出てくる次の言葉に大いに好奇心をそそられてしまったからです。
- 哲学という学問が病気の治療に実践的に役に立つということはほとんどない。しかし哲学が自我とか「自分自身」というものについての考え方を提供するものであるということもあって、認知症とその症状に対する我々のリアクションについて理解するための助けとなるものだ。
Philosophy is not of much practical use with most illnesses but in the case of dementia it provides insights about selfhood and identity that can help us make sense of the condition and our own reactions to it.
|
 |
普通にはほとんど役立たずの哲学も認知症の理解の促進には役に立つと言っているわけですね。このエッセイでは "identity" という言葉がキーワードの一つとなっています。一つの日本語に置き換えるのが難しい言葉だと思うけれど、ここでは一応「自分自身」という日本語を使っておきます。
アリスの問い:私って誰?
"Still Alice" という映画をご存知ですか?昨年作られたアメリカ映画なのですが、日本では『アリスのままで』というタイトルでつい最近封切られたのだそうです。ネット情報によると「若年性アルツハイマー病と診断された50歳の女性言語学者の苦悩と葛藤、そして彼女を支える家族との絆を描く人間ドラマ」となっています。リードビーターのエッセイは、この映画の主人公(アリス)が語る次のセリフで始まります。
- 調子のいい日は、ごく普通の人間として過ごすことができるけれど、そうでない日には、自分で自分が分からない(見つからない)という感じがする。自分が何者であるのかが分からないし、自分が次に失うものは何なのかも分からないのです。
On my good days, I can almost pass for a normal person. On my bad days, I feel like I cannot find myself… I don’t know who I am and what I am going to lose next.
リードビーターのエッセイは、このセリフの中の「自分が何者であるのか」(who I am)という部分を中心的なテーマにしています。自分(人間)とは何か・・・これがidentityであり、哲学の世界のテーマですよね。
この映画の中で主人公のアリスが認知症と診断された理由は、専門医による「記憶テスト」(memory test)にアリスが合格しなかったからです。そのテストは、「いまのアメリカ大統領は誰か?」というものだった。リードビーターによると、この種の記憶テストは「75才以上のための入学試験」(SAT test for the over-75s)のようなもので、不正解だと認知症、正解だとまだそうではないという風に区分けされてしまう。認知症に関してはこのように記憶を基本にした自己認識能力のテストがいまのところ極めて一般的であるけれど、それではその人物の「自分自身」が部分的にしか分からない、とリードビーターは言います。
「記憶」にこだわりすぎる
ベルギーのルーベン大学のボールドウィン・ヴァン・ゴープ(Baldwin van Gorp)教授は、認知症についてのメディアの取り上げ方を研究しているのですが、彼によると「認知症=個人的な記憶力の減退・喪失」という側面からのみ語られ過ぎている。そのために認知症対策といえば「脳を活性化させておく」(keep your brain as fit as possible)とかさまざまな肉体的・心理的な訓練(physical and mental exercise)を奨励するものが多い。中にはメモ書きを常に患者の目のつくところに貼っておいたりして、患者の視覚に訴えるものもある。そのいずれもが「対策」を患者の外側に求めている。ひょっとすると将来は、認知症付き添いロボットのようなものが開発されて、決められた時間に薬を飲ませだり、トイレを使ったあとは水を流したりしてくれるようになるかもしれない。
|
 |
認知症を「記憶」という側面からのみ考えようとすると、どうしても「記憶の回復」(memory cures)の方にアタマが行ってしまい、それが記憶回復のための薬の開発や極端にいうと脳移植による記憶の回復のような方法に繋がってしまう。脳の中の記憶を司る部分に海馬(hippocampus)というところがあるらしいのですが、アメリカではその部分に人為的に刺激を与えることで記憶力を回復させるという動物実験が進められているのだとか。
これらの薬や脳移植のような「テクノロジー」を認知症の患者に応用して記憶を取り戻せたとしても疑問は残る。すなわちその人間は、認知症に罹る以前もしくは罹ってしまってからの人間と「同じ人間なのか?」(are they the same person?)という疑問です。技術によって作り変えられた「別の人間」なのではないか?ということです。
世の中と繋がってこそ
このエッセイは、認知症に罹ってしまった人びとの治療ではなく、まだ罹っていない人たちが認知症とどう向き合うべきかについて語るものなのですが、「自分が何者であるのかが分からない」というアリスの問いかけを「記憶」という側面からのみ考えようとすることに批判的なリードビーターが目を向けるのが「人格」(personhood)というものについてのヨーロッパ哲学の伝統です。彼が挙げている哲学者はハイデガーであり、メルロポンティですが、彼らの考え方を一言で説明すると
- 「自分が何者なのか」は、単に自分の記憶を整理整頓するだけの自己認識だけで分かるものではない。重要なのは、他者との関係であり、自分がどのように自分を取り巻く世の中の一部になっているのかということである。
Who we are depends not simply on our self-reflective ability to marshal our memories but, crucially, on our relationships with other people and how we are embedded in the world around us.
ということになる。「自分」というものは、「記憶」とか「思索」というような「アタマ」の中にだけ存在するものではなく、それぞれを取り巻く「世界の中にあってこその存在」(beings-in-the-world)である、と。つまり「自分が何者なのか?」に対する答えは自分自身の中に入り込んでいるだけでは絶対に見つからないということであり、自分の外側に目を向け、自分が他人とどのように関わっているのかを知ることである・・・リードビーターは主張している。
|
 |
自分とは何か?という問いかけについては、例えばデカルトの「我思う、ゆえに我あり」(I think. Therefore I am / je veux,
donc je suis)という言葉が浮かぶけれど、リードビーターは、人間は夫であり妻であり、息子であり娘であり、警察官であり教師であり、料理人であり・・・という世の中とかかわり方・繋がり方の中に「自分自身」を見出そうとする態度が必要だと言っている。これはまだ認知症になっていない人がとるべき姿勢についてです。認知症の患者の場合はこの「他者との繋がり」そのものが分からなくなっており、そのことが特にケアをする人びとにとっては過酷な経験となる。今年の2月にBBCで放送された「認知症日記」(Dementia
Diaries)という番組の中で認知症の夫に付き添う妻は次のようにその苦しみを述べている。
- 私が付き合っている人、がなり立てる相手である人、私を欲求不満で泣きわめかせる人・・・この人はまるでアカの他人のようなのよ。見かけは私の夫なの、でもあのハワードはもういない。
The person I’m dealing with, the person I’m yelling at, the person who’s making me weep with frustration, is like a stranger. He looks like my husband, but Howard’s gone.
「知」だけが人間ではない
認知症の人びとと生きるときに大事なのは、彼らの記憶状態ではなく、彼らがいま何を感じ、何によって心や身体を動かされるのかを知ることだ、とリードビーターは指摘します。認知症患者は、本を読むことができないのはもちろんのこと、読んでもらってもストーリーについていくことができない。しかし彼らは音楽に感動したり、ダンスで身体を動かすことを楽しんだりすることはある。それらによって微かとはいえ記憶が蘇ることもある。これは「われ思う故にわれあり」のような「個人」の世界ではないし、単なる「思索」の世界でもない。
メルロ・ポンティという哲学者は自分自身というものは「心」ではなく「肉体」に存在すると主張したのだそうですが、リードビーターは、文章による指示よりもダンスのステップのような肉体的な動きを記憶することが認知症患者には大事な場合もあると主張している。単に歩くだけでもいい。脳移植だの海馬の刺激だのによって人為的に記憶を取り戻そうとするより、認知症患者が肉体的・物理的に安心していられるような場所(環境)を作ることであるということです。それには看板やサインの類が分かりやすくて照明も心地がいいことなどが含まれる。それはまた健常者にとっても「居心地のいい場所」であることは間違いない。
|
 |
英国における認知症研究の第一人者であるジューン・アンドリュース(June Andrews)という人が書いた "Dementia: The One-Stop Guide" によると、英国の病院はサインもスタッフが使う言葉も認知症の人には難しすぎるものが多く、それが患者とのトラブルの種になり、認知症患者がお荷物扱いされることが多いのだそうです。
この瞬間に生きる
リードビーターは、人間が必ずしも「記憶」とか「知性・理性」だけの存在ではなく、「感覚」と「肉体」をも有した存在であることを理解すると同時に認知症の人びとが、自分たちと同じ闘いに取り組んでいるということを理解することが肝心だと言っている。その闘いとは、自分を作り、作り直すという作業であり、自己発見をし、自己主張をする闘いであるということです。その闘いは認知症患者がもはや「昔の自分」ではないにしても続いているものなのだ、と言っている。
リードビーターは、『アリスのままで』という映画のなかで、主人公のアリスが米国アルツハイマー協会の会合で行うスピーチを紹介しています。
- いまのところ私は生きているし、生きているということを分かっています。自分には愛する人がいるし、人生でやりたいこともあります。自分が物事を思い出せないということに腹が立つこともあります。でも私には一日のうちで純粋に幸せと喜びを感じるときもあるのです。お願いですから、私が苦しんでいるとは思わないでください。苦しんではいないのです。私は闘っているのです。それは世の中の一部であろうとする闘いであり、かつての自分と繋がり続けようとする闘いです。私は自分に言い聞かせるのです。この瞬間を生きよ、と。実際、私にできるのはそれだけなのですよ。この瞬間に生きるということ・・・。
For the time being, I’m still alive. I know I’m alive. I have people I love dearly. I have things I want to do with my life. I rail against myself for not being able to remember things - but I still have moments in the day of pure happiness and joy. And please do not think that I am suffering. I am not suffering. I am struggling. Struggling to be part of things, to stay connected to whom I once was. So, ‘live in the moment’ I tell myself. It’s really all I can do, live in the moment.
|

|
記憶はどうせ衰えるもの
社会が認知症と付き合っていくためには、「アメリカ大統領の名前を言えなければ病気だ」というように「合格・非合格」を決め付けるようなシステムに認知症患者を閉じ込めることはやめることだ、とリードビーターは主張します。その種のシステムを廃止した「優しい社会」(kinder
society)は、大統領の名前を言える人たちにとっても暮らしやすい場所のはずだというわけです。そのような社会を作るためには、未だ認知症になっていない人びとも「自分が何者なのか」を確認する過程において、常に自分を取り巻く「世界の中にあってこその存在」(beings-in-the-world)なのだということを学ぶことだ、として次のようにエッセイを結んでいます。
- 簡単に言うと、記憶さえまともならオーケーと考えたがる誘惑を断ち切ることだ。人間、記憶に関する限り、誰だって下降線をたどる可能性があるものなのだから。
Put simply, we should avoid the temptation of becoming memory snobs, as any of us could find ourselves downwardly mobile so far as memory goes.
|
▼この種のエッセイを読むと、つい「要するに筆者が言いたいのは・・・」とまとめたくなるのですが、リードビーターのこのエッセイに関する限り簡単にまとめることなどできない。彼は認知症対策について語っているというよりも、「人間とは何か」ということを認知症に関連して語ろうとしているように思える。もうちょっと正確に言うと「人間とは何か」を語ったり、考えたりするときに我々がとるべき姿勢について語っているように思えるわけです。それは「われ思う、故にわれあり」というような抽象的かつ個人的な世界ではなくて、世の中と関わりながら生きている人間(夫・妻・教師・運転手・・・)であり、美しい音楽を聴けば嬉しくなり、美味しいものを食べれば幸せを感じる etc という具体的な人間です。
▼ただ筆者の主張ではっきりしていると思うのは「認知症対策」という名目で、人間の脳そのものに手をつけて別の人間を作り出そうとすることへの拒否であり、認知症でない人間が考えついた「記憶テスト」のようなもので人間を判断しようとすることへの疑問です。『アリスのままで』という映画の主人公は「自分が見つからない」(I
cannot find myself)と言いながらも、「苦しんでいるのではない」(I am not suffering)と言い、「この瞬間に生きる」(live
in the moment)と自分に言い聞かせている・・・そのような人間が暮らしやすさを感じる環境を作ろうと提案している。つまり認知症であろうがなかろうが、誰にとっても生きていきやすい環境を、というのが「公共政策アドバイザー」としてのリードビーターの提案なのかもしれませんね。
|
| むささびジャーナルの関連記事 |
認知症に優しい町づくり
認知症チャレンジ:「心の付き添い犬」育成計画 |
|
| back to top |
6) どうでも英和辞書
|
| A-Zの総合索引はこちら |
 |
daylight hours:日照時間
今年は6月22日(月曜日)が夏至でしたね。日照時間が1年で最も長い日。6月22日を境目にだんだん日が短くなっていく。夏至のことを英語では "summer solstice" というのだそうです。
ところで日照時間で思い出すのはイスラム教のラマダン(断食月)のことですね。いつこれが行われるのかは年によって違うけれど、今年は6月18日~7月18日なのだそうです。つまり現在、イスラム教徒の皆さんは「断食」の真っ只中というわけですが、まさか全くの飲まず食わずではない。食べ物と飲み物が断たれるのは「日の出から日没まで」です。多くのイスラム教徒は日の出前と日没後に食事をとる。
当たり前ですが、場所によって日の出と日没の時間が違いますよね。The Economistのサイトによると2015年のラマダン開始日の6月18日、世界最大のイスラム国であるインドネシア(2億9200万人)のジャカルタの日の出時間は午前6時、日没は午後5時46分だった。ということはジャカルタのイスラム教徒の皆さんはその日、11時間46分飲まず食わずであったわけです。世界で2番目にイスラム教徒が多いインド(1億7630万人)の場合、日の出はインドネシアと同じ午前6時だったけれど、日没が午後8時16分だったから、断食時間は13時間16分だった。
イスラム教徒は世界中にいますよね。北欧などは夏の日照時間がかなり長いから「断食」もタイヘンでしょうね。例えばスウェーデンには約40万人のイスラム教徒が暮らしていますが、ラマダン開始の6月18日、日の出は午前3時半、日の入りは午後の10時(!)だった、ということは断食時間は18時間36分ということに。これはきついでしょうね。でもこれで驚いてはいけませんよ。アイスランドの場合、イスラム人口は約1000人なのですが、6月18日の断食時間は「ほぼ22時間」(almost 22 hours)であったそうであります。「それじゃぁ飢え死にする!」と思いません?ご安心ください、ヨーロッパのイスラム教徒については聖地メッカの日の出・日没時間に従っても結構という決まりがあるのだそうです。これだと12時間の断食ですむのだそうであります。
ちなみに(ウィキペディアによると)昨年のラマダンは6月30日からの1ヶ月であったのですが、その日、アイスランドの首都・レイキャビクの日の出時間は午前1時34分、日の入りは午前0時02分、合計すると日照時間は22時間28分ということになるのであります。 |
| back to top |
7) むささびの鳴き声
|
▼一番目に掲載した”「沖縄慰霊の日」の伝わり方”のところで、慰霊の挨拶をする安倍さんに向かって「戦争屋!」と野次ってくれた那覇市の82才に感謝すると同時にこの人のコメントを掲載した琉球新報のことを(むささびが)激賞しています。その部分を書いていたら、何とかいう作家(?)が「沖縄の新聞など潰してしまえばよろしい」と述べたというニュースが伝わってきました。これには笑えましたね。むささびジャーナル297号で、日本の地方紙の普及率という記事を掲載しています。参考にしたのはいまから8年ほど前のFACTAという雑誌に出ていた情報です。
▼それによると、沖縄における「沖縄タイムス」の世帯普及率は41.3%、「琉球新報」のそれは38.6%となっている。こと新聞に関する限り、ほとんどの家庭がこのどちらかを購読しているということですよね。他の新聞(全国紙)はどうか?普及率が最も高い全国紙は日本経済新聞で0.8%というのだから素晴らしいじゃありませんか?日経以外ですか?ホントに聞きたい?朝日が0.3%、毎日と読売が0.1%、産経は0.0%です。
▼「普及率」なんて言われてもピンと来ない方のためにあえて発行部数を申し上げますと、沖縄タイムスと琉球新報がそれぞれ20万部ずつ、全国紙は全部足しても(笑ってはいけない)7000部にも届かない。もちろんこれは8年も前の数字です。いまではもっと全国紙が普及しているかもしれないけれど、「40万部vs7000部」はなかなかひっくり返せないよね。沖縄で「タイムス」と「新報」を潰すということは、沖縄から新聞そのものをなくしてしまえと言っているのと同じこと。「沖縄の新聞を潰せばいい」と言った作家さんは、どうやって潰せと言っているのでありましょうか?ひょっとして、この2紙は法律で購読禁止とし、どうしても新聞をとりたいのなら全国紙にすることを義務付ける、購読する全国紙によっては政府から補助金を支給するとか?安倍さんならできるんでない?
▼で、もう少しだけ沖縄慰霊の日にこだわると、あの日、安倍さんは沖縄戦で死んだ人びとに対して「謹んで哀悼の誠」を捧げる挨拶をしているのですが、英国メディアときたらそれにはほどんとお構いなしで「野次られた」(heckled)ことだけを伝えている。「ご挨拶」の原稿(和文はここ・英文はここ)を用意したスタッフにしてみれば面白くないでしょうね。というわけで、せめてむささびジャーナルだけでもこれを取り上げてあげようと思うわけ。悪いけど1カ所だけということで・・・。安倍さんは沖縄戦について、美しい沖縄が一挙に「修羅の巷」となり、20万人もの人命が奪われたというわけで、
- 戦火の只中で、多くの夢や希望を抱きながら倒れた若者たち、子どもの無事を願いつつ命を落とした父や母たち。平和の礎に刻まれた多くの戦没者の方々が、家族の行く末を案じつつ、無念にも犠牲となられたことを思うとき、胸塞がる気持ちを禁じ得ません。
と言っている。
▼最後の「胸塞がる気持ちを禁じ得ません」の部分は、英文では "it pains me greatly" となっています。何だか虫歯に苦しんでいる人のような言葉ですね。すでにさんざ報道されているけれど、命を失った20万人の内訳は(沖縄県平和祈念資料館によると)日本人が約19万、アメリカ人が約1万3000人。日本人19万のうち沖縄出身者は約12万なのですが、その12万のうち9万4000人が「一般人」なのですね。なぜ軍人でもない人たちがそんなにたくさん亡くなったのか?(これもさんざ報道されていることですが)多くの一般人が日本軍から「投降してはならぬ」と言われたり、防空壕に日本の軍人と隠れていて、赤ん坊が泣き出して日本の軍人に殺されたり(泣き声が米軍に聞こえるとまずいという理由)etcということですよね。これらの日本軍人のトップにいた人たちが靖国に祀られており、安倍さんは彼らに敬意を表したいと言っている。その人が「胸塞がる気持ちを禁じ得ません」だの
"it pains me greatly" とか言ったって、あまりにも白々しい・・・そんなことはガイジン記者にだって分かる。
▼くどくて悪いけど、むささびははるか昔に「広報」という仕事をしておりました。PRですな。その立場から言うと、安倍さんの外国メディア担当広報官の気持ちは複雑でしょうね。せっかく"it
pains me greatly"とか言って平和愛好者としてのボスを売り込んだつもりなのに「戦争屋」呼ばわりされたことしか記事にならないなんて・・・。ただ、広報担当の口癖の一つとして
"any PR is better than no PR" というのもある。とりあえず報道されたのは、無視されるよりはマシだよねってことかもね。
▼最後に龍谷大学の松島泰勝教授が6月2日に日本記者クラブで会見をしたのですね。テーマは『沖縄は日本の植民地 だから独立を目指す』で、ここをクリックすると超簡単な会見の内容が出ています。この人は『琉球独立論』という本の著者でもある。少なくとも沖縄の新聞壊滅論を語っている作家さんよりはマシなんでない!? |
|
| back to top |
| ←前の号 次の号→ |
 |
| むささびへの伝言 |
![]()
