8月15日も過ぎて、空の高さとか雲の形など、関東地方には(かすかとはいえ)ようやく秋の臭いがしてきました。毎年、この時期になると降ってわいたように「二度と戦争をしてはならない」という言葉がメディアを埋め尽くす。そんなことを73年間も続けた挙句に「戦後レジームからの脱却」という言葉だけを繰り返す人間が首相の座に君臨している・・・彼の気持ちからすると「二度と戦争を・・・」というスローガンも戦後レジームの一環です。
|
目次
1)イングランドからオークが消える!?
2)『近代人の疎外』を再読して
3)「日本人の疎外」を考える
4)英国人は自分を誤解している
5)どうでも英和辞書
6)むささびの鳴き声
むささび俳壇
|
1)イングランドからオークが消える!?
|
 |
ちょっと古い記事ですが、6月27日付のGuardianによると、現在英国・環境省の音頭でイングランド全土に 1100万本の木を植えようというプロジェクトが進められています。その背景には英国ではヨーロッパ大陸などと比較すると余りにも森林面積が少なく、英国内で使われる木材もほとんどが外国からの輸入に頼っているということがある。
|
 |
| イングリッシュオークの葉っぱとドングリ(acorn)。英国には"From little acorn"という一種の格言のようなものがある。「大きなオークの木も始まりは小さなドングリだった」というわけで、「大きなことも最初は小さいのだから我慢してやらなきゃ」といういましめ。 |
|
英国を代表する樹木にオークがあるのですが、今から100~200年も前のビクトリア時代に植えられたオークの木 が現在伐採されて材木として使われている。が、ビクトリア時代から現代にいたるまでは殆ど植樹というものが行なわれてこなかったので間もなくイングランドからオークの姿が消えてしまうのではないかとさえ言われている。
|
陸地に占める森林の割合:2015年 世界銀行
 |
Guardianの記事によると、もともと材木は英国経済にとっては欠かせないものだった。13世紀初頭(1215年)に制定されたマグナカルタには森林所有権(forestry
rights)に関する条文があったし、大英帝国華やかなりし 19世紀の英国海軍の行進曲は“Hearts of Oak”というタイトルだった。さらに第一次世界大戦(1914~ 1918年)の直後には森林庁(Forestry Commission)が出来て住宅建設のための木材確保を目的とした
森林の開発が進められた。
|
 シェフィールど市内の立木の伐採に反対する市民たち
シェフィールど市内の立木の伐採に反対する市民たち |
なのに・・・現在の英国における森林は影の薄い存在になってしまっている。例えば英国全土に占める森林の割合は13%。この数字は森林庁が出来たころの5%に比べれば2倍以上に拡大されているけれど、ヨーロッパの平均である30%には及ばない。また英国で加工される材木は年間約1300万トンとされているけれど、これは必要とされる木材の20%にすぎず、あとはすべて輸入に頼っている。
1100万本の木を植えるというと何やらタイヘンな数のように響くけれど、専門家によると、それに要する面積は4400ヘクタール(44平方キロ)で、ロンドンの面積(ざっと1600平方キロ)の3分の1にも届かない面積であり、実は現在でも年間800ヘクタール相当の植樹が行われているのだそうです。それを思えば1100万本なんて「大海の一滴」(a drop in the ocean)というわけです。
|
 |
森林を増やすについては、土地の持ち主に対する税制上の優遇措置も用意されている。例えば商業目的で植樹する森林には相続税がかからないだけでなく、植える樹木によっては政府からの補助金(ヘクタール当たり3500ポンド)が下りる。ただ植える樹木が将来材木として販売されるのではなく、森の所有者の快適さのみを追求するような木(主として広葉樹)の場合は優遇措置は与えられない。
植林計画を進めるにあたって、まずやらなければならないのが正確な情報収集で、森林率にしても信頼できる情報があまりにも少ないのだそうです。データを集めることさえしていないのだから、英国がおかれた現状そのものがよく分からない。つまり植樹活動をスタートさせたとしても、スタート時点でどの程度の樹木が植わっているのかという基本的な情報がないのだから進捗状況も分からないということになる。
|
 |
ある森林保全についての専門家が特に指摘するのが、都市部における樹木の不足状態。世界的な傾向らしいのですが、都市を覆ってきた木のカバーが不足している(urban canopy cover is declining)のに、これを復活させる適切な政策が採用されてこなかった。都市部における樹木の必要性。シェーフィールドの場合。今年の3月、市内に植えられていた樹木6000本が伐採されそうになった。
植樹活動も重要ながら、現在生えている樹木の保全も欠かせない。となると問題になるのが鉄道の線路に沿って生えている樹木が線路管理のために伐採されていること。実施しているのは線路管理を専門に行っているNetwork Railという会社で、8億ポンドの予算で2万マイル(約3万2000キロ)におよぶ線路に沿って生えている木を伐採する計画を実施することになっている。この計画自体は今のところは政府命令でストップがかかっているのですが、将来どうするのかは分かっていない。
|
 |
樹木については地方自治体の中には頭を悩ませているところがあるのだそうです。例えば北イングランドのシェフィールド(人口:52万)では、6000本の伐採を計画したのですが、住民の反対にあってこれがとん挫している。市当局も優れた住環境の維持という意味からも樹木の重要性は認めているのですが、伐採対象の6000本はいずれも交通や歩行の妨げになっているものばかりで、これを切るのは住民のためだと主張している。Guardianの記事によると、交通の妨げになっていることが分かっていながら伐採を怠ると、その樹木が原因で事故が起こった際には市が損害賠償で訴えられる可能性もある、となると財政逼迫の折から「今のうちに伐採を」ということになって、揉めているのだそうです。
|
▼個人的な思い出ですが、むささびは、昔(2002年)イングリッシュオークの苗木を日本国内に植樹する活動(日英グリーン同盟)に関わったことがあります。日本全国約200か所の町や村に英国から運んできたオークの苗木(背丈はざっと1メートル)を植えてもらいました。あれから16年、それぞれのオークはどうなっているのか・・・。自然が相手ですから無事に育つという保障など何もない。
|
 |
▼上の写真は英国の棺桶です。今から100年以上前のことですが、北海道のナラの木から作った板が盛んに英国に輸出されて棺桶用の材料に使われた。オークは日本でいうとナラの木です。日本産のナラから作った板は弾力性に富んでいて棺桶用の材料に向いていたのだそうです。写真の棺桶の丸い部分を作るためには弾力性に富んだ板が必要だったということ。この話は日英グリーン同盟に参加した北海道砂川市の関係者から聞きました。記録によると2002年5月19日に砂川市内の北光公園というところにオークが植えられています。無事に育ってくれていると嬉しいのですが・・・。 |
|
back to top |
2)『近代人の疎外』を再読して
|
|
|
back to top |
3)「日本人の疎外」を考える
|
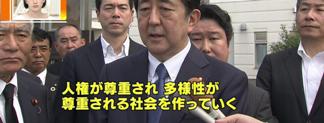
|
『近代人の疎外』という本にむささびが最初に接触したのは1960年代のことです。「疎外」という現象について、いまいち分かったような分からないような、という情けない読後感しか持てなかった。あれから50年以上経った現在、再読してみたわけです。著者であるパッペンハイムのメッセージをむささびなりに解釈してまとめると次のようになる。
|
- 人間の歴史は、地縁・血縁・階級などが基盤となる共同体的な社会(ゲマインシャフト)から個人による自己利益の追求が基盤となる打算的な社会(ゲゼルシャフト)へと「進歩」した。
- ゲゼルシャフト的な社会では人間の価値を商品の価値を決めるような尺度で判断しようとするので、そのことによる疎外(人間が人間でないような感覚)が生じる。
- 疎外を克服する闘いの結果、疎外が克服された社会が到来する可能性はあるが、そこでは別の種類の疎外現象が待っていることは考えられる。
- しかしそれでも現在直面している疎外を克服するための闘いは止めるべきではない。
|
|
 |
あの頃の日本
この本は基本的に1950~60年代の欧米社会について語っているのですが、むささびがこれを読んだ60年代の日本は、パッペンハイムが言うような「打算的ゲゼルシャフト社会」だったのだろうか?資本主義社会であったことは間違いないけれど、労働組合の力は強かったし、終身雇用も当たり前というわけで、どちらかというとゲマインシャフトのような雰囲気の世の中だったのではないか?それが1990年代に入って「親方日の丸」の官僚主義の非効率性が批判され、民営化や規制緩和路線が主流となるに従ってゲゼルシャフト的な世の中になったのは、この30年ほどのことのような気がしません?1960年代には考えてもみなかった「非正規雇用」だの「契約社員」などが当たり前の世の中になっているわけですから。
相模原事件と疎外
その「ゲゼルシャフト的日本」で2016年7月に起こったのが相模原の障害者施設殺傷事件だった。あの事件についてむささびは記事を二つ載せています。一つは事件直後の351号に出ている「相模原事件:福島教授が感じたこと」という記事で、ポイントは東大の福島智教授の次のコメントです。
- (この事件は)今の日本をおおう「新自由主義的な人間観」と無縁ではないでしょう。人間を労働力の担い手としての経済的価値や生産能力で価値付け、序列化する社会では、重度の障害者の生存は、本質的には軽視され、究極的には否定されます。
福島教授のいう「人間が経済的価値にもとづいて序列化される社会」こそが『近代人の疎外』でいうゲゼルシャフト社会ですよね。教授はまたそのような日本社会について、「人間の存在意義の軽視・否定の論理とメカニズム」が支配する社会であり、ひとにぎりの「勝者」「強者」だけが報われる社会になっていると表現しています。
|
 |
「生産性」という圧力
相模原の事件については、むささびジャーナル388号の<「生き辛さ」が引かせた「一線」>という記事で紹介した北九州の牧師、奥田知志さんも現代の日本には「何も生産しない人間には存在価値がないという発想が生む圧力」が潜んでおり、それがあの容疑者を押し潰したと言っている。福島教授と全く同じことを言っているわけですが、力点がほんの少し異なるように(むささびには)響く。福島教授が命を奪われた障害者の側に立っているのに対して、奥田さんはそのような凶行に走った容疑者の心理について考えている。 |
 |
奥田牧師はまたごく最近(7月29日)の教会(北九州・東八幡教会)のサイトに『生産性の暴論に終止符を』というエッセイを載せています。このエッセイで取り上げられたのは「LGBTには生産性がない」と言った杉田水脈とかいう国会議員のことです。牧師によると、この議員も相模原事件の容疑者も「生産性」を基準に人間の価値を決めることが正しいと確信している点で共通している。両方とも自分のやったこと言ったことが正しいと思っている「確信犯」ということです。杉田議員が『新潮45』に投稿したエッセイの中の問題の部分だけ取り出すと次のようになる。
| 例えば、子育て支援や子供ができないカップルへの不妊治療に税金を使うというのであれば、少子化対策のためにお金を使うという大義名分があります。しかし、LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女たちは子供を作らない、つまり「生産性」がないのです。そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか。にもかかわらず、行政がLGBTに関する条例や要項を発表するたびにもてはやすマスコミがいるから、政治家が人気とり政策になると勘違いしてしまうのです。
|
| ▼この文章で杉田議員が使っている「大義名分」、「賛同が得られる・・・」、「税金を投入」、「果たしていいのかどうか」などの表現に、この人(だけではないかも)の幼稚さを見る思いがしません?どれもいわゆる「政治家」の世界で当たり前に使われているものです。それらを彼女(51才)が使用して自分も政治家になったつもりでいる・・・人まねを平気で(それと思わずに)やってしまう幼稚さです。 |
|
 |
「いのちに意味がある」
そもそも生産性とは何なのか?奥田牧師の地元に「ホームレスの自立支援センター」を作ろうとしたときに、近隣住民による反対運動が起こった。反対派の言い分は「(ホームレス支援のような)生産性の低い施設を配置するよりももっと高生産性の施設を作って欲しい」というものだった。その施設は反対を押し切って開所され、これまでに1000人以上のホームレスが生活を取り戻したのだそうです。そのような数の人びとが通常の生活に戻ることができたのだから、そのセンターの「生産性」は極めて高いと言えるのでは?
杉田議員によると、LGBTは「子供を作らない=少子化対策の役に立たない=非生産的」というわけですが、奥田牧師によると、LGBTであるが故の差別に対して抗議の声を上げるLGBTの姿に共感を覚え、生きる力を与えられたと感じる人がたくさんいる。そのような人びとを生み出しているという意味ではLGBTも大いに「生産的」であると言える。しかし奥田牧師は「そういう言い方もよくないのだろう」と言います。それらのLGBTが「多くの人びとに生きる意味を教えているから価値がある」という発想では、杉田議員のような暴論に勝つことはできない。つまり
- 「生産性の暴論」に最終的に打ち勝つのは「いのちに意味がある」と断言することしかない。この普遍的な価値を取り戻せるかが勝負となる。
ということであります。
|
 |
人間は人間であることにおいて価値がある(生産性の有無など関係ない)・・・そのことを「断言する」という牧師の言葉に『近代人の疎外』でパッペンハイムが使った、疎外克服のための「闘いを止めてはならない」という言葉との共通点を(むささびは)見るのであります。 |
▼26才だった相模原事件の容疑者は、あの施設に職を得るまでは仕事もしないで生活保護を受けながら生きていた。奥田牧師の想像によると、あの若者を狂気に追い込んだのは「何も生産しない人間には存在価値がないという発想が生む圧力」です。「自分には存在価値がない」という思い込みが「障害者には存在価値がない」という思い込みに繋がった。そして障害者を抹殺することで自分にも存在価値があると思い込もうとした。
▼もう一方の確信犯、杉田議員はどうか?子供ができない夫婦の不妊治療を政府が援助するのはオーケー(大義名分がある)であるけれど、最初から子供を作る気もないLGBTのために税金を使う必要はないと言っている。その人たちが納税者であったとしても彼らには納税者としての権利を主張する資格はない・・・と杉田議員は言っている(とむささびは解釈する)。
▼(むささびは)ここ30年ほどの間に日本もゲゼルシャフトになったと言ったけれど、ひょっとするとその見方は間違っているかもしれない。人間を商品扱いするのがゲゼルシャフトではあるけれど、そこでは少なくともお互いが自己利益を追求することが奨励されている。杉田議員のような発想は「自己利益の追求」を奨励するというよりも「日本という国家の役に立つ人間であること」を奨励するものですよね。国家は過去も現在もゲマインシャフト社会なのですよね。基盤となるのは自己利益を追求する個人ではない。国家の役に立つ人間です。LGBTは役に立たない・・・杉田議員のような存在は相模原事件の容疑者よりも質(たち)が悪い。何故なら彼らには税金の使い道を決める権力が与えられているから。そしてこの議員にその権力を与えたのは(情けないけれど)日本の選挙民です。
▼もちろん現代の日本にゲゼルシャフト的な要素が強く存在するのは本当ですが、それは(例えば)地元が経済的に潤うのならカジノを作ることが奨励されるのは当たり前だという発想です。シンゾーは国家中心主義という意味ではゲマインシャフト人間であるけれど、とにかく儲かればいいという意味ではゲゼルシャフト人間です。過去と現代の疎外要因を両方とも持ち合わせている・・・あるいはアタマの中は空っぽでゲマインもゲゼルも関係ないのかも? |
|
|
back to top |
4)英国人は自分たちを誤解している
|
 |
|
|
8月9日付のThe Economistの政治コラムが英国人の国民性について語っているのですが、イントロが次のようになっている。
- It’s time to rethink everything we thought we knew about British national character
自分たちが英国人の国民性だと思っていたものについて、何もかも考え直す時に来ている
「自分で自分のことを誤解していた」と言っているのですよね。何を誤解していたのか?
- More than most people the British pride themselves on being sensible.
英国人は他国民に比べると自分たちが「賢明」であることを誇りにしている。
保守的で革命嫌い?
キーワードは"sensible"です。辞書的には「賢明な」という意味ですが、もう少し具体的にいうと、英国人は「思想より実践」(prefer
pragmatism to ideology)、「極端より中庸」(moderation to extremism)、「変化より継続」(continuity
to change)を好む国民性ということです。フランス人のようにxx主義を振りかざすような頭でっかちではないし、アメリカ人のように狂信的個人主義でもない・・・良くも悪くも慎重で保守的な国民性ということですよね。むささびは英国人のキャラクターはそのようなものであると思っていました。が、それが違うらしい。
- 昨今の政治の世界を見ていると、英国人が「賢明」だという見方には疑問を抱かざるを得ない。
The notion that the British are above all sensible makes the current state of politics even more confusing.
とのことであります。
|
 |
例えば訳も分からない状態でBREXITの暗闇に飛び込んでしまったこと、労働党が(ジェレミー・コービンという)過激人間を党首に選んでしまったこと、これまで外務大臣まで務めた人間(ボリス・ジョンソン)がブルカというイスラム文化独特の衣服を身に着けた女性を「郵便ポスト」や「銀行強盗」呼ばわりしたり etc・・・とても「賢明な国」とは思えない出来事が相次いでいる。
| ▼過激派・反戦論者のコービンについてはここをクリックすると出ています。ボリス・ジョンソンのブルカ問題については、日本のメディアではどの程度話題になったのか、よく分からないけれど、BBC日本語版の報道はここをクリックすると出ています。 |
20世紀の英国
一体どうなっとるんだ?というわけですが、その疑問に対する一つの答えは、英国人が「慎重で保守的」などと考えるのが間違っている、英国人が自分自身を誤解している、「賢明なる英国人」は、漸進主義を望み革命的変化は望まないことになっているけれど、果たして英国人は「賢明」な人間たちなのか?と疑問を呈しているわけですよね。 |
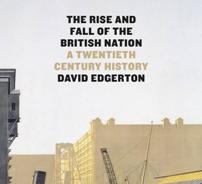 |
キングス・カレッジのデイビッド・エジャトン(David Edgerton)教授が最近書いた“The Rise and Fall of the British Nation”(国家としての英国の盛衰)という本によると、20世紀の英国は「漸進」どころか、混乱と革命(rupture and revolution)に明け暮れていた。1900年頃の英国は製造産業が世界のトップを走っており、軍艦、武器などを幅広く輸出していた。また石炭産業に100万人の労働者が従事するなどエネルギー供給国としても世界一だった。さらにその頃の英国に特徴的だったのは中央よりも地方が強かったことで、公共事業の多くが地方政府もしくはボランティア組織によって進められていた。つまり「小さな政府」の国だった。
アトリーからサッチャーへ
事情が激変したのは第二次大戦が終わった1945年だった。労働党のアトリー政権が誕生してからは製造業の強さに変化はなかったものの、かつての小さな政府や自由貿易に代わって中央集権的な政府が登場した。福祉国家・英国が誕生したのもこの頃であり、石炭・鉄道・鉄鋼・ガス・電気など主要産業はどれも国営化され、たくさんの公営住宅(council houses)が作られたのもこの頃だった。その頃の英国人の8割が自分たちのことを「労働者階級」(working class)と呼んでおり、1950年代に入ってその多くが製造業で働くようになっていた。
|
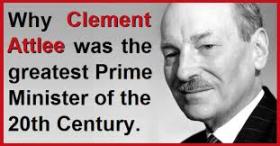 |
そのような英国をさらに変えてしまったのがサッチャーだった。彼女の登場によって1980年代の英国はアトリー流の「大きな政府」におさらばして、かつてのような自由放任・小さな政府の国となった。産業的にも製造業よりもサービス産業(特に金融業)の振興に力が入れられた。鉄道・鉄鋼・ガス・電気等々、あらゆる産業の民営化が進んだのも80年代のことだった。それと同時に「脱工業化」(de-industrialisation)が叫ばれ、その中でかつては盛んだった「労働者階級の文化」(working-class culture)が衰退していった。
英国人は思想で動く?
それにしてもなぜそのような急激な変化が可能だったのだろう?という疑問に対する答えは、
- 英国人が自分たちが思っている以上にプラグマティック(現実的)というよりも「思想的」な国民だったのだ
the British are more ideological and less pragmatic than they like to think.
ということになる。 |
 |
民営化や脱工業化政策を推進するサッチャーが度々に口にしたのが、ハイエク(Friedrich Hayek)だのフリードマン(Milton Friedman)のような経済学者の「理論」だった。サッチャー以上に「思想的」だったのがトニー・ブレアで、労働党政権(1997年~2010年)であるにもかかわらず、自由市場経済を推進する一方で東欧からの移民受け入れのようなリベラルとされる政策に力を入れるという「ダブル・リベラリズム」の姿勢をとった。ブレアは移民奨励策に伴うコストと利点を秤にかけて損得を考えるというよりも、移民奨励を善悪という価値観の問題として扱ってしまった。
大学は最高、職業訓練は最低
サッチャーやブレアの姿勢を見ていると、英国が「中庸を尊ぶ国」(essentially moderate country)などとはとても言えず、常に内部分裂や血なまぐさい抗争に明け暮れる国であったともいえる。教育の面でいうと、英国は世界に冠たるエリート教育を誇る一方で、職業教育(vocational
education)の点では世界でも最低の国の一つとなっている。ロンドンの金融街(シティ)と言えば世界の資本主義のメッカであることは確かであるけれど、英国の国民保健制度(NHS)は最も社会主義的な制度であることも間違いない。ロンドンという世界屈指の豊かな国際都市を抱える一方で、英国にはブラックプールのような「見捨てられた町」(capital
of marginalisation)もある。ブラックプールでは妊婦の喫煙率が26%(ロンドンの中心部では2%)もあるし、男性の平均寿命がロンドン(ケンジントン)のそれよりも9年も短い。
|
 |
これらの極端現象が意味していることが二つある。一つは長年にわたって政治の世界の常識となってきたはずの「英国的な賢明さ」(British sensibleness)というものは忘れた方がいいということ。
今は革命期なのだ
もう一つ、英国人はこの国が間もなく「正常」(保守的で中庸を尊ぶ国)に戻るなどということを夢想しない方がいいということ。現在の英国はあのアトリー時代(1940年代)やサッチャー時代(1980年代)のような革命的とも言える変化の時期の真っただ中にいるのだということを理解すること。ただ・・・
- かつての変革期と現在の違いは、現在の英国には、変革期にふさわしい政治指導者を輩出する能力に欠ける(ように思える)ということだ。かつてのクレメント・アトリーやマーガレット・サッチャーに代わって今我々の目の前に立っているのはジェレミー・コービンとティリサ・メイなのだ。
The big difference is that Britain no longer seems capable of producing political leaders worthy of revolutionary times. In place of Attlee and Thatcher now stand Mr Corbyn and Theresa May.
というのが、このコラムの結びです。 |
▼つまり変革期であるにしては、指導者がジェレミー・コービンとティリーザ・メイでは余りにも心もとない、と嘆いているわけですよね。終戦直後の選挙では、あのウィンストン・チャーチルが率いる保守党が名もなきアトリー率いる労働党に敗れた。英国を戦争勝利に導いたヒーローのチャーチルが敗れるなんて、政治的エリートの世界では誰も考えていなかった。最大の誤算は、あの当時の英国人の間に広がっていた「厭戦気分」に気が付かなかったということだった。
▼「気が付かなかった」といえば、2年前のBREXITも同じです。結果からすると、かつての「労働者階級」の支持なしにBREXITはあり得なかった。「かつての」というのは、トニー・ブレアが「新労働党」(New
Labour)として「第三の道」なるものを歩み始めたときに「古臭い」と批判されて冷や飯を食った左派系の労働党員やそれを支持する北イングランドの製造業の労働者たちです。まさか彼らが右翼的なBREXITの側にまわるなんて、キャメロン首相(当時)も彼を支持していた労働党の右派グループも、そしてEU離脱を主張したグループでさえも気が付かなかった。
▼厭戦気分の英国人に福祉国家を提案したのがアトリー、労組の「横暴」にうんざりしていた英国人に「金儲けの自由」を訴えたのがサッチャー、その自己利益追求主義に対抗してボランティアリズムを提唱したのがブレアという具合に、それぞれの時点でその時代にふさわしい考え方が提案されてきた。EUを離脱したあとの英国に草の根労働者階級が何を期待しているのか?むささびの推測によると、何も期待していない・・・はっきり言って「EU離脱は誤っていた」という気持ちがあるだけ。そのような英国人に何らかの希望を提供するようなリーダーが登場するのか?確かに難しいとは思うけれど、あえて言えば労働党左派の中の親EU的な感覚を有する人間ということになるのでしょうね。 |
|
back to top |
5) どうでも英和辞書
|
| A-Zの総合索引はこちら |
 |
liveability:暮らしやすさ
The Economist誌の姉妹組織であるThe Economist Intelligence Unit (EIU) が毎年発表している「世界の暮らしやすい町ランキング」(Global Liveability Index)の2018年版が発表されました。このランキングはかなり権威があるとみえて、BBC、CNNなどいろいろなメディアが取り上げています。全部で140の都市をさまざまな要素(住環境・犯罪率・インフラ・教育・文化等々)ごとに点数をつけて比較するものです。
2018年版のトップ(つまり世界一暮らしやすい町)はどこだと思います?オーストリアの首都・ウィーンです。実は昨年までの7年間で連続トップの座を守っていたのがオーストラリアのメルボルンで、ウィーンは常に2番目だった。それが今年はメルボルンが第2位となったということです。
むささびにとって(失礼ながら)意外だったのは第3位の町です。大阪。そう日本のあの大阪でんがな。大阪の何が評価されたのか?EIUによると「公共交通機関の充実」と「犯罪率の低下」だそうで「大都会としての安定感」が際立っているとのことであります。ついでに(と言っては失礼か?)言っておくと、東京が第7位に入っている。
|
| Global Liveability Index 2018 |
1. Vienna
2. Melbourne
3. Osaka
4. Calgary
5. Sydney
6. Vancouver
7. Tokyo
7. Toronto
9. Copenhagen
9. Adelaide |
50. Los Angeles
52. Cleveland
53. Detroit
54. Lisbon
55. Rome
56. Houston
57. New York
58. Taipei
59. Seoul
60. Prague |
101. BS Begawan
102. Asuncion
103. Manila
104. Baku
105. Quito
106. Tunis
107. Hanoi
108. Bogota
108. Istanbul
108. Riyadh |
11. Zurich
12. Auckland
12. Frankfurt
14. Geneva
14. Perth
16. Helsinki
17. Amsterdam
18. Hamburg
19. Montreal
19. Paris |
61. Lexington
62. Buenos Aires
63. Santiago
64. Bratislava
65. Warsaw
66. Noumea
67. Montevideo
68. Moscow
69. Dubai
70. St Petersburg |
111. Mexico C.
112. New Delhi
113. Jeddah
114. Guatemala C.
115. Casablanca
116. Ho Chi Minh C.
117. Mumbai
118. Kiev
119. Jakarta
120. Al Khobar |
21. Berlin
22. Brisbane
23. Honolulu
24. Luxembourg
25. Munich
26. Wellington
27. Oslo
28. Dusseldorf
29. Brussels
30. Barcelona |
71. Abu Dhabi
72. Athens
73. San Jose
74. Suzhou
75. Beijing
76. Tel Aviv
77. Tianjin
78. Kuala Lumpur
79. Sofia
80. Lima |
121. Tashkent
122. Nairobi
123. Cairo
124. Abidjan
125. Phnom Penh
126. Caracas
127. Lusaka
128. Tehran
129. Kathmandu
130. Colombo |
30. Lyon
32. Pittsburgh
32. Stockholm
34. Budapest
35. Hong Kong
35. Manchester
37. Singapore
37. Washington DC
39. Madrid
39. Minneapolis |
81. Shanghai
82. Belgrade
82. Bucharest
82. Shenzhen
85. Kuwait C.
86. Johannesburg
87. Doha
88. Rio de Janeiro
89. San Juan
90. Dalian |
131. Dakar
132. Algiers
133. Douala
134. Tripoli
135. Harare
136. Port Moresby
137 Karachi
138. Lagos
139. Dhaka
140. Damascus |
41. Dublin
42. Boston
43. Reykjavik
44. Chicago
44. Miami
46. Milan
46. Seattle
48. London
49. San Francisco
50. Atlanta |
90. Muscat
92. Pretoria
93. Sao Paulo
94. Bahrain
95. Guangzhou
96. Panama C.
97. Qingdao
98. Amman
98. Bangkok
100. Almaty |
|
| back to top |
6)むささびの鳴き声
|
▼今年も8月15日が終わりました。むささびがこの時期のメディア報道にウンザリを通り越して、ほとんど不愉快な気分を持つようになったのはいつ頃のことだったか。新聞も放送も「もう二度と戦争をしてはならない」というメッセージを伝える企画でいっぱいになる。どれを聴いても読んでも真面目なメッセージであることは疑いがない、にもかかわらずウンザリ感を強く持ってしまう。例えば8月14日付の毎日新聞のサイトに出ている『終戦73年 狂気二度と 宮崎の元特攻隊員、不戦願い手記』という記事。終戦時に特攻隊員だったけれど出撃は免れた人が「自分の命も自分のものでなく、自由にならなかった時代だった。二度とそういう時代をつくってはならない」という思いから手記を綴っているというものです。この記事を読んで、その元特攻隊員の想いに疑問を挟む人はいないと思う。
▼同じ日の毎日新聞には、神戸の大空襲で重傷を負った女性(89才)が「戦争は残酷、罪深い」と訴える記事が載っているし、90才になる「元軍属」という男性が、終戦時に懇意にしていた軍人から集団自決に加わるように誘われてこれを断ったことに未だに自責の念にかられているというストーリーも。8月になるとこの種の報道がメディアを埋め尽くす(ようにむささびには感じられる)。そのどれもが「二度と戦争は・・・」と訴える当事者のメッセージで結びとなる。むささびを含めて、誰もそれに異論を唱える者はない。なのにむささびがウンザリするのは何故なのか?おそらくこれらの終戦特集企画がメディアの世界の「年中行事」となってしまっていることが理由なのではないか?「毎年この時期にはこの番組をやらなきゃ」というわけで「何故やるのか?」は考えるまでもない。「大みそかだから紅白歌合戦を」と同じです。
▼「戦争はこりごりだ」という経験者に沖縄の現在について意見を求めたことはあるのか?「二度と戦争をやってはいけない」と言っていた桂歌丸と「日米安保」について話をしたことは?『報道特集』で自らの戦争体験を語っていた芸能人は、憲法を改正しようと言う政治家(シンゾーのこと)をどのように思うのかを聞いたことは?おそらくそのどれもが「アタシらには難しいから・・・」という答えしか得られないかもしれない。しかし誰もが選挙では投票をするわけです。分からないなりにも、政治との関わりは持たざるを得ないわけだから、そなりの言葉を発することは可能です。メディアがそれをさせない・・・とむささびは疑っている。なぜさせないのか?それをやると番組自体が「政治的」になってしまうことを怖れるから。「戦争はこりごり」という言葉自体が実は相当に政治的なものなのに、です。
▼4つ目に掲載した「英国の国民性」の記事に関連して言うと、日本人は「戦争はこりごりだ」と言いながら73年を過ごし、いま「戦後レジームからの脱却」(即ち憲法改正)という言葉を金科玉条のように繰り返す人間を首相に据えても平気な人間になってしまったということですよね。「長いものに巻かれる」という生存本能が国民性になってしまった。そしてその責任の一端は、メディアによって年中行事化した「戦争は二度とやってはいけない」特集にある・・・と言いたいわけ。
▼むささびの想像によると、いずれはBREXITのようなことが日本にも起こる。JAPEXITとか言って・・・。アメリカ体制からの独立志向です。一方では「あの明治維新に帰ろう!」という熱病、もう一方には「平和憲法は守ろう」という常識・良識(sensible)志向がある。前者の熱病患者についていうと、sensible人間はこれと対決するっきゃない。出て行ってもらうしかない。問題は現在の日本にBREXITを実現させたような疎外人間がどの程度いるのかということ。「LGBTには生産性がない」という暴論に心ひそかに拍手を送る人間がどの程度いるのか?(奥田牧師の言葉を借りると)そのような発想は「ダメなものはダメ」(No
is no is no)と「断言する」こと。
▼今朝6時に起きたら外の気温は18度でした。お元気で! |
|
back to top |
←前の号 次の号→ |
 |
| むささびへの伝言 |
