1)ハエの脳はバカにできない
|
 |
食卓にとまっているハエをハエ叩きでやっつけようとしても逃げられるなんてことはしょっちゅうありますよね。当方としてはかなりの速度でしかも正確に叩いているつもりなのに、です。ダブリンにあるトリニティ・カレッジのケビン・ヒーリー(Kevin
Healy)という動物学の教授を中心とする研究チームがAnimal Behaviourという専門誌に発表した論文によると、ハエのような小動物はモノの動きを、人間的感覚からするとスローモーションで見るのだそうです。私が振り下ろすハエ叩きの動きがスローモーションで見えるのだから一撃を避ける可能性が(例えば)人間などよりははるかに高いということです。9月15日付のBBCのサイトに出ていました。
スローモーションで見えるというのを別の方法で言うと、眼が物体の動きを捉えてその情報を脳に送り、脳がこれを解析して「避ける」という動きにつなげる・・・このプロセスが速いという意味でもありますね。ヒーリー教授らの研究によると、ハエの眼が物体の動きを識別する速度は人間の眼の4倍ほどなのだそうです。かないっこない。この種の識別速度は身体の小さい動物ほど速く、象のような大きな動物は全く反対で、ゆっくりした物体の動きもフィルムの早送りのように見えるので、小動物が捉える物体も捉えられないということが起こる。
ところで、人間も含めた生き物が、動いているものを識別する能力を客観的に比較する尺度の一つに「臨界フリッカー融合頻度」(critical flicker-fusion
frequency:CFF)というものがあるのだそうです。点滅する光を見ていると、点滅が速くなればなるほど繋がって見える(点灯状態)ようになる。人間の場合、普通の人は1秒間に60回の点滅が限度なのだとか。CFFの世界ではこれを周波数で表して「60ヘルツ」と言う。犬の場合は80ヘルツが平均らしい。つまり1秒間に80回点滅してもそれを「点滅」として捉えることが出来るということです。それに引きかえ、深海で暮らすIsopodというカブトムシ風の生き物の場合は1秒間に4回の点滅以上はすべて「点灯」に見えてしまう。CFFが4ヘルツというわけです。
ヒーリー教授のチームはさまざまな生き物のCFFを比較しているのですが、CFFの周波数が最も高い部類に入るのは、リスとハト(pigeon)で、golden
mantled ground squirrelと呼ばれる種類のリスなどはCFFが120ヘルツ、ハトは100ヘルツです。つまりリスの場合、1秒間にライトが120回点いたり消えたりしてもそれぞれを識別できる・・・ということは相当に素早い敵の動きでも目で確認できるということになる。反対に一番CFF周波数が最も低い部類に入るのは、ヨーロッパウナギ(14ヘルツ)、オサガメ(15ヘルツ)、ハナグロザメ(18ヘルツ)などとなっています。ちょっと可笑しいのは
tiger beetleというカブトムシで、走ることは速いけれど、CFFがそれに追いついていかず速く走り過ぎて一瞬盲目状態に陥ることがある。そんな時はいったん停止して自分を襲うかもしれない敵の位置を確かめるのだそうです。
今回の研究に参加したセント・アンドリュース大学のグレーム・ラクストン(Graeme Ruxton)が面白いコメントを残しています。
- 人間よりもはるかに高いCFF周波数で、眼が脳に情報を送っても、脳の方でこれを解析する能力がない限り価値はない。この研究が明らかにしたのは、非常に小さな生き物の脳でも素晴らしい情報解析能力を有しているということが分かったということだ。ハエは深い思想家ではないかもしれないが、物事を決定する素早さは素晴らしい。
Having eyes that send updates to the brain at much higher frequencies than our eyes do is of no value if the brain cannot process that information equally quickly. Hence, this work highlights the impressive capabilities of even the smallest animal brains. Flies might not be deep thinkers but they can make good decisions very quickly.
言えてる!
▼小林一茶の俳句に「やれ打つな 蝿が手をする 足をする」というのがあるけれど、実はハエたちは人間の4倍の速さで物体の動きを察知する能力があるのであります。それから宮本武蔵の映画を見ていたら、武蔵が食事をしながら箸でハエをつまんでいるシーンがありました。あんなの本当にありですかね。
▼かつて「ボールが止まって見えた」と言ったのは、ジャイアンツの川上哲治だったと思うけれど、あれって要するに川上さんのCFF周波数が高かったってことですかね!? |
|
back to top
|
2)日本の若者:「就活自殺」の背景
|
 |
知らなかったのですが、9月10日はWHO(世界保健機構)が定める「世界自殺予防デー」(World Suicide Prevention Day)だったのですね。WHOのサイトに、世界105カ国における自殺率の表が出ています。人口10万人あたり何人の自殺者が出ているかという比較ですが、最も多いのがリトアニアの71.7人、次いでロシア(63.4人)、韓国(62人)などが続いています。日本は49.4人でかなり高い方にあります。英国はぐっと少なくて13.9人となっています(いずれも2009年の数字)。
どの国にも共通しているのは、男の自殺率の方が女のそれよりもはるかに高いということで、ロシアなどは男が10万人あたり53.9人なのに女性は9.5人しかいない。ざっと6:1ですね。日本は男が36.2人で女性は13.2人だから、女性の自殺者は男性の3分の1強ということになる。英国は男10.9人に対して女性は3.0人となっています。
その世界自殺予防デーに関連して、NPO自殺対策支援センター・ライフリンクの清水康之代表が、NHKの「視点・論点」という番組で、「"就活自殺"の背景に迫る」というトークを行っています。非常に面白いものだと思います、ご一読を。「就活自殺」というのは、学生が就職活動に失敗する中で絶望して自ら命を絶つことを指します。警察庁の統計によると、2007年には60人であったものが、昨年(2012年)は2・5倍の140人を上回るまでに増えている。清水さんによると、自殺未遂者は実際に亡くなる人の10倍はいるとのことで、ということは2012年には1400人の若い学生が「就職失敗」を理由に、自殺を試みている計算になる。
ライフリンクが現に就活活動を行っている大学生・大学院生200人を対象に行った意識調査によると、下のグラフに見るとおり、日本の社会に対してネガティブなイメージを持っている学生が非常に多い。
「正直者がバカを見る」のが日本社会であると学生たちが考えるのは、就活中にさまざまな「裏側」に遭遇するからです。本当は採用活動をしてはいけないとされている時期に水面下で「内々定」を出す企業があるし、「学歴不問」を謳っているのに実際には大学名でふるいをかける企業がある・・・というようなことで、「正直者がバカを見る」ような目に多くの学生たちが遭遇しているということです。
清水さんのトークの中で、私が最も面白いと感じたのは、彼の組織でインターンとして働く学生4人との会話の結果です。この学生たちも実は就活学生なのですが、清水さんが彼らに、就活自殺する若者の心境を理解できるか聞いてみたところ、全員が「理解できる」と答えた。その理由がとても面白い(とむささびは思う)。彼らの言葉によると、
- 自分は、自分たちは、小さい頃から周りの目に怯えながら生きてきた。
のだそうです。小中学校ではいじめられることを防ぐために、自分のやりたいことなど考えずに「できるだけ目立たないように、周りから排除されないためのキャラを、ずっと演じて生きてきた」と言うのです。そして高校生ともなると教師や親からの評価にも気を配るようになる。大学進学を希望するなら「学習意欲」の点でも高い評価をもらわなければというので、
- 演じてでも「やる気」をみせていかなければなりません。大人の顔色をうかがいながら、作り笑いをして、「いい子」を演じ続けてきたというのです。
そして、何とか大学に入ることができてほっとしたのも束の間、就職活動に取り組まなければならないわけですが、就活で企業回りをすると面接で必ず聞かれる質問が二つあるのだそうです。
- あなたの夢はなんですか?
- 他の人にできないことで、あなたにできることはなんですか?
ここで学生たちは面食らう。それまでほぼ20年間、「周りと同じようにしていなさいと言われ、自分の存在を消すように努力して生きてきた」というのに、いきなり就活で「あなた」を問われるのです。あなたの夢は?なんて聞かれても「はぁ?」というしかない。分かります?
で、仕方ないというので、やったこともない「自己分析」や「自分さがし」をやり、おぼろげながら見えてきた「自分」を必死になって入社願書のようなものに書き込む。しかもそれが一社や二社ではない。何十社もある。まさに気が狂うような「努力」をやっている。なのに、何十社も回って歩いてもどこも自分を受け入れてくれない。
- 小さい頃から、言われたように生きてきただけなのに、それでも自分の居場所や出番を与えてもらえないのだとしたら・・・。
清水さんのところでインターンをやっている学生たちが、就活自殺の増加について「理解できる」というのは、本当に死にたい・自殺したいという意味ではなく、「こんな人生、もう馬鹿馬鹿しくて生きるのを止めたくなる」という気持ちはよく分かるという意味である、と。ライフリンクの調査によると、就活を始めてから「本気で死にたい」「消えたい」と思ったことがあるという学生は21%に上ったのだそうです。5人に1人です。
清水さんによると、「不透明な採用プロセス」「ルールを守らない企業」などのゆがみが就活学生に「集中的に襲い掛かっている」として
- 就活自殺の背景にあるのは、私たち大人社会のあり方の問題でもあるのです。
と言っています。
▼生れてから20年、なるべく「自分」だけが目立つことがないようにしながら生きてきた若者が、就職の面接試験で「あなたの夢はなんですか?」と聞かれて戸惑う。で、戸惑いながらも適当な答えを探して書類に書き込んで送るけれど、返ってくるのは「不採用」の通知ばかり。確かに疲れるでしょうね。
▼ただ、私、清水さんの文章のこの部分を読みながら、戸惑う若者のことよりも、面接で「あなたの夢はなんですか?」とか「他の人にできないことで、あなたにできることはなんですか?」という質問をする企業の面接担当者のことを考えてしまった。清水さんによると、これは「必ず聞かれる」質問であるとのことです。同じ質問をする企業がたくさんあるということですよね。
▼両方とも「あなた」のことを語ってくれと言っている。別の言葉で言うと「個性」ということです。個性を話題にしているのに質問そのものはほかの社も聞いている(ことが分かっている)質問なのですよね。面接担当者の「個性」はどうなっているのか?ということです。
▼就活学生がどのような答えをしても、それは心から出たものではなくて、就職試験に受かるための標準的な答えであるということは質問者の方も分かっている。要するに質問する方も、される方も本気ではない。そのようなウソ芝居を上手に演じた方が勝ち・・・というようなゲームがまかり通っている。そのようなやり方で生きてきた「正社員」によって構成される日本企業に国際競争力など期待できるはずがないですよね。
▼自分でもいいとは思っていない「就活ルック」に身を包み、考えてもいない「私の夢」をあたかも本気で考えているように語る・・・いい加減に止めた方がいいですよ、学生さん。自分のためです。就職先は日本企業だけではない。 |
|
| back to top |
3)ラムズフェルド:破壊はするが建設はしない?
|
 |
ドイツの週刊誌、シュピーゲル(Der Spiegel)の9月16日付のサイトに、ブッシュ政権時代に国防長官だったドナルド・ラムズフェルド(Donald
Rumsfeld)との単独インタビューが掲載されています。主なる話題はシリアの化学兵器問題へのオバマ大統領の取り組みなのですが、自分が国防長官だったときに起こったアフガニスタンやイラク戦争についても語っています。記事はここをクリックすると読めます。一問一答形式で読みやすいけれど、そうとうに長い。例によって(むささびの独断で)面白いと思う部分だけピックアップしてみます。
オバマ大統領は、シリアへの爆撃について、米国の下院のみならず外国からの支持を取り付けるのにも大いに苦労しているわけですが、シュピーゲルの記者が「なぜこれほどの苦労をしているのか」と質問したのに対するラムズフェルド氏の答えは次のとおりです。
- オバマがシリア爆撃について米国内でも外国でも支持を得られない理由は、自分が何をしたいのか、爆撃の目的は何か、それによって何を得たいと思っているのか等について説明していないということにある。議会や外国の支持を得るためには、(意図が)明確であること、目標が無理のないものであること、結果として起こることが分かっていることなどが必要なのだ。
Rumsfeld: I believe the reason he has had difficulty gaining support both in the US and from other countries is because he has not explained what he hopes to do, what the mission would be and what he hopes to accomplish. To gain support in our Congress and from other nations requires clarity, an acceptable mission and an explicit outcome.
これに対してシュピーゲルの記者は「あなたが真面目に言っているとは思えない」(You cannot be serious)というわけで、イラク戦争をやってしまったブッシュ自身は自分の意思がはっきりしていたかもしれないけれど、現在ではほとんどのアメリカ人が、あの戦争ではブッシュ政府に騙されたと思っている。だからオバマのシリア爆撃に対する支持が非常に低いのでは?という趣旨の質問をしたのですが、それに対してラムズフェルド氏は、「アメリカ人は昔から戦争嫌いだった」として、第二次大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争なども実はやりたくなかったのだという趣旨の反論をする。これに対してシュピーゲルの記者が
- アメリカの見方からすれば、第二次大戦は「聖なる関わり」(noble engagement)であり、長い眼で見ればやっただけのことはあったと言えるかもしれないが、イラクやアフガニスタンに同じことが当てはまるとはとても思えない。
From the American perspective, World War II was a noble engagement that paid off in the long run. The same can hardly be said of Iraq and Afghanistan.
と反論。これに対してラムズフェルド氏がアフガニスタンでもイラクでも、アメリカがやったことのお陰で昔に比べれば社会はよくなっているではないかと反論すると、インタビューする記者が
- その言い方は冷たくて、不真面目と言ってもいいくらいだ。(イラクやアフガニスタンでは)何万人もの人間が命を落とし、何十億ドルものお金が費やされている。それでもこれらの国の将来が明るいのかどうかさえ分からない。だというのにアメリカは出て行こうとしている。自分たちのことは自分たちでやれというわけだ。
That sounds almost cynical given the thousands of people who lost their lives and billions of dollars those wars cost. And we still cannot be sure that these countries have a better future. But the US is now leaving them to their own devices.
とやり返す。このあたりからインタビューというよりも「激論」の様相を呈してくる。ラムズフェルド氏の反論は
- あんたが何を言おうと構わんがね、私の意見では、アメリカは他国に入って行って国の建設までやるような国ではないということだよ。それはその国の人々次第なんだから。
Call it what you will, but my view is that we aren't a country that can go into another nation and do nation building. That's up to the people in those countries.
というものだった。シュピーゲルの記者も黙ってはいない。
- イラクやアフガニスタンのような国に入って行って民主化のために体制転覆までやるのだとしたら、その国の再建を手助けするのが義務ってものなのでは?
If you go into a country like Iraq and change a regime to democratize the region, is it not your duty to assist in the rebuilding of the nation?
と迫る。それに対するラムズフェルド氏の答えは・・・
- 手助けはしますよ。しかしイラク戦争の目的は、あくまでも体制転覆であって、国家建設ではなかったということ。私は、「民主主義」という言葉が気になって仕方なかったのだ。選挙をやれば民主主義ができるってもんではないからな。ヒットラーだって元はと言えば選挙で出てきたのだからな。最近ではエジプトのムスリム同胞団だって民主的に選ばれたのだ。でも結果としては民主主義にはなっていないではないか。
We can certainly help, but the purpose of the war in Iraq was regime change, not nation building. I worried about the word "democracy." Elections don't make a democracy. Adolf Hitler was initially elected. More recently, the Muslim Brotherhood in Egypt was democratically elected. Neither resulted in democracies.
というわけで、この激論風インタビューは延々続いたのであります。ちなみにシュピーゲルの記者はMarc HujerとGregor Peter Schmitzという名前であったのですが、読者からの投書欄には「記者のインタビューは相手に失礼だ。シュピーゲルは左翼に譲り過ぎる」という批判的な意見もあったけれど、「戦争犯罪人のラムズフェルドのような人物の意見をなぜ聞く必要があるのだ」というのも結構ありました。
|
▼ラムズフェルドの「体制転覆はやるけれど国家建設まではやらない」という発想をどう思います?イラクやアフガニスタンのような国についてアメリカは「破壊」はするけれど「建設」はその国が自分でやるものだと言っているのですよね。他国へ勝手に乗り込んで行って「皆さんの指導者は悪人です。だからやっつけます。でもその結果、お国がどうなるかは皆さん次第です」と。いくらなんでもひどすぎるのでは?
▼タリバンやサダム・フセインは、欧米の基準からするとどうしようもない人たちかもしれないけれど、その国なりの長い歴史の中で出てきた指導者であることに変わりはない。だいいち彼らがアメリカや英国を爆撃したわけでもない。
▼戦前の日本は欧米によって完膚なきまでに破壊されましたよね。彼らに言わせると、当時の日本の指導者たちはタリバンやサダム・フセインのような人たちであったかもしれないけれど、決定的な違いは日本はアメリカを爆撃してしまった。オサマ・ビン・ラディンみたいなものですね。しかもアジア大陸では欧米を敵に回して帝国主義戦争をやっていた。ただアメリカは日本で「体制転覆」(天皇制の廃止)はやらなかった。終戦と同時にソ連相手の冷戦が始まっており、日本の体制を維持して、この国を前線基地にする必要があった。
|
|
|
back to top |
4)アイルランド大飢饉とThe Economist
|
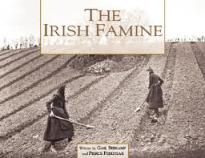 |
今からほぼ170年前の1845年、アイルランドで食糧飢饉が起こりました。ジャガイモの不作によるものでpotato famineと呼ばれています。この出来事と英国および雑誌The Economistの関係について、フェリックス・マーティン(Felix Martin)という人が書いた"Money: The Unauthorized Biography"という本が興味深い指摘をしています。
独立国であったアイルランドが「英国」(イングランド、スコットランド、ウェールズの連合王国)に併合されたのは1801年だったから、大飢饉が起こった1845年当時のアイルランドはすでにUnited Kingdomの一部となっていたけれど英国内でも極貧のエリアとして知られていた。当時の英国は産業革命の真っただ中で世界の工場として繁栄を謳歌していたのですが、アイルランドは農業経済から抜け出せずにいたこと、さらにその農業もポテトだけがほとんど唯一の作物だったことが貧困の背景にあります。
そして1845年9月、アイルランドのポテトが悲惨な不作であることがロンドンの中央政府に伝わった。ロンドンの政府は直ちに現地に視察団を派遣、英国内にはアイルランド救済委員会という慈善組織も立ち上げられた。アイルランド人たちがロンドンの中央政府からの援助が来るのを待っていたときに発行されたThe Economist誌が、1845年11月末の号で次のような書き出しで始まる社説を掲載した。
- 慈善こそが、イングランド人が犯す国民的過ちである。
Charity is the national error of Englishmen.
The Economistは、アイルランドの大飢饉は人間の悲劇には違いないが、だからと言って英国政府が援助の手を差し伸べるのは、経済の原則からしてアイルランド救済のためには「全く間違った方法である」(absolutely
the wrong way)と主張したのです。何が間違いなのかというと、一つにはアイルランド人の「モラル・ハザード」(moral hazard)を引き起こであろうということ。
- 支援をすることが当面の問題解決にはなるかもしれないが、そうすることでアイルランド人たちに永久的な依存体質に与えてしまう。
Send aid, and one might alleviate the immediate problem -- but at the cost of reducing the Irish to a state of permanent dependency.
つまり甘やかしはアイルランドの将来のためによくないということです。もう一つ・・・
- 二番目の問題点は市場の活動に(国家は)関与すべきでないという経済学における神聖なる原則を犯すことになる。
The second was the hallowed principle of non-intervention in the operation of the market.
ということであります。このポイントは、アイルランド大飢饉に先立つこと70年も前の1776年にアダム・スミスが発表したThe Wealth of Nations(国富論)という本でさんざ強調されていた。つまり経済というものは、個人が自らの利益を、政府に干渉されることなく自由に追求することによってのみ強くなり、社会的な問題も解決されるのだということです。つまりアイルランドの大飢饉を解決するべく政府が関与するというのは「愚かな過ち」(foolish error)にすぎないということであります。アイルランド人自らが何とかしなければならないということです。
大飢饉が継続する中で、The Economistはさらに翌年(1846年)3月の号でも同じような主張を繰り返します。「政府の不干渉」という、アダム・スミスが主張した自明の理(self-evident
truths)を否定するのは、客観的かつ科学的な事実(objective, scientific fact)を否定するものであり、
- それは算数における初歩的なルールを学ぶなと言っているのと同じで、2+2=5であると主張するようなものだ。
'appears like calling on us to unlearn the first rules of arithmetic, and do our sums by the assertion that two and two make five'
と決めつけた。
そして1846年8月、ポテトはやはり収穫されず2年連続の大飢饉という最悪の事態となり、一時はアイルランド全体に暴動が起こるようになった。The Time紙は「アイルランドは全滅だ(total annihilation)」として具体的な援助をするべきだと主張したのですが、当時のロンドンの政治家も官僚もアダム・スミスの信奉者が多く、見かねた首相のロバート・ピールが、10万ポンド相当のアメリカ産のトウモロコシ(動物の飼料用)をアイルランドに送ったのですが、それが不評を買って辞職に追い込まれたのだそうです。
"Money...."の著者であるフェリックス・マーティンによると、ロンドンの政治家や官僚たちは、アイルランドが「全滅」と報道されている事態にも関わらず、アダム・スミスの経済理論についての抽象的なディスカッションを続けており、The
Economistは翌年になっても、政府不干渉の原則を主張し続けた。
結局、この大飢饉によって100万人が餓死、100万人がアイルランドを捨ててアメリカやイングランドに移住した。つまりアイルランドは200万人もの人口を一挙に失ったのですが、これは当時のアイルランドの人口の3分の1にあたる数字なのだそうです。
フェリックス・マーティンはこのエピソードを、アダム・スミスの経済原則(人間が自分の利益を自由に追求していくことで全体として豊かになる)にこだわったThe Economist誌や当時のロンドン政府の指導層に批判的なトーンで書いているのですが、当時のオックスフォード大学で政治経済学を教えていた、アダム・スミスの信奉者であったナッソー・シニア(Nassau Senior)という教授が言ったとされる次の言葉も紹介しています。
- 私は、1848年のアイルランド飢饉による死者が100万人を超えることはないのではないかと恐れている。それだけでは慈善を施すに足るとは言えないからだ。
I fear that the famine of 1848 in Ireland would not kill more than a million
people, and that would scarcely be enough to do much good.
フェリックス・マーティンによると、当時は新しい思想であったアダム・スミスの自由主義経済の原則によって、それまで大切とされてきた道徳や政治の世界における正義(justice)という考え方が「客観的な科学上の真実」(objective scientific truths)にとって代わられてしまったわけです。
ところで、この本の中身とは直接関係ありませんが、アイルランド飢饉から150年目の1997年、アイルランドで行われた飢饉の犠牲者を追悼する集会が行われた際に、当時の労働党のブレア首相が声明を発表、
- 当時の英国政府は自らの国民が、作物の不作によって大いなる人間の悲劇に直面していたにもかかわらず見て見ぬふりをした。
Those who governed in London at the time failed their people through standing by while a crop failure turned into a massive human tragedy.
と述べています。このことを報じるThe Independent紙によると、ブレアさんは当時の英国政府が行った失政について「悲しみを込めて認めて」(he sadly noted)はいるけれど、謝罪はしていないのだそうです。「謝罪」をしてしまうと、あの頃に遡る形での責任(retrospective
responsibility)が生じてしまうからなのだそうです。
▼"Money: The Unauthorized Biography"という本について、現在のThe Economistはどのようなことを言っているのだろうと思って調べてみたところ、本そのものを紹介してはいるけれど、同誌の大飢饉当時の社説などについては全く触れていなかった。
▼飢えるアイルランド人救済のためには「政府は何もしないのが長い眼で見るといちばんいいのだ」とThe Economistは主張し、その理論的根拠が『国富論』の中でアダム・スミスが述べた政府の干渉なしに人間が自己利益を追求すれば、"見えざる手”によって経済が強くなって、全体的な貧困もなくなるという言葉にあったとフェリックス・マーティンは言うのですが、本当にアダム・スミスはそんなこと言ったのでしょうか?堂目卓生という人の『アダム・スミス』という本によると、「(人間の利己心によって動かされる)市場が公共の利益を促進するためには、市場参加者の利己心だけでなく、フェア・プレイの精神も必要だ」とアダム・スミスは考えていたとなっています。
|
|
|
|
5)どうでも英和辞書
|
A-Zの総合索引はこちら
|
to punctuate:句読点を入れる/文章を区切る
「ここではきものをぬいでください」という日本の文章は句読点の入れ方で意味が全く違いますよね。
- ここで、はきものを脱いでください
- ここでは、きものを脱いでください
英文にもこの種のややこしさがある。ある教師が下記の英文を黒板に書いた。
- woman without her man is nothing.
そして生徒たちに「正しく区切れ」(punctuate the words correctly)という問題を出したところ男子と女子では答えが違ったのだそうです。
- 男子の答え:Woman, without her man, is nothing.(男のいない女なんて何でもない)
- 女子の答え:Woman! Without her, man is nothing.(女性よ、女がいなければ男なんて何でもないのよ!)
|
|
back to top |
6)むささびの鳴き声
|
▼ヤクルト・スワローズのバレンティン選手が56号・57号のホームランを連発して王貞治の記録を破ったというニュースですが、最近なぜかプロ野球に興味がなくなっている「むささび」には、あまりピンと来ませんでした。記録を作ったのがバレンティンというガイジン選手であったからでは決してありません。正直言って、王貞治の日本記録にも世界記録にもさしたる想いはなかったのですが、それはワンちゃんが阪神タイガースや西武ライオンズの選手ではなかったということだけが理由です。
▼毎日新聞の「発信箱」というコラム(9月20日付)で、論説委員の福本容子さんが、近鉄バファローズのローズ(2001年)、西武ライオンズのカブレラ(2002年)がもう少しで王貞治の日本記録を更新しかけたときのことを書いています。そう、あのときは相手の投手が殆ど敬遠に近いようなボールしか投げずに記録更新を「阻止」したのですよね。実はその前、1985年に阪神タイガースが優勝したときも阪神のバースが54本のホームランを打った状態でシーズンの最終戦を迎えたけれど、殆どの打席が敬遠の四球で、バースのシーズン記録は54本で終わってしまった。あのとき敬遠などされなければ、間違いなくバースが新記録を出していた(と、当時はほんの少しだけトラキチだったむささびは考えた)。
▼いずれにしても可哀そうなのはワンちゃんで、彼はローズのときも、カブレラのときも、そしてバースのときもすべて相手チームの監督であったのですよね。だからあたかもワンちゃんが自分の記録を破られるのがイヤで、監督という立場を利用して自分のチームの投手に「敬遠」を命令したのだとか言われる立場になってしまった。ローズが記録更新をしかけたときには、王が監督をつとめるダイエーのコーチが「ローズに王さんの記録を抜かせるワケにはいかない」という発言をしたのですよね。バースのときは「四球・四球・安打・四球・四球」だった。お金払ってその試合でバースが新記録を作るかもしれないと思ってきたファンは怒ったでしょうね。
▼福本容子さんの「発信箱」に話を戻すと、彼女が言いたかったのは、バレンティンの新記録のことではなくて、日本の大企業において「最高経営責任者」と呼ばれる人の国籍です。世界の大企業250社で2012年に最高経営責任者になった人の25%が外国人(外国生まれという意味)であったのに対して、日本企業で外国人がトップにいるのは「日産のゴーンさんらほんの数人」だそうです。福本さんによると、日本人が外国人を「敬遠」してしまっている。野球であれビジネスであれ、本当は「競争は歓迎した方が結局自分を高める」のに、というわけです。
▼「ローズに王さんの記録を抜かせるワケにはいかない」という発想がまかり通っていたのがプロ野球の世界で、3人もの外国人強打者がその発想のおかげで記録を阻まれた。福本さんの言うように「競争の欠如」も問題かもしれないけれど、「フェアプレイ」の欠如こそが日本の最大のガンであるとむささびは思います。
▼いちおう聞いておきたいけれど、東電の社長に外国人を起用するなんてこと考えられていますかね。これから考える余地は?答えは両方ともノーだとすると、その理由は何なのでしょうか?そこがいちばん知りたい。福本さんによると
- 「お・も・て・な・し」はあくまですぐ帰るお客さん用。外部の人間が居座って主力になったり、内部の者の上に立ったりするのはあまり歓迎されてこなかった。
-
- となる。
▼最高経営責任者のようなすごい人たちのハナシではなく、企業に就職しようと悪戦苦闘している学生たちの「就活自殺」の増加はフェアプレイ(公明正大)の欠如に理由の一つがあることは間違いない。アダム・スミスの時代もいまも、キーワードが「フェアプレイ」であることは同じです。 |
|
back to top
|
←前の号 次の号→

message to musasabi
journal |
![]()